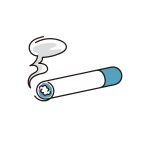当サイトの一部に広告を含みます。
関連投稿
住宅ローン選び
ライフプランから検討しませんか
住宅購入は、ほとんどの方にとって一生に一度の大きな決断です。その後の生活に大きな影響を与えることは想像しやすいのではないでしょうか。特に住宅ローンの選びは大切で、ローンの金利タイプにより返済額や家計への負担が大きく変わります。
変動金利と固定金利、それぞれに特徴があり、どちらがあなたに合っているかを見極める必要があります。まずは、両者の違いを理解することから始めてみましょう。
変動金利vs固定金利、どちらが自分向き?
①変動金利は天気予報
変動金利とは、金利が市場の動向に応じて変動する住宅ローン金利のことを指します。具体的には、銀行等の金融機関が定めた基準金利(たとえば、短期金利や長期金利)に連動して金利が変動し、それに合わせて返済額が変動します。
想像しやすいよう日常的なものに例えると、天気予報のようなものです。天気予報は予測できる部分はありますが、急な天候の変化に対応しなければならないこともあります。変動金利も同じく、金利が安定しているように感じても、外的な要因により急な変動も起こり得るリスクがあります。
②固定金利は定期預金!
固定金利とは、住宅ローンの金利が契約期間中は一定で、変動しないタイプの金利を指します。契約時に設定された金利は、返済完了まで変わることはない点が定期預金に近いといえるでしょう。
定期預金ですと途中で利率が変わらない反面、決まった利率が適用され続けるので安定した運用が可能ですよね。
③ハイブリッドローンは美味しいとこ取り?
ハイブリッドローンとは、一定期間の間は固定金利が適用され、その後に変動金利へ移行するローンをいいます。例えば、最初の5年間は固定金利で、残る返済期間は市場金利に応じて変動する形態がこれにあたります。
| 金利タイプ | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 変動金利 | 市場金利に連動し、金利が変動する | ・初動金利が低いケースが多い ・金利が下がると返済額も減少する可能性がある | ・金利が上がると返済額も増える可能性がある ・長期的な返済計画が立てづらい |
| 固定金利 | 金利が契約時に決まり一定 | ・返済額が一定で安定している ・金利の変動に左右されない | ・初動金利が高めに設定されるケースが多い ・金利が下がってもその恩恵を受けられない |
| ハイブリッドローン | 一定期間は固定金利を適用し,その後は変動金利に移行する | ・最初の数年は安定した返済ができる ・その後、金利が下がればお得になる可能性がある ・一定期間の金利固定が精神的安定に繋がる | ・金利の変動タイミングにより支払が増える可能性がある ・全期間固定されないため、長期的に見ると安定性に欠ける |
【例1】30代 家族が増えるタイミングでローンを組む場合
たとえば、30代に差し掛かり、家族が増えるタイミングで住宅ローンを組む場合を考えてみましょう。お子さんができると、生活費や教育費など、将来への積み立てを検討する必要がありますよね。こうした状況では、「安定」や「予測可能性」を重視したくなるのではないでしょうか。なぜなら、急激な金利高騰により家計が大きく影響を受ける可能性があるからです。
この場合、固定金利のほうが将来的な支出を見通しやすく、今後の生活に対する不安軽減につながります。
【例2】独身時代にローンを組む場合
一方、独身時代に住宅ローンを組む場合、ライフプランの柔軟性は比較的高いでしょう。今後、結婚や家族の計画があったとしても、金利が下がればラッキー、上がっても「自分次第でどうにかできる」という自信も持てる。こう考えると、変動金利が魅力的に映るのではないでしょうか。
どちらを選ぶのが正解か?
金利の選択に際し、どちらが良い・悪いと断言するのは至難の業です。そのため、以下を参考に検討しましょう。
1.変動金利がオススメな人
変動金利は、市場金利に連動して金利が連動しますので、金利が低い時期にはお得感があります。その一方で、金利が上がったときには返済額が増える可能性もあります。これらを踏まえ、以下に該当する方には変動金利がオススメだと考えます。
- 早期返済を考えている場合
- 収入に余裕があり、金利上昇のリスクを受け入れられる場合
- 柔軟な返済計画を希望する場合
【例3】Aさんのケース(30歳 独身、数年内に転職予定)
Aさんの場合、将来的にライフスタイルが大きく変わる可能性があります。そのため、長期的な返済計画を立てる必要がありませんので、変動金利がオススメだと考えます。特に初動金利を低く設定する金融機関が多く、金利が安定している間なら返済額が抑えられる点はメリットだといえます。
また、数年以内に転職と引っ越しを予定しているため、比較的短期間でのローン返済が望ましいかと思います。仮に転職後に住まいが変わる場合は、そのタイミングで住宅を売却し繰り上げ返済を行うことも考えられます。
2.固定金利がオススメな人
固定金利は、金利が変動しないため、毎月の返済額が一定です。そのため、安定した返済を続けられる一方で、金利が下がっても恩恵を受けることはできず、将来の金利動向を予測できない不安がつきまといます。これを踏まえ、以下に該当する方には固定金利をオススメします。
- 将来の収入や支出への不安が大きい場合
- 安定した収入が確保されている場合
- リスクを回避したい場合
【例4】Bさんのケース(35歳 既婚+子どもあり)
Bさんの場合、夫婦共働きで安定した収入があるものの、お子さんにかかる教育等に不安を感じていらっしゃいます。このように、将来的な支出が予測されるときには固定金利が安心かと思います。
特にお子さんの教育費や老後資金をしっかりと準備したい場合には、金利の変動による家計への不安を減らし、より生活設計がしやすい固定金利が望ましいのではないでしょうか。
3.ハイブリッドローンがオススメな人
ハイブリッドローンは、変動金利と固定金利の良いところを取り入れたローンタイプで、以下の方にオススメです。
- 初動は安定した金利を希望し、将来の金利上昇に備えたい場合
- 将来の経済環境が不確実で、一定期間の金利変動リスクを避けたい場合
- 短期間の住宅ローンを検討している場合
- 家族構成やライフプランが不確定な場合
- 短期間の返済後、再借り入れや借り換えを検討している場合
【例5】Cさんのケース(32歳 独身、先行きが不透明)
Cさんは独身で、今はお子さんもいらっしゃらないものの、いずれ結婚し家族を持ちたいと考えています。そのため、独身の間は安定した返済額を確保し、将来的には金利を抑えられたら良いのにーと感じています。ですので、最初は固定金利を選び、生活が安定している間に計画的な返済を進め、その後は金利が低くなるタイミングを見計らい変動金利に切り替えたほうが有利でしょう。
また、Cさんのように将来的にライフプランの大きな変更が予測される場合には、最初の固定金利期間で安心感を得て、その後の金利動向に合わせた柔軟な対応が実現できるのはハイブリッドローンの大きな魅力だと言えます。
住宅ローンの借入先
住宅ローンの借入先として、以下が考えられます。
1.銀行(メガバンク、地方銀行)
三菱UFJ銀行や三井住友銀行、みずほ銀行等のメガバンクや、横浜銀行や静岡中央銀行などの地方銀行が考えられます。
①メリット
メガバンクや地方銀行の場合、安定した金利による提供が期待でき、特に有利な条件を選べることもあります。また、大手銀行は信頼性が高いことから、安心して借り入れることができます。
インターネットバンキングやローンの借り換えサービス等、サービスが充実している点も魅力ですよね。
②デメリット
金利が安定している反面、審査基準が厳しく、条件に合わなければローンが承認されないこともあります。また、手続きが複雑で時間を要することも多い点には注意しましょう。
2.信用金庫・信用組合
地元に根差した信用金庫や信用組合も住宅ローンを提供しています。これらの金融機関は、地域密着型のサービスが多く、特に地域住民に優遇措置をとることもあります。
①メリット
信用金庫や信用組合の住宅ローンを活用する場合、地元での信用が高く、柔軟な対応が期待できます。また、他の金融機関に比べ良心的な条件を提供しているところもあります。
②デメリット
これらの機関では、地域限定や特定の条件に依存する場合もあり、銀行に比べると審査基準が厳しいこともあります。また、大手銀行に比べ、サービスの選択肢や支店数が少ない場合もある点に注意しましょう。
3.ネット銀行
楽天銀行や住信SBIネット銀行、ジャパネット銀行などのネット銀行は、店舗を持たず、インターネットを通じて取引を行います。
①メリット
ネット銀行の場合、店舗を設けていないことから運営費用がかからず、他行に比べて金利が安く設定されていることが多いです。また、ローンの申し込みや手続きについてもインターネットを通じて行うことができ、便利でスピーディーに進められる点が魅力でもあります。
②デメリット
ネット銀行は、対面での相談やサポート対応が難しいため、オンラインでの手続きに不安がある人にはオススメいたしかねます。また、保証人や保証会社が必要なケースがほとんどですので、あらかじめ周りの人に相談しましょう。
4.フラット35(住宅金融支援機構)
フラット35とは、政府系金融機関である住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)から提供される住宅ローンを指し、主に長期固定金利の住宅ローンでもあります。
①メリット
フラット35は、長期固定金利のため、ローン期間中に金利変動の不安がなく、返済計画が立てやすい点が魅力です。また、大手銀行に比べると審査基準は比較的緩やかで、幅広い人々が活用しています。
②デメリット
他の金融機関に比べると金利が高いことも多く、長期的にみると返済額が大きくなる場合があります。また、住宅の省エネ性能に関する基準を満たさなければならないこともありますので、注意が必要です。
5.保険会社(住宅ローン保険)
一部の保険会社は住宅ローンを提供しており、生命保険とセットになっているプランもあります。
①メリット
保険会社が提供する住宅ローンの場合、万が一に備えた保険がセットになっているものが多く、安心感を得られる点はメリットだと言えます。
②デメリット
住宅ローンだけでなく保険が付帯するため、他行に比べて金利が高く設定されるケースが多いほか、取扱っている保険会社が限られており、選択肢が少なく感じる点はデメリットかもしれません。
住宅ローンを選ぶ際のポイント
住宅ローンを選ぶ際は、以下のポイントに注意しましょう。
- 団信の内容を確認する
- 諸費用の内訳を確認する
1.団信の内容を確認する
団信(団体信用生命保険)とは、受託ローンを借りる際に加入するもので、借主が死亡、または高度障害になった場合に残債務を保険でカバーすることを目的とした生命保険を指します。
①団信のメリット
団信のメリットは、借主の万が一のことが合った場合にローンの返済免除が受けられ、遺族の生活が守られることです。また、通常の生命保険と比べると低廉(安価)で、住宅ローンの金利に含まれる場合が多いため、個別で加入する手間が省かれるケースがほとんどです。
②団信のデメリット
基本的に、団信の対象は「死亡」、または「高度障害」となった場合であり、病気や事故、軽度の障害は保障対象外となる点に注意が必要です。加えて、加入後にはその内容や保障範囲を変更できない場合がありますので、注意しましょう。
2.諸費用の内訳を確認する
住宅ローン契約に際し、事務手数料や保証料が必要です。これらの金額は一律で定められるものではないため、契約前に複数社で検討するのがオススメです。
①事務手数料
事務手数料は、住宅ローンの申込みの際に必要な手続や書類の準備、契約書の作成に係る費用をいいます。多くの銀行では3万~5万円程度で設定されますが、一部の金融機関やネット銀行の中には無料のところもあります。
事務手数料が安いからといって、ローンの金利まで安いとは限らない点に注意しましょう。
②保証料
保証料は、住宅ローンの返済が滞った場合に備え、保証会社が肩代わりするための費用をいいます。一般的に、以下の方法で算出されます。
| 一括前払 | 契約時に一括で支払う方法 通常、借入金の0.5~2%程度で設定されます |
| 金利に上乗せ | ローン金利に保証料分を上乗せする方法 たとえば、金利0.5%に保証料分を0.1%上乗せし、実質的には0.6%となるケースが該当します |
③その他
住宅ローンに関する費用について、事務手数料や保証料の他にも以下が含まれます。
| 印紙税額 | 2万円~ ※借入額により異なります |
| 火災保険料(地震保険料) | 15万~50万円程度 |
| 不動産取得税 | 不動産価格×4% |
| 登録免許税 | 不動産価格×0.4% ※事例により異なります |
| 固定資産税 | 固定資産税評価額×1.4% |
| 仲介手数料 | 仲介者により異なります |
| 登記代行手数料 | 10万~15万円 |
住宅ローン選びに関するよくある質問(FAQ)
Q1. 住宅ローンを選ぶ際、変動金利と固定金利どちらを選ぶべきですか?
A1: 結論から言うと、絶対的な回答はありません。どちらが良い悪いで決められるものではないのです。
たとえば、変動金利は金利が低く、初期の返済額が少なく設定されることが多いので短期的には有利です。しかし、金利が上昇すると全体の返済額が増えるリスクがあります。いっぽう、固定金利は返済額が安定的で、将来の金利上昇リスクを回避したい人に向いていますが初動は高め。
双方の長短を見極め、ライフプランに応じて選択が必要です。
Q2. 住宅ローンを借りる際の理想的な借入額はありますか?
A2: 一般的に、借入額は年収の5倍程度が目安とされます。
ただし、返済能力や生活費、将来の支出を考慮し、あなたにとって無理のない範囲で借入額を設定するのが望ましいので、あくまで参考程度に捉えてくださいね。
Q3. 住宅ローンの返済期間は何年が適当ですか?
A3: 一般的な返済期間は30年ですが、短期間で返済したければ20~25年、反対に、月々の返済額を減らしたい場合は35年も選べます。
ですので、返済額を抑えたい場合は長期間、早期に完済したい場合は短期間を選び、ライフプランに合わせ調整しましょう。
Q4. 住宅ローン以外に(事務)手数料や保証料はどれくらいかかりますか?
A4: 一般的な事務手数料は3万〜5万円程度、保証料は借入額に応じ0.5%〜2%程度です。保証料が金利に上乗せされることもあるので、総支払い額で比較することが大切です。
Q5. 住宅ローンの繰り上げ返済はいつから始めるべきですか?
A5: 繰り上げ返済は早期に始めるほど利息の軽減につながります。
金利が高い時期に繰り上げ返済を行うと効果的ですが、生活資金に余裕があるタイミングで始められるといいですね。
Q6. 住宅ローンの審査基準はどのようになっていますか?
A6: 住宅ローンの審査について、年収や勤続年数、返済比率(収入に対する月々の支払い額)などが重視されます。また、借入額や返済期間、信用情報も審査の重要な要素となりますが、総合的に見られるのがベターだと考えます。
Q7. 住宅ローンの借り換えは本当にメリットがありますか?
A7: 住宅ローンの借り換えについて、金利が低くなったタイミングで行うと効果的(メリットがある)です。借り換えの際は、手数料や手続きの費用もかかりますので、総支払額で比較して判断しましょう。
Q8. 住宅ローンの金利が上がった場合、月々の返済額はどのように変わりますか?
A8: 変動金利の場合、金利が上がると月々の返済額が増えます。具体的には、金利の上昇に伴い、月々の利息部分が増加し、返済額の中で元金部分が減少することになります。そのため、返済期間が延び、支払額が増えるリスクがあります。
たとえば、借入額が3,000万円、金利が1.0%から1.5%に上がった場合、月々の返済額(元利均等返済の場合)は、数千円から1万円程度増えることになります。
これについては、(1)金利上昇前に繰り上げ返済で元金を減らす、(2)変動金利から固定金利へ移行するなどの対処法が有効だと思われます。
Q9. 住宅ローンの借り入れ前に必要な書類や手続きは何ですか?
A9: 住宅ローンの申し込みに関し、収入証明書(源泉徴収票など)、本人確認書類(運転免許証など)、物件の売買契約書、健康保険証などが必要です。事前に準備しておくとスムーズに進みます。
手続について、(1)融資の申込み、(2)審査、(3)仮審査結果の通知、(4)本審査、(5)契約、(6)融資実行という流れで進むことになります。
Q10. 住宅ローンにおける団体信用生命保険(団信)は必要ですか?
A10: はい、必要な場合が多いです。
住宅ローンにおける団信(団体信用生命保険)は、多くの金融機関ではローン契約の条件として強制加入となっており、万が一、ローン契約者が死亡または高度障害により返済ができなくなった場合、残りのローン残高が保険で支払われる仕組みです。
団信に加入したくない場合や、保障内容を変更したい場合、ローン金利が高くなる可能性があるほか、団信をつけることで得られるはずの保障が得られませんので、生命保険等に別途加入する必要が生じるかもしれません。
Q11. 住宅ローンの金利タイプを変える場合、どのタイミングで変更するのが得ですか?
A11: 変動金利から固定金利に切り替えたい場合、市場金利が低いタイミングで変動金利を選んだ後、金利が上がる前に固定金利に切り替えると良いでしょう。反対に、固定金利から変動金利に切り替える場合は、市場金利が低いタイミングを見計らうことがポイントです。
Q12. 住宅ローンの金利以外に、選ぶ際に気をつけるべきポイントはありますか?
A12: 金利のほかに注意すべきポイントとして、(1)返済方法(元利均等返済、元金均等返済)、(2)返済期間、(3)手数料や保証料、事務手数料などが挙げられます。また、繰り上げ返済や返済計画の柔軟性(返済額変更や支払いの一時停止など)についても確認しておくと安心です。
Q13. 住宅ローンを早めに完済したい場合、どの金利タイプが有利ですか?
A13: 早期に完済したい場合、金利が低い変動金利が有利ですが、金利の上昇リスクを受け入れられる場合に限るかと思います。固定金利は返済額が一定で安定しているため、途中で返済がしやすいという点で有利です。