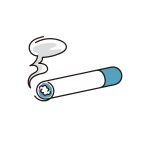当サイトの一部に広告を含みます。
遺産に「投資信託」が含まれていたら?
自分でできる相続手続の進め方と注意点を解説
親や配偶者が亡くなり、相続手続を進めるとき、遺産の中に「投資信託」が含まれていたら―預金や不動産と比べ、どう対応すればよいのか迷う方も多いはずです。
投資信託は、株式や債券、不動産等に間接的に投資できる金融商品で、近年は資産運用の一環として広く利用されています。
しかし、その相続手続は、一般の預貯金とは異なる点もあり、少し注意が必要です。
本記事では、遺産に含まれる投資信託について、相続手続の進め方と必要書類、分割方法、税務上の注意点までを、専門家に頼らずご自身で進めたい方向けに、できるだけわかりやすく整理しました。
投資信託とは?簡単におさらい
投資信託(ファンド)とは、投資家から集めた資金について運用のプロ(投資信託会社など)がまとめて管理・運用する仕組みです。
投資先は、株式・債券・不動産など多岐にわたり、購入者(=受益者)は、その運用効果の一部を「分配金」等の形で受け取ります。
✅ 銘柄を選ぶのは運用会社なので、自分で個別株を選ぶ必要がありません
✅ 価格は毎日変動し、1口あたりで売買されます(これを「基準価額」と呼びます)
相続では、「誰がこの投資信託を引き継ぐのか」が大切です。
ここでいう”引き継ぐ”とは、「将来の運用益や分配金を受け取る権利」のことです。
専門的な言い方をしますと、投資信託を持っている人を”受益者(じゅえきしゃ)”といいますが、ここでは「将来の運用益や分配金を受け取る人」と理解していただければ十分です◎
投資信託の相続手続:3つの進め方
相続手続の進め方は、状況により大きく3つに分けられます。
- 遺言書がある場合
- 遺産分割協議を行う場合
→遺言書がない/内容と異なる分割を希望 - 協議がまとまらない場合
→家庭裁判所で調停・審判
1.遺言書がある場合
故人が有効な遺言書を残している場合、その内容が優先されます。投資信託についても、以下のような指定がされている可能性があります。
- 指定した相続人に投資信託を現物で引き継がせる(名義変更)
- 投資信託を一度売却し、現金で分ける
- 特定の相続人にすべて譲渡する
遺言書の内容を確認し、どのような形で引き継ぎが指示されているかをまず確認しましょう。
1.1. 遺言書の検認手続き
| 遺言書の種類 | 検認の要否 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言書 (自分で書いた遺言) | 通常は必要※ | 家庭裁判所での「検認手続き」が必要です※ |
| 公正証書遺言書 (公証人が作成) | 不要 | そのまま手続きに使えます |
「検認」とは、裁判所が遺言書の内容や保管状況を確認する手続きをいい、遺言の有効性を判断するものでない点に注意しましょう。
💡 自筆証書遺言でも“検認不要”にできる方法があります
2020年からスタートした「法務局の自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、通常必要な検認手続きが不要に。制度の概要や手続き方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
👉 自筆証書遺言書保管制度とは?制度のポイントと使い方を解説
2.遺産分割協議をする場合
遺言書がない、または内容と違う分け方をしたいときの進め方
遺言書がない場合や、遺言の内容と異なる形で財産を分けるには、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰が、何を、どのように相続するかを話し合いで決める必要があります。
投資信託が遺産に含まれる場合でも、この話し合いを経て、
✅投資信託をそのまま分ける(現物分割)
✅売却して現金化し、分ける(換価分割)
✅一人が受け取り、他の人に代償金を支払う(代償分割)
といった方法を選ぶことになります。
2.1.投資信託のの分け方は3パターン
| 種類 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 現物分割 | 投資信託をそのまま相続人で分ける 例:AさんとBさんが半分ずつ名義変更 | 同じファンド内でも単位未満株があると端数処理が必要になることも |
| 換価分割 | 投資信託を売却し、現金化してから分ける | 売却時点での価格により、受け取る額が変動する |
| 代償分割 | 1人が投資信託を受け取り、他の相続人にその分の現金などで”代償”を支払う | 贈与税のリスクを避けるため、遺産分割協議書に明記が必要 |
2.2. 遺産分割協議書を作成する際の注意点
相続人全員で合意に至ったら、「遺産分割協議書」を作成します。
この書類は、金融機関などでの手続きに必須となるため、内容に漏れや曖昧さがないよう注意が必要です。
🔍記載しておきたいポイント
- 亡くなった方の氏名・生年月日・住所
- 相続人の氏名・生年月日・住所・続柄
- 投資信託の内容(金融機関名、銘柄、証券口座番号、評価額など)
- 分割の方法(現物・換価・代償)を具体的に明記
- 相続税がかかる場合の費用負担の分担方法
💡相続税の申告や支払いに関係する内容もここに記載しておくと、あとでトラブルになりにくくなります。
👉 詳しい書き方やサンプルは
【関連記事】遺産分割協議書を自分で作成するための完全ガイド!
2.3. 投資信託の評価方法
投資信託の評価は、税務上の取り扱いとして以下の2つに分類されます。
(1)貸付信託受益証券(信託銀行が管理)
-
元本の額+既経過収益額-源泉所得税相当額-買取割引料
-
信託銀行が提示する「買取金額」をベースに計算
(2)証券投資信託受益証券(一般的な投資信託)
-
1口あたりの基準価格 × 口数 + 未収分配金 などを基準に算出
-
MMFなどの日々決算型と、それ以外で評価方法が異なる
📌 上場している投資信託(ETFなど)の場合は、株式と同様の評価方法(相続発生日の終値など)で計算されます。
👉 詳しくは
【関連記事】相続時に知っておくべき株式の評価方法と手続きのポイント
3.調停・審判をする場合
相続人同士で話し合いがまとまらないときは家庭裁判所へ
遺産分割協議で相続人全員の合意が得られない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。
調停は、家庭裁判所に設置される「調停委員会」が間に入り、相続人同士の合意を目指す手続きです。
調停が成立すると、その内容に基づいて相続手続を進めることができます。
3.1.調停でもまとまらなければ「審判」へ
調停で話がまとまらなかった場合は、手続きは「遺産分割審判」に移行します。
この場合、家庭裁判所の裁判官がすべての事情を踏まえ、最終的な分け方を決定します。
調停や審判になると、時間や手間だけでなく、心身の負担も大きくなります。
できるだけ話し合いでまとまるのが理想ですが、どうしても合意が難しいときは法的手続きを検討しましょう。
投資信託の相続手続き:流れと必要書類まとめ
手続きを自分で進めるための実務チェックリスト
投資信託の相続は、以下のステップで進めていきます。
1. 証券会社・信託銀行に「死亡の連絡」
故人が投資信託を保有していた証券会社や信託銀行に、「死亡の事実」を連絡します。
手元に残高証明書や運用報告書がある場合は、そこに記載された金融機関・口座番号を確認しましょう。
残高が不明な場合は、まず残高の有無を照会することから始めます。
金融機関により専用窓口や相続専用ダイヤルがありますので、そこに問い合わせるとスムーズです。
2. 必要書類をそろえて提出
手続きに必要な書類は、「遺言書がある場合」と「遺産分割協議をした場合」とで異なります。
①遺言書がある場合
- 遺言書
- 自筆証書の場合は検認済調書(保管制度利用時は不要)
- 故人の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(出生から死亡までのすべて)
- 相続人全員の戸籍謄本※
- 投資信託を引き継ぐ人の印鑑登録証明書
- 遺言執行者の印鑑登録証明書(任命されている場合)
- 金融機関所定の相続届・申請書類など
②遺産分割協議を行った場合
遺言書がない場合や、遺産分割協議を行った場合、以下の書類が必要です。
- 遺産分割協議書
- 故人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本※
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 金融機関所定の申請書類など
📎 多くの金融機関では、「法定相続情報一覧図の写し」があれば戸籍の一部を省略可能です。
👉 詳しくは
【関連記事】法定相続情報証明制度の使い方と注意点
3. 証券口座の名義変更または開設・移管
- 相続人がすでに同じ証券会社に口座を持っていれば、その口座に名義変更が可能です
- 持っていない場合は、相続人自身の証券口座を開設し、移管手続を進める必要があります
代償分割を選んだときの注意点
代償分割で、ある相続人が投資信託を相続し、他の相続人に現金を支払う場合、原則として贈与税はかかりません。
ただし、以下の場合は注意が必要です。
- 遺産分割協議書に「代償分割であること」を明記していない
- 相手に支払う金額が自分の法定相続分を超えてしまっている
たとえば、3人兄弟で1,000万円ずつが本来の取り分なのに、ある相続人が3,000万円ぶんの投資信託を相続し、他の2人に2,000万円ずつ払ってしまったばあい、受け取った側に贈与税が課税される可能性があります。
換価分割を選んだときの注意点
換価分割(投資信託を売却して現金で分ける)については、原則として非課税ですが、やはり遺産分割協議書にその旨を明記しておくことが大切です。
協議書に「売却の上、分配する」旨を記載しませんと、形式的に贈与とみなされるリスクがあります。
おわりに
専門家に頼らなくても、相続手続は進められる
投資信託の相続は、預金や不動産と違い、評価方法や名義変更の手続きに独特のルールがあります。
そのため、「難しそう」「自分では無理かも…」と感じる方も少なくありません。
けれど、ポイントを押さえて書類をきちんとそろえれば、自分で進めることも十分可能です。
特に、相続人同士で協力しながら分け方を決められる状況であれば、必要な書類や段取りをひとつずつ確認していけば手続きは着実に進めることができます。
この記事では、「遺言書がある場合」「協議をする場合」「調停や審判に進む場合」といった状況別に、
具体的なステップや注意点を解説してきました。
手続きに不安があるときは
もちろん、「何をどう書けばいいのかわからない」「この書類で大丈夫か確認したい」といったときは、行政書士や税理士、弁護士などの専門家に相談するのもひとつの方法です。
特に、
-
相続人が複数いて話し合いが難航している
-
相続税の対象となる財産がある
-
投資信託の分け方に迷いがある
といったケースでは、早めの相談がトラブルを防ぐ鍵になります。
相続は「いつかやること」ではなく、ある日突然「今すぐやらなければならないこと」になります。
大切な人の思いと財産をきちんと受け継ぐためにも、まずは一歩、はじめてみましょう。