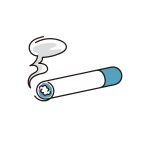当サイトの一部に広告を含みます。
Contents
関連投稿
子どもがまだ小さいから
妻の仕事の都合もあるし
家のローンもあるし、親の介護も…
気づけばいつも、自分のことは後回し。
けれど、本当にそうしたかったのでしょうか。そうするしかありませんでしたか。
20代の頃に描いた未来図。
30代になって諦めた挑戦。
40代目前でふと湧き上がる、この問い。
「このまま、何もせずに終わっていいのか?」
もしもあなたがそう思う瞬間があったのなら、再スタートのきっかけに「行政書士」という資格が合うかもしれません。
- 学歴や職歴が問われない
- 家庭と仕事を両立できる柔軟な学習スタイル
- 合格後は「開業」「副業」「別資格へのステップアップ」等の選択肢がとれる
これは、誰にも邪魔されない「静かな反撃」の一歩。
この先に待っているのは、「誰か」のための人生でなく、あなた自身が選ぶ人生です。
第1章|行政書士試験とは何か:制度と現実を知る
「資格試験」と聞いたとき、まず気になるのは合格の可能性ではないでしょうか。
特に、学業を修めてからブランクがある方や、勉強の習慣がない人ほど、「自分には無理だろう」と結論づけてしまいがち。
けれど、行政書士試験は独学でも十分突破できる国家試験です。
■ 受験資格はゼロ
行政書士試験について、受検資格は、年齢、学歴、国籍等に関わらず、誰でも受験することができます。
ただし、合格後に行政書士として活動する際は「登録要件」を満たす必要がある点に注意しましょう。
極端な話、幼児でも字の読み書きができれば受験することができます。
■ 試験制度の概要
| 試験日 | 毎年1回、11月の第2日曜日 午後1時~午後4時まで3時間 |
| 試験会場 | 毎年7月の第2週に公示 住まいや住民票記載住所に関係なく、全国の試験会場で受験可能 |
| 出題形式 | 五肢択一のマークシート方式、一部記述有り |
| 試験科目と内容 | 「行政書士の業務に関し必要な法令等」(出題数46題) 憲法、行政法(行政法の一般的な法理論/行政手続法/行政不服審査法/行政事件訴訟法/国家賠償法及び地方自治法が中心)、民法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題 |
| 「行政書士の業務に関し必要な基礎知識(出題数14題) 一般知識、行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令、情報通信・個人情報保護及び文章理解の中からそれぞれ出題 | |
| 合格基準 | 次のいずれも満たすこと 1.行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が122点以上 2.行政書士の業務に関し必要な基礎知識科目の得点が24点以上 3.試験全体の得点が180点以上 詳細はこちらからご確認いただけます。 |
| 受験手数料 | 10,400円 ※2025年7月1日現在 |
| 合格率 | 約10~15% ※毎年変動有り |
※法令は試験実施日の属する年度の4月1日時点で施行されているもの
合格率だけを見ると狭き門に見えるかもしれませんが、多くの受験生は対策不足・記念受験・準備不十分です。(毎年欠席者も多く見られます)
そのため、戦略的に取り組めば、十分射程圏内だといえます。
■ 合格者の“主な年齢層”は、30〜40代
直近3年間における行政書士試験の合格者の属性を見ると、最多は30代~40代となっています(出典:最近3年間における行政書士試験の受験者・合格者の属性 令和7年1月29日)
つまり、学生や新卒でなく、家庭や仕事の合間を縫って学習した人たちが合格している現実があります。
同じように悩み、時間のやりくりに苦しみながらも、一歩ずつ積み上げた人が“届いている”資格なのです。
■ 独学も可能、でも戦略は必須
行政書士試験は、独学で合格することが可能です。
ただし、“気合と根性”だけで突破できるものではない点に注意しましょう。
- 出題範囲が果てしない
- 記述式の制度
- 合格ラインのクセ
これらの壁を越えるには、戦略が必要です。
とはいえ、仕事や家庭と両立させて合格した人も少なくありません。
第2章|なぜ、行政書士が“キャリア再設計”に適しているのか
家族がいるから下手に動けない
仕事を辞めるなんてとんでもない
このようなしがらみを抱えている人にこそ、行政書士資格はオススメです。
以下、具体的にその理由を見ていきましょう。
■ 国家資格なのに、生活と両立できる“試験設計”
行政書士試験は、毎年1回のペースで実施され、出題範囲や傾向が比較的安定しています。
つまり、限られた時間内でも積み上げられる構造だといえるのではないでしょうか。
同じ士業資格のうち、司法書士や社労士は膨大な科目数を抱えるものと比較しても、学習時間1年での合格も現実に狙えるのがこの試験の大きな特徴です。
ちなみに、私は2回の不合格を経験しています😇😇😇
■ 合格後、すぐ登録しなくていい
行政書士を名乗るには、試験に合格後、「登録手続」を経る必要があります。
しかしながら、登録手続に期限はありませんので、合格さえすれば登録≒開業時期についてはあなたに決定権があります。
たとえば、
- 子どもが就学したら
- 本業に関わる法務や契約時に知識のみを活かす
- 就職・転職活動で国家資格保持者であることをアピールする
このように、いきなり行政書士を名乗らずとも、家族や生活環境に応じた“解像度”で活かすことができるのです。
■ 独立開業にも、副業にも、社内活用にも強い
行政書士には、資格取得後にいくつか分岐点があります。
| 開業タイプ | 本人の得意分野や経歴、人脈を活かし、0→1で事務所設立 |
| 副業タイプ | 副業解禁の波に乗り、許認可申請や届出業務、書類作成等を請け負う |
| 社内活用タイプ | 契約、コンプライアンス、許認可が関わる部署で資格を活かす ※この場合、「使用人行政書士」として登録が必要です |
選択肢が限局的でないことから、いきなり”詰む”可能性は低いといえます。
■ “言葉”と“知識”で稼ぐ仕事だから、体力や年齢の影響を受けづらい
行政書士最大の武器は、頭脳×文章力。
言い換えるなら、加齢や体力の衰えに影響を受けづらい職業だといえます。
- 若い頃より落ち着いて対応できる
- 経験を活かし、クライアントと向き合える
- 定年がなく、一生現役でいられる
そのため、いくつであっても“遅すぎる”ことはなく、目指したときが適齢期ではないでしょうか。
■ ひとりで始められる
行政書士として開業する際、以下が必要です。
- 登録費用
- 事務所
- 電話番号(スマホで◎)
- パソコン、プリンタ等の電子機器
- 鍵付き金庫 など
行政書士として登録するには、各都道府県に設置される行政書士会(単会)経由で日本行政書士会連合会に登録申請を行う必要があります。
この際、事務所としての要件を満たす必要があるのですが、各単会により要件が異なりますので事前にご確認ください。
開業に際し、多くの人が「資本金」や「人脈」、何らかの「許可」が必要なのでは?と考えるようですが、これらは必要ありません。
第3章|家庭と仕事がある人のための行政書士・学習戦略
やる気はあるけど、時間がない
1日のうち、座ってる時間なんてほとんどない
行政書士を目指す人のうち、初手でつまずくのがこういう方です。
けれど、ご安心ください。
行政書士試験の合格者には、あなたと同じように時間に追われながら学習した人がいます。
彼らがどのように合格にたどり着いたのか。
それは、時間の“使い方”でなく、”設計”でした。
■ 勉強時間の目安は「600〜800時間」
各資格塾が出している数値は異なりますが、一般的に合格までに必要とされる勉強時間は「600~800時間」だといわれています。
この数字を達成するには、1日2時間で10か月、平日1.5時間+週末3時間で足りますが、いずれも「継続」と「効率」が求められることに変わりありません。
■ あなた専用の“生活×学習”マトリクスをつくる
家庭や仕事を抱えている人に対し、万人向けの勉強法が通用することはまずありません。
そのため、初手で使える時間を可視化するのがオススメです。
📌 例:ある40代・子育て世代の1週間
| 曜日 | 勉強時間帯 | 学習内容の例 |
|---|---|---|
| 月~金 | 通勤時間(30分×2)/往復 | 音声学習 テキストの素読み |
| 就寝前30分 | 過去問1科目分 記述1問 | |
| 土曜日 | 午前2時間 | 演習+記述の添削と見直し |
| 日曜日 | 家族の外出中1時間 | 模試、苦手潰し |
→ このように「日々のリズム」に学習を“埋め込む”発想が必要です。
■ 最短ルートで合格するための教材選び
教材を選ぶ際、「全教科を完璧にやる」は不合格ルートまっしぐら。
行政書士試験の出題範囲が広いものの、毎年出題されている論点には偏りがあります。
| 独学派 | TAC、LEC等の市販教材×資格塾の外部模試がオススメ |
| 通信講座派 | アガルート、スタンディング等の「スマホ完結型」だと時短◎ |
| 過去問重視派 | 5年分×3周が最低ライン+記述は手書き |
時間には限りがあるため、先に範囲と教材を決め、やりこむのがオススメです。
【関連動画】【行政書士試験】使ったテキスト全部見せます|独学で合格した私の教材選びと使い方のリアル(YouTube)
■ 途中で“中だるみ”させない仕組み
- SNSで学習の進捗報告(#行政書士試験)
- 模試や講義スケジュールを他人との約束にする
- 毎週末に進捗をチェック
モチベーションが高まるのを待つのではなく、管理するつもりで継続しましょう。
■ 今週の30分が勝敗を分ける
どんなに仕事や家庭が忙しくても、1週間の学習時間がゼロだと致命的。
- 1日5分でいい
- 1日1問でいい
- 1日1行でいい
量に関わらず、学習時間ゼロの日はつくらないことです。
これこそが、家庭のある受験生の最低ラインであり、最大の戦略でもあります。
第4章|合格後の選択肢と収益化のリアル
行政書士試験に合格。スタートラインは、その先です。
開業して食えるのか
副業で使えるか
どうやって収益化すればいい?
ここでは、合格後のキャリアパスとお金の流れを、現実ベースで整理していきます。
■ 登録は“すぐにしなくてもいい”
行政書士は、合格しただけで名乗ることができません。登録する必要があります。
俗に言う開業は、この登録とほぼ同義で、登録費用(30万円前後)や、業務の準備期間が必要です。
■ 開業パターン別・収益モデル
📌 ① スタンダード型(許認可業務・書類作成)
| 顧客 | 個人事業主/中小企業 |
| 業務 | 建設業許可、契約書作成、法人設立等 |
| 年収 | 0 → 300万円 → 500万円(2~3年でこの水準も) |
📌 ② ニッチ特化型(入管・民事・ペット関連など)
| 顧客 | 特定の属性に強い |
| 業務 | VISA申請専門、死後事務委任に特化、動物関連事業等 |
| 年収 | 単価が高く、少数精鋭で60万円/月も狙える |
📌 ③ 情報発信型(SNS×行政書士)
| 顧客 | 個人/受験生/副業層 |
| 業務 | YouTube、コンサル、教材販売 |
| 年収 | 資格を信用資産として使い、情報発信との親和性が高い |
いずれも、自分の得意や過去の経験を活かして設計できる点が強みだと言えます。
■ 「いきなり独立」が怖い人へ:副業からでもOK
- 知人の会社に顧問として入る
- SNSで無料相談を始めてみる
- ブログ等で経験談を書いてみる
こうした小さな副業からの一歩でも、確実に実務につながります。
資格があることで、“話せるフィールド”が一気に広がるのです。
■ 資格を「収入」に変える3つの原則
- 市場の見極め(ニーズのある分野に軸足を)
- 人に伝える力を磨く(発信/提案/文章力)
- まず、やってみる(未経験でも始められる業務から)
完璧を目指すだけでなく、やりながら考える動作が許される業務もあります。
第5章|「動けない男」が最初にやるべき、たったひとつのこと
家庭の事情、仕事の責任、時間のなさ。誰だって言い訳したいわけではありません。
それでも、「いま動く」決断ができないこともあるでしょう。
そんなあなたに必要なのは、資格学校や教材、スケジュール帳ではなく、10分だけの自分との約束です。
■ 勉強を始めるのではなく習慣づける
多くの人は「○○から勉強を始めよう」と考えますが、いさその日が来ると何らかの“理由”が登場し、先延ばし。
もし本当に変わりたいのなら、「今日10分やる」ことです。
- 行政書士講座を扱っている資格塾等に資料請求する
- YouTubeやGoogleで「行政書士試験 解説」と検索し、結果を視聴・閲覧する
- 参考書コーナーで1冊立ち読みする(本屋さんごめんなさい!!)
最初からいきなり費用や時間をかける必要はありません。
行動に移した方から、次の一歩が踏み出せるのです。
■ 未来の自分を“具体的に”イメージする
- お子さんが寝静まった後、机に向かう背中
- 名刺の肩書きに「行政書士」が追加される日
- 家庭の外で活躍する自分の姿
あなたが資格を取るのは、”逃げ”や”見栄”ではありませんよね。
「これからの人生を、家族のせいにしないため」の選択ではないでしょうか。
■ 自分を犠牲にしてきたあなたへ
もっと早く始めておけばよかった
多くの受験生が口にする言葉です。
けれど、遅すぎるタイミングなどありません。
このブログを読んでいる“今”こそが始め時かもしれません。
■ 明日を変える、最初のアクションリスト
- ”行政書士試験”で検索してみる
- 資料請求・無料講座を申込む
- 家族に「行政書士試験を受けてみようと思う」と告げる
- スマホのカレンダーに学習開始日を登録する
上記のうち、1つでも実行するだけで景色は変わるはずです。
これは、“静かな反撃”の物語である
誰に迷惑をかけるでもなく、仕事を辞める必要もありません。
あなたの人生は確かに、動かせるのです。
行政書士という国家資格は、単なる肩書きではありません。
自分の意志で人生を選び直すための「ツール」であり、自分に嘘をつかずに生きるための「矛盾のない一手」です。
ここまで読んだあなたは、もう“何も知らない人”じゃありません。
あとは、ほんの少しの行動だけです。
次のページに、最初の一歩をまとめておきました。
さあ、静かに反撃を始めましょう。