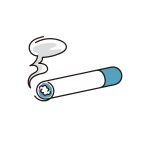当サイトの一部に広告を含みます。
Contents
関連投稿
あと3か月あるし、今から本気出せばいける(はず)
そうお考えでしたら、既にイエローゾーンです(ピッピ―!!)
行政書士試験は、11月上旬 ≒ 本番まであと90日。
けれど、残されている時間を自由に設計できる最後のチャンスは8月です。
いま、この瞬間にズレた戦略を抱えたまま進んでいる人は、確実に落ちていきます。
逆に言えば、8月の過ごし方を間違えなければ勝機はあります。
この記事では、動画では語りきれなかった「8月に伸びる人の戦い方」と「崩れる人の共通点」を、さらに掘り下げてお伝えします。
🧩第1章|8月は“仮仕上げ”!ここで止まると努力は水の泡
まだ試験まで日数あるし、様子見でいこう😊
そんなふうに足を止めると、取り返しがつかなくなります。
行政書士試験は、ただ努力すれば合格できるものではありません。
仕上げ方を知っていた者が、最後に笑う試験だと考えています。
✅8月の立ち位置を改めて整理すると
| 8月 | 時間の使い方×戦略を自由に設計できるラストチャンス |
| 9月 | 模試ラッシュ+記述の伸ばし時 |
| 10月 | 得点への最終調整 |
上表でわかるように、8月にやるべきは「やみくもに勉強を頑張る💪🔥」ではなく、仕上げに入る準備を終えることです。
🔍8月に「仮仕上げ」の状態をつくる
ここで言う“仮仕上げ”とは、以下の3点を揃えることです。
- 行政法、民法で合格ラインに届く感覚をつかむ
- 記述が白紙にならない程度に書ける
- 一般知識が足切りラインを上回る
これら全てが完璧である必要はありませんが、もう少しで届きそうな状態に近づけているかが重要です。
💬「行政法まだ苦手で…」が許されるのは、もう終わり
- 行政法の条文を読むのが辛い
- 記述問題にどう答えて良いか分からない
- 模試を受けたもののメンタル撃沈
あなたが上記のような状態なら、ラストチャンスです。
なぜなら、9月以降は「整えて伸ばす」だけにしておくのが理想だからです。
ここで整えられなければ、ズレが大きくなるばかりなのです。
📌今月中に“言語化”せよ
大切なのは、がんばっているかどうかではなく、戦略の明確化です。
- 自分に抜けている論点はどこか
- どのパターンの記述で詰まるのか
- 模試のどこでミスが多発しているか
これらのピースを言語化し、1つずつ潰していける人だけが調整フェイズに入ることができます。
📝第2章|合格者がやっていた「8月のやること5選」
8月は「とにかく頑張る」といった漠然とした努力ではなく、“成果につながる行動”だけが求められる月です。
ここでは、合格者が実際にやっていた“やるべきこと”を5つに厳選して紹介します。
① 苦手科目の「分解リスト」を作る
「行政法が苦手」レベルの抽象度では、対策すら練ることができません。
| × | 行政法がわからん🫠🫠🫠 |
| 〇 | 行政手続法の「不利益処分→理由提示義務」が弱い |
上記のように、論点・条文・出題形式まで“分解”し、明文化するのが8月最初のお仕事です。
Tips
- スプレッドシートorノートに論点別で解いた回数と正答率を記録しましょう
- 迷ったら以下からチェックしましょう
行政法:手続>不服>情報公開
民 法:意思表示>時効>相続
② 記述式は“毎日1問”を習慣化
8月時点で記述に未着手の方。不合格フラグが立っています。
記述問題は60点満点。このうち1問でも取れるかどうかで全体の結果が大きく変わります。
- 1日1問×30日=最低30パターンは練習できる
- 最初は30字程度でOK(とりあえず手を動かす)
- 書く前5秒で「誰が、何を、どうした」の構造をイメージする
Tips
- 使う教材は1冊に絞り、回転数を上げる
- 模範解答の言い換えパターンをストックすることで得点しやすくなる
③ 模試は“得点”ではなく“設計図”にする
模試の偏差値に一喜一憂してませんか?
合格者は、模試を「戦略立て直しツール」として活用しています。
- 正答した問題でも根拠が曖昧 → 即復習
- 誤答問題の共通点 → 分野別にマーク
- 自信がある問題を外した → 思考ミスの分析
Tips
- 模試復習ノートを作り、繰り返し見返す
(1回目→当日または翌日/2回目→1週間後/3回目→模試直前)
④ 過去問を“テーマ別演習”に切り替え
これまで年別に区切って答練していた受験生さん。
8月以降は、年別でなく論点別に過去問を解きましょう。
| 憲法 | 人権保障 (頻出) | 幸福追求権(13条):自己情報コントロール権、プライバシー権など 表現の自由(21条):検閲・事前抑制・名誉毀損との関係など 学問の自由、職業選択の自由、信教の自由(特に政教分離原則) 法の下の平等(14条):合理的区別 vs 差別(立法目的の正当性判断) |
| 統治機構 (近年増加傾向) | 国会の地位と立法手続き(41条~) 内閣の権限(行政行為との関連) 裁判所の独立と違憲審査(憲法81条) 地方自治(94条):条例制定権、機関委任事務の廃止後の整理など | |
| 民法 | 総則 | 意思表示の瑕疵(錯誤・詐欺・強迫) 制限行為能力(未成年者・成年被後見人など) |
| 物権 | 所有権と占有権の違い 抵当権の効力範囲(賃借権と対抗関係) 共有物の利用と管理(民法264条) | |
| 債権 (再頻出) | 債務不履行(履行遅滞・不能・不完全履行) 損害賠償と信頼利益 vs 履行利益 不法行為と過失相殺、共同不法行為 連帯債務と保証債務(根保証含む) 売買契約と解除・危険負担(改正後対応) | |
| 親族・相続 | 法定相続分と代襲相続 遺留分侵害額請求(旧:減殺請求) 協議分割・遺産分割の手続き | |
| 行政法 | 行政行為 (最重要) | 行政行為の定義・分類(法律行為的・事実行為的 etc.) 取消しうる行政行為 vs 無効な行政行為 行政行為の効力(公定力、不可争力、拘束力、形成力 etc.) 取消しの可否と瑕疵の治癒・遡及効 撤回・職権取消し・失効 |
| 行政手続法 | 処分手続(聴聞/弁明/理由提示) 命令等制定手続(パブリックコメントなど) 申請に対する審査基準・標準処理期間 行政指導(強制性の有無、文書交付義務など) | |
| 行政不服審査法 | 不服申立ての種類(審査請求、異議申立て、再審査請求) 原処分主義/上級庁主義 不服申立て期間・手続の流れ 裁決の効果・拘束力 執行停止・審理員制度(旧:行政審判官) | |
| 国家賠償法 | 国家賠償法1条:公権力行使による違法行為(公務員の過失等) 国家賠償法2条:公物の設置・管理瑕疵 1条の「公務員」「職務行為」「違法性」「損害」との関係性 代位弁償と求償権 | |
| 損失補償 | 憲法29条3項との関係 土地収用法における補償原則(正当補償) 違法ではないが財産権を制約する公権力行為 全損 vs 一部損・制限(事業損失補償との違い) | |
| 行政強制・行政罰 | 行政上の強制手段 即時強制・行政代執行・直接強制・執行罰の区別 手続・要件・例(ゴミ処理、建物除却等) 行政刑罰・行政上の制裁(過料との違い) | |
| 行政立法 | 命令の種類(委任命令・執行命令) 通達・告示との違い 委任の限界(白紙委任の禁止など) | |
| 行政契約 (近年注目) | 私法上の契約と行政契約の違い 指定管理者制度、PFI、請負契約との関係 | |
| 行政指導 (繰り返し) | 行政指導と処分の違い 行政手続法上の規定(文書提示義務・相手の自由意思など) 義務付け・不利益取り扱いの禁止 | |
| 商法/会社法 | 商行為 | 商人の定義、商業登記と営業的活動 代理商・問屋・運送取引などの典型商行為 |
| 株式・機関 | 株主総会の種類(通常/臨時)と議決要件 取締役会・代表取締役の権限と責任 役員の競業避止義務・忠実義務・善管注意義務 株式の譲渡制限、自己株式の取得 設立手続、募集株式発行、定款変更 |
複数年度をまたぎ、同じテーマを並列で解くことにより、出題傾向や重要論点が見えるようになります。
Tips
- パターン認識できるよう比較読みを実行
- 使い込んだ過去問をテーマ別に再構成し演習用にするだけ
⑤ 一般知識は“足切り対策”から“得点源”へ
一般知識について、漠然と「足切りラインさえ超えればいいんでしょ?」とお考えのあなた。危険です。
- 文章理解対策として1日1問解いてみる(※反射読みの訓練)
- 時事は新聞より直近の白書まとめで重点補強
- IT・個人情報保護関連は過去問+頻出キーワードの理解重視
Tips
- 文章理解は解法パターンを掴めると伸びやすい
- 時事は予想問題に手をつけておくことで9~10月の安心感が違う
「全部は無理かも」と感じるのもわかりますが、だからこそ、8月にやるべきではないでしょうか。
中途半端に過ごす8月は、9月を“敗戦処理”に変えてしまうリスクがあります。
💣第3章|8月に“崩れる人”の4つの共通点
8月は、「爆伸びする人」と「無音で壊れる人」とが明確に分かれる月でもあります。
皮肉なことに、崩れていく人の多くは自覚がありません。
どなたも「がんばっているのに、うまくいかない」…そんな苦しさを抱えながら受験を終えます。
この章では、8月に崩れやすい人の行動パターンを4つ、言語化してお伝えします。
あなたに当てはまるものがあれば、今すぐに立て直しましょう。
① 作業量で安心する「勘違い努力型」
- 今日は10時間机に向かった
- テキスト3周目突入した
だから、何?時間をかけた、周回こなすだけでは意味がありません。
実行前と比較し、解けるようになっていますか?
- 解けない問題をスルーしている
- 間違えた理由を分析せず、次の問題へ
- 覚えたつもりになり、再現性無視
これらに覚えがある方、いくら努力したところで記憶に定着しないどころか、得点にも繋がりません。
対策
これらへの対策として、1日の終わりに「今日できるようになったこと」を書き出す習慣をつけましょう。
② 模試の点数でメンタル崩壊
- 偏差値50以下…もう無理…
- 合格者とは頭の作りが違う
このような心境に陥っていませんか?不合格者あるあるです。
模試は“本番の予測”ではありません。
模試を受けるまでに行ってきた学習のズレを測定するためのツールです。
対策
- 点数ではなくミスの傾向、正答要因を振り返る
- 点数が悪いときこそ改善の好機
③ 生活リズムが壊れたまま
- 就寝時間は深夜2時/起床時間は昼
- 食事はコンビニ弁当
- 集中時間は夜のみ
- 日中はスマホやタブレットが手放せない
このような状態では、本番において、本来のパフォーマンスを発揮することができません。
行政書士試験は13時開始です。
これに合わせて脳をピークにもっていける身体がなければ、得点は厳しいです。
対策
- 朝は遅くとも7時に起床し、午前中に主要科目
- 眠ければ昼に仮眠を
- 夜は記述、復習が◎
- 朝型生活に変えると記憶力+集中力が上がりやすい
④ SNSで他人と比較して病む
- もう過去問終わってんの?無理ぃ…
- エッッ…!?!?そんなにやってんの?
こんな風に、どこかの他人と自分を比較しているあなた。
時間とメンタルの無駄遣いです。辞めましょ。
あなたが比較すべき対象は、「昨日のあなた」だけです。
昨日より今日、1mmでも前進しているか?を意識しましょう。
対策
- SNSの閲覧・投稿は夜だけに制限(できれば時間を決めて)
- 他人の勉強報告を見る暇があるなら五肢択一を1問でも解きましょう
- 自分自身の勉強報告をするなら、あくまで自己記録として行うこと
8月に崩れる人の多くは、勉強量が不足しているからではありません。
戦略と防御方法をご存じなかったからです。
大丈夫。ここから90日間でまだ立て直せるはずです。
🌅第4章|“生活”を秋仕様にアップデート
「やる気が出ない」
「集中力が続かない」
それは本当に、あなたの意志の問題ですか?
行政書士試験は、ただの知識勝負じゃありません。
本番の3時間で、知識を引き出せる身体と脳を作れるかどうか。この土台が整っていなければ、どれだけ勉強しても“点数”には繋がらないのです。
① 朝型生活に完全シフトせよ
行政書士試験本番は、午後1時開始です。
つまり、朝起きてから3〜4時間後に脳のピークを合わせる必要があるのです。そのため、
- 昼に起床し、深夜に勉強
- 夜でなければ集中できないと思い込んでいる
- 朝は頭がはたらかず、何も手に着かない
このような状況だと、本番の3時間が地獄と化します。
おすすめのルーティン例(合格者実例)
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 7:00 | 起床 軽い運動(散歩やストレッチ等) |
| 8:00 | 行政法+民法等の主要科目演習 |
| 12:00 | 昼食 必要なら仮眠(15~20分) |
| 14:00 | 記述、一般知識等の応用演習 |
| 17:00 | 当日の復習+暗記 軽めの読書も◎ |
| 22:00 | 入浴+リラックスタイム 就寝準備 |
| 23:00 | 就寝 |
② 脳のための「食事×睡眠」設計
脳は“栄養と回復”で動いています。
ですので、食事内容と睡眠時間次第で、記憶の定着率と集中力が劇的に変わることがあります
📌食事のポイント
| 朝 | たんぱく質(卵/納豆/ヨーグルト) 炭水化物(ご飯/パン) | 脳を起こす |
| 昼 | 糖質(うどん/そば) 軽めのたんぱく質(鶏胸肉等) | 眠気防止 |
| 夜 | 脂質少なめを意識 | 就寝3時間前には済ませる |
📌睡眠のポイント
- 就寝時間は毎日固定(理想は23時台)
- 入浴とブルーライトカットで入眠儀式をつくる
- 夜更かしは禁物
※睡眠不足は記憶力を30%落とすといわれています
③ スマホは“物理的に隔離”せよ
試験勉強の大敵。それは、やる気ではなくスマホです。
- 集中していたところ、LINE通知により途切れる
- SNSを「ちょっと見」しただけのつもりが30分
- 勉強アプリを開いたのに、YouTubeを見ていた
このような動作に1回30分が奪われ、1日に3回発動している場合、それだけで90分のロスです。
対策例(合格者が実践)
- 勉強中はスマホを別室にて管理する
- 通知はすべてオフorおやすみモードに
- タイマー勉強法(25分集中×5分休憩)を導入し、時間内のスマホ断ち
- SNSチェックは「夜30分」に制限
集中できないのは、単に、生活が“合格仕様”になっていないだけかもしれません。
勉強法を見直す前に、まず“自分の土台”を整えてみませんか。
🎯第5章|点数を変えたければ、「記述」と「模試」を制すべし
行政書士試験において、合格点に“届く人”と“届かない人”の最大の差は何でしょうか。
答えは、お察しの通り「記述問題」と「模試の扱い方」です。
テキストを何周しても、過去問を何年分解いても、この2つを“本番仕様”に仕上げられなければ、点は伸びません。
✏️記述は「構造」と「言い換え力」で勝負が決まる
- 模範解答の言い回しが真似できない
- 説明したいけど30字以上書けないor字数オーバーになる
- 時間をかけても言葉が出てこない
これらの症状は、記述に必要な“構造力”と“表現変換”を身につけていないことが原因です。
📌記述を伸ばす3ステップ
| 1 | 構造を読む訓練 | だれが/何を/どうしたの型で整理する |
| 2 | 言い換えの練習 | 模範解答を自分の言葉で言い換える練習する |
| 3 | 採点者目線で練習 | 減点されにくい表現を意識して添削する |
👉 実際の添削例や記述テンプレは、事務所ブログ内の別記事で紹介予定です。
📎 → 記述式の型トレーニングはこちら(※近日公開予定)
🧠模試は「点数」じゃない、「戦略」を読み解く道具
「偏差値が低くてやる気なくした」
「記述がボロボロで落ち込んだ」
模試を受験後、このように感じてらっしゃるようでしたら、模試の本質を見誤っているかもしれません。
模試とは本来、自分の勉強法の何がズレているかを可視化する診断ツールです。
📌模試活用のプロセス
| 1 | 間違いを分解 | 知識不足/思考ミス/問題文の読み誤り等 |
| 2 | 得点できた問題を検証 | なぜ解けたか/根拠は明確だったか |
| 3 | 9月の強化目標に変換 | ○○分野を強化する等、計画に繋げる |
本記事でお伝えしきれないノウハウについて
本記事でお伝えしきれないノウハウについて、以下にまとめています。
note記事|私自身が添削した記述の“型”と改善プロセスを公開
- 書けない×出てこない人がどうやって書けるようになったか
- 30字→40字/50字→40字と調整する方法
- 減点されづらい言い換えフレーズ
記述と模試。これらを武器にできた人だけが、最後の1か月で合格ラインに飛び込めるのではないでしょうか。
🔚おわりに|変わるかどうかは、「この8月」の過ごし方で決まる
あと3か月…まだ3か月だとお考えですか?それとも、3か月しかないと思われますか?
この問いに「焦り」を感じたのなら、まだ間に合います。
しかし、何もしないまま迷っていると脱落してしまいます。
YouTubeメンバーシップでは、「合格を目指す仲間」として並走してくれる人を募集中です。
当チャンネルメンバーシップは、もともと愛鳥・善の治療費をまかなうために始めたのですが、今は、榊原自身が「愛玩動物看護師学科」に進学するための学費を目標に、活動を続けています。
「変わりたい」
「やり直したい」
「人生を取り戻したい」そんなあなたと、同じ方向を向いて走れたら嬉しいです。
メンバーになることで、直接応援することができます。
特典はありません。でも、意味はあります。
👉https://www.youtube.com/channel/UCRex_B9uPGOMsofqrxh7ScQ/join
試験本番まで、あと90日。
やる気が出るのを待つよりも、“迷わない仕組み”を持てた人が勝つのです。
明日の自分を変えたいなら、今日、動いてください。
関連投稿