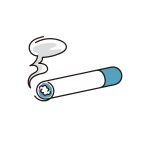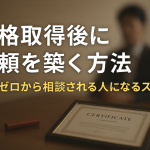当サイトの一部に広告を含みます。
身寄りがいない、あるいは頼れる人がいない。
それだけで、施設への入居を断られるケースが今でも珍しくありません。
しかし実際には、保証人がいなくても入居を認めてもらえる仕組みやルートがきちんと存在します。
この記事では、
- 保証人のいない人が福祉施設に入る方法
- その際に気をつけたい手続とトラブル回避のポイント
について、制度と現場の両面からわかりやすく解説します。
孤立を責める、あるいは、卑下するのではなく、現実的な選択肢を知ること。
それが、老後と生活を守る第一歩となります。
Contents
関連投稿
身元引受人の存在
老人ホームや介護施設等の福祉施設に入居する際、保証人や身元引受人を求められるのが一般的です。
福祉施設は、基本的に利用契約を本人と結びます。
けれど、入居者が高齢で判断力や体力が落ちている場合、
- 支払いの遅延、滞納
- 医療機関への緊急搬送や死亡時の対応
- 退去時の原状回復や荷物の整理
といった場面において、誰が責任を取るのかが曖昧となります。
そのため、施設側は「もしものときに連絡がつく人」や「代わりに手続をしてくれる人」を契約条件として求めるのです。
保証人と身元引受人
保証人と身元引受人の違いは、以下の通りです。
| 役割 | 主な内容 | 法的性質 |
|---|---|---|
| 保証人 | 入居費・利用料等の金銭債務を保証。 未払時には支払い義務を負う。 | 法的義務有り (民法上の保証契約) |
| 身元引受人 | 緊急時の連絡・退去時の立会い・遺品整理等、生活や身上面の支援。 | 法的拘束力は弱く、慣習的・道義的な役割が中心 |
つまり、保証人はお金の責任、身元引受人は生活面のサポートと連絡窓口であり、両者とも施設と本人の間をつなぐクッションのような存在だといえます。
とはいえ、施設により定義が異なるケースがありますので、事前に確認しましょう。
保証人・身元引受人の要件
保証人・身元引受人に求められる要件は、法律で明確に決まっているわけではなく、各施設が契約上の条件として定めています。
場合によっては、収入を問われることもありますが、配偶者、子等の親族から選ばれるのが一般的です。
以下に、よくある基準を挙げますので参考にしてください。
保証人の要件
保証人の目的は、入居費・利用料の未払等の金銭的に備えることです。
主な要件として、
- 支払い能力があること
- 成年で、判断能力があること
- 本人と連絡がとれる関係性であること
- 場合によっては、親族であること
身元引受人の要件
身元引受人の目的は、緊急時や死亡時等、生活・身上面での対応を引き受けることです。
主な要件は、
- 本人の状況を把握し、連絡・対応ができること
- 継続的な関係性があること
- 法的義務ではなく、道義的・社会的責任を負える人
- 施設との連絡に支障がないこと
保証人・身元引受人がいない場合
保証人も身元引受人も立てられない場合でも、すぐに入居できないと諦める必要はありません。
近年では、身寄りのいない高齢者が増えている現実に合わせ、いくつかの公的・民間の受け皿が整ってきています。
主な対処法は、以下の通りです。
- 成年後見制度を利用する
- 身元保証支援法人(NPO・社会福祉法人等)を利用する
- 行政の地域包括支援センター・福祉科に相談する
- 信託や預託金制度を利用する
成年後見制度を利用する
判断能力が低下している場合、家庭裁判所に成年後見人の選任を申立て、その人が契約や支払いの代行を行うことが可能です。
施設により、後見人がいると保証人不要となるケースもあります。
身元保証支援法人を利用する
家族に代わり「身元保証」「入退院時対応」「葬送支援」等を請け負う団体があります。
契約内容や料金は各法人で異なりますが、全国的に整備が進んでいます。
行政書士が契約に立会い、信託設定等を支援するケースも。
行政の地域包括支援センター・福祉科に相談する
自治体により、保証人のいない高齢者の入居支援や生活支援体制整備事業を実施しています。
福祉施設やケアマネジャー経由で、適切な支援団体を紹介してもらえることもあります。
信託や預託金制度を利用する
あらかじめ一定額を預け、そこから入居費や葬儀費を支払う仕組みをとる施設もあります。
保証人の代わりに、金銭面の安心を確保する方法だといえます。
身元保証サービスを利用する際の注意点
身元保証サービスを選ぶ際、次の点に注意しましょう。
- 保証人代行と称し、高額な費用を取る悪徳業者も存在します。
→ 必ず行政・専門職・公的団体を経由して確認しましょう。 - 施設により「保証人不要」でも、緊急連絡先の記載を求められるケースがあります。※
- 後見制度を使う場合、後見人の権限の範囲を事前に確認しましょう。
※「保証人不要」とあっても、誰かが最期まで連絡を受け取れる体制は求められるケースがあります。
この場合、以下の対処法が考えられます。
成年後見人がいる場合
後見人を緊急連絡先として記載することができます。
施設により、保証人の代替として扱ってくれます。
身元保証支援法人を利用している場合
契約内容に「緊急時の連絡対応」まで含まれている場合、その法人を記載することができます。
ほとんどの場合、入院・死亡時の対応までセットになっていますが、契約前に必ず確認しましょう。
どうしても該当者がいない場合
地域包括支援センターやケアマネジャーに相談し、行政が連携してくれる体制の有無を探しましょう。
自治体により、社会福祉協議会や民生委員が「連絡窓口」として関与することもあります。
つまり、保証人はお金の責任 / 緊急連絡先は命と生活の連絡窓口と性質が異なるため、保証人不在でも後者だけ埋められるよう整えておけば入居は可能です。
保証人がいない場合の福祉施設入居方法まとめ
当ページでは、保証人(身元引受人)がいない場合の福祉施設入居方法を解説しました。