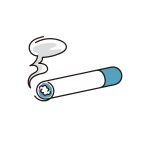当サイトの一部に広告を含みます。
たばこを販売するには、「たばこ小売販売業許可」を取得する必要があります。
しかし、申請の流れや要件を調べようとすると、財務省やJT(日本たばこ産業)の資料が難解で、結局何をすればよいのかわからない──。
そんな声を多くいただきます。
本記事では、一般小売販売業許可の要件・申請手続・注意点について、実際の相談や申請経験に基づき、わかりやすく解説します。
特に、「個人でも申請できるの?」「物件を借りたあとで申請できないことがあるって本当?」といった、実務でつまずきやすいポイントを中心に取り上げます。
この記事を読み終えるころには、以下が明確になります。
- 自分は申請できるか
- 申請までに準備すべきもの
- 専門家に頼るべきタイミング
Contents
関連投稿
第1章 たばこ小売販売業許可とは
たばこ小売販売業とは、たばこを営業目的で消費者に販売するために必要な許可を指します。
許可権者は財務大臣ですが、実務上は営業所所在地を管轄する日本たばこ産業株式会社(JT)が申請の窓口を担当しています。
※なお、たばこ小売販売業許可の権限自体は財務大臣にありますが、実際の申請受付・現地調査などの実務は、国から委託を受けた日本たばこ産業株式会社(JT)が行っています。そのため、手続き上はJT支社への申請となります。
この許可には「一般小売販売業」と「特定小売販売業」の2種類があります。
両者の差は、販売場所の性質(開放的か、滞留性が高いか)です。
| 区分 | 販売場所・特徴 | 代表的な例 |
|---|---|---|
| 一般小売販売業 | 通常の店舗など、一般消費者が自由に出入りできる場所 | コンビニ・商店など |
| 特定小売販売業 | 人が長時間滞在する施設や閉鎖的な空間での販売 | 飲食店・旅館・劇場・大規模店舗(売り場面積400㎡以上)など |
つまり、喫茶店や旅館のようにお客さんが長く滞在する場所で販売するには「特定小売販売業」、それ以外の一般的な店舗で販売する場合は「一般小売販売業」に分類されます。
行政書士の視点から
現場では「どちらで申請すべきか」迷われるケースが多くあります。
特に、施設の性質が“半開放的”な場合(フードコートやイベントスペースなど)ですと、どちらの区分にも該当する可能性がありますので、早い段階でJTに販売形態を確認することが重要です。
誤った区分で申請しますと、許可の取り直しやタイムロスにつながりますので要注意です。
第2章 申請前に確認しておきたい5つのポイント
たばこ小売販売業の許可申請は、申請書を提出すれば終わりというものではありません。
実際の審査では、申請者本人の適格性や営業場所の環境、販売見込みなど、複数の条件を確認されます。
申請準備に入る前に、次の5点を押さえておきましょう。
① 申請者の要件
申請者が一定の欠格事由に該当する場合、許可を受けることはできません。
代表的なものは以下のとおりです。
- たばこ事業法に基づく罰金刑以上の刑を受け、執行から2年を経過していない
- 申請前2年以内に、たばこ販売業の許可を取り消された
- 破産手続開始決定を受け、復権を得ていない
法人の場合は代表者も審査対象になります。
また、未成年者が申請する場合は、その法定代理人の適格性も確認されます。
行政書士のワンポイント
過去に他業種で行政処分を受けた場合でも、たばこ事業法上の欠格に該当しないケースがあります。
不安なときは、事前にJTに照会をかけておくとスムーズです。
② 営業場所の条件
たばこの購入に著しく不便と認められる場所(たとえば袋小路の奥など)は、許可が下りません。
また、営業所の所在地区分により他の販売店との距離基準が設けられています。
この距離基準は「市」「町村」「指定都市」などによって異なり、同じ市内でも繁華街・住宅街で扱いが違うこともあります。
目安としては、都市部で50~100m、郊外で150~200mです。
ただし、交通施設や団地内などには特例が適用される場合があります。
③ 自動販売機を設置する場合のルール
自動販売機での販売を予定している場合は、成人識別機能(taspo対応)が必須です。
| 一般小売販売業の場合 | 店舗に併設する形で、従業員が利用者を直接確認できる位置に設置すること |
| 特定小売販売業の場合 | 管理責任者または従業員が、機械と利用者を容易に視認できる位置に設置すること |
たばこの自販機は、設置場所の管理環境が不十分な場合、設置そのものが認められないことがあります。
④ 取扱予定高(販売見込み数量)
営業予定場所での取扱数量(販売見込み)が、月4万本未満だと許可が受けられません。
ここでの試算方法は、次のとおりです。
| 一般小売販売業 | 供給見込区域内の世帯数 × 世帯あたり平均購入本数(400本) |
| 特定小売販売業 | 施設の平均利用者数 × 業態別平均購入本数(3.5~6.5本) |
現場での注意点
近隣に大型店や観光施設がありますと、販売見込みが実際より低く算出されることがあります。
JTの現地調査により「低調地域」と判断されると、不許可になるケースも。
⑤ 営業所の使用権限と法人の目的
物件の賃貸借契約書または所有権の証明書類が必要です。
申請後1か月以内に開業見込みが立たない場合、許可を受けられません。
法人の場合、定款または寄附行為に「たばこの販売」を目的として含める必要があります。
もし目的に記載がない場合には、定款変更後に申請を行いましょう。
ここまでが「許可を取るための前提条件」です。
次の章では、実際にどのような流れで申請が進むのか、スケジュール感を含めて説明します。
第3章 たばこ販売許可の申請から取得までの流れ
たばこ小売販売業の許可申請は、書類をそろえるだけで終わりではありません。
現地調査や修正を経て、正式に許可が下りるまでには1か月~2か月程度を見ておく必要があります。
ここでは、申請から取得までの全体像を時系列で整理します。
① 申請書類の準備
まずは、JTの公式サイトまたは支社窓口で申請書(Word形式)を入手します。
添付すべき主な書類は次のとおりです。
- 誓約書
- 住民票または登記事項証明書(法人の場合)
- 破産者・成年被後見人に該当しない証明書
- 予定営業所の図面
- 所有者の同意書または賃貸借契約書
- 二十歳未満喫煙防止の誓約書(自販機設置時)
行政書士の現場感
書類自体はそれほど多くありませんが、図面の作り方と距離測定の根拠で手戻りが起きやすいです。
図面は、建物平面図に出入口・自販機の位置を正確に記載しましょう。
② JTへの申請・受付
提出先は、営業所所在地を管轄する日本たばこ産業株式会社(JT)支社です。
郵送でも受け付けていますが、窓口での相談・確認を挟んで提出した方がスムーズです。
JTでの受付後、担当者による書類審査と現地調査が行われます。
③ 現地調査
JTの担当者が、以下の内容を中心に確認します。
- 営業所の位置(交通の利便性や周辺環境)
- 他の店舗との距離
- 施設内の喫煙設備・自販機の設置場所
- 表記・案内表示の状況
この段階で、環境区分(市街地/農地/観光地など)や距離要件の最終判定が行われます。
誤差があると補正を求められ、再調査になる場合もあります。
物件を契約する前に、JTの担当支社へ「販売予定地の距離基準」を相談しておくと、契約後に不許可になるリスクを減らせます。
④ 納付書の受領と登録免許税の納付
審査で問題がなければ、JTから「納付書」と「登録免許税領収書提出書」が届きます。
金融機関で登録免許税15,000円を納付し、領収書を貼付してJTに提出します。
⑤ 許可証の交付・営業開始
JTから正式な「たばこ小売販売業許可証」が交付されます。
許可証が届いた日から販売が可能になります。
注意点
許可を受けてから1か月以内に営業を開始しない場合、許可が取り消されることがあります。
開業準備を同時進行で進めておきましょう。
第4章 許可が取れない・取り消される主なケース
せっかく申請しても、要件を満たさなければ許可は下りません。
また、取得後でも一定の行為に該当すると、営業停止や許可取消しの処分を受けることがあります。
ここでは、現場でよく見られる不許可・取消しの原因を整理します。
① 不許可になりやすいケース
距離要件を満たさない場所で申請した場合
→ 団地や駅構内など、特例が適用されると思い込んで申請すると不許可になることがあります。
取扱予定本数が月4万本未満と判断された場合
→ 試算が甘いと「需要不足」とみなされます。
物件の使用権限が曖昧な場合
→ 賃貸契約の名義が異なる、転貸扱いなど。
定款に「たばこの販売」が含まれていない法人
→ 目的外事業として却下。
現場で多い不許可理由は、「距離」「予定本数」「定款目的」の3つです。
特に店舗の賃貸契約を先に進めてから申請するケースは、取り返しがつかなくなることもあります。
② 許可後に取消し・停止になるケース
たばこ事業法第23条では、以下のような行為を行うと営業停止または許可取消しの対象になります。
- 許可条件に違反したとき
- たばこを定価外で販売したとき
- 注意表示(健康警告)を消去・変更して販売したとき
- 無許可で営業所を移転または出張販売したとき
- 正当な理由なく1か月以上営業を休止したとき
- 不正な手段で許可を取得したとき
- 20歳未満の者にたばこを販売したとき
とくに「20歳未満への販売」は最も重い処分の対象になります。
一度処分を受けると、2年間は再申請できないため、従業員教育を徹底しましょう。
③ 行政書士の視点:取り消しを防ぐコツ
たばこ販売の許可は、一度取れば終わりではありません。
現場では次の3点を守るだけでも、トラブルを大幅に減らせます。
- 自販機の定期点検を怠らない(成人識別装置の作動確認)
- 売場変更・改装時は必ずJTに相談する
- 休業予定が1か月を超える場合は、事前に届出する
これらの報告や相談を怠ると、「報告義務違反」として形式的に処分されることがあります。
第5章 実務の現場で見た落とし穴3選
ここからは、実際の申請や相談で多いトラブルを紹介します。
どれも書類上は問題なさそうに見えて、あとから修正に追われるケースです。
落とし穴① 物件を借りてから「距離要件」で不許可になる
店舗の契約を先に進め、あとから申請した結果「近すぎて不許可」──よくある流れです。
JTは現地調査で既存店との直線距離を測るため、地図上で見たよりも距離が短く判定されることがあります。
対策
物件候補が決まったら、契約前にJTへ「距離確認」を依頼すること。
無料で確認してもらえます。
落とし穴② 定款や契約書の記載漏れ
法人が申請する際、「たばこの販売」が定款の事業目的に含まれていないと、申請を受け付けてもらえません。
また、店舗を賃借する場合は、賃貸借契約書の使用目的欄にも「たばこの販売」が含まれている必要があります。
対策
定款の目的を事前に確認し、必要なら登記変更を先に行うこと。
契約書も、貸主の同意をもらって文言を追記しておくと安全です。
落とし穴③ 自動販売機の設置位置が“視認不可”
店内から自販機や購入者が直接見えない位置にあると、「成人識別管理が不十分」とされることがあります。
特に飲食店や宿泊施設のように構造が複雑な場合は注意が必要です。
対策
申請時に提出する図面へ、自販機の位置と視認範囲を明示する。
実際の店内写真を添付すると確認が早くなります。
行政書士からの一言
たばこ販売の許可は、数字より「現場の見え方」が重視されます。
距離や数量を満たしていても、現地の環境次第で判断が変わることがあるのです。
図面・契約・動線、この3つを揃えると、審査は一気に通りやすくなります。
第6章 ここまで読んで「自分でできるか不安」な人へ
ここまでの内容を読んで、
「書類は揃えられそうだけど、JTとのやり取りが心配」
「物件選びや距離の確認を一人でやるのは不安」
そんな方も多いと思います。
たばこ小売販売業許可の申請は、形式はシンプルでも実務は意外と複雑です。
JTは個別の事情にも柔軟に対応しますが、そのぶん現場判断の余地が広く、「書類上OKでも、現地でNG」となることも珍しくありません。
行政書士に依頼するメリット
- 物件の距離確認・環境区分の事前照会がスムーズ
- 書類作成からJTへの補正対応まで一括サポート
- 不許可リスクを事前にチェックできる
とくに、テナント契約や改装を伴う場合は、申請前の相談がいちばんコスパの良いリスク対策になります。
「書類の作り方だけ知りたい」という方向けに、許可申請のチェックリストと記載例をnoteで公開しています。申請の流れを理解したうえで、自分で進めたい方におすすめです。
関連リンク
まとめ
たばこ販売許可のポイントは、制度よりも「現場の見え方」です。
距離・数量・構造の3点を押さえ、申請前に一度JTへ相談しておけば、後からのトラブルはほとんど防げます。
制度を正しく理解して準備を整えれば、個人でも十分に取得可能な許可です。