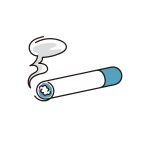当サイトの一部に広告を含みます。
最近、カラーコンタクトレンズ(以下「カラコン」)の取り扱いについて相談を受ける機会が増えています。
特に、美容サロンや雑貨店などで
「おしゃれ用のカラコンを販売したい」
「ネットショップで扱ってもいいのか」
といった声が目立ちます。
一見するとカラコンは化粧品やアクセサリーのように思えますが、法律上は「高度管理医療機器」に分類される医療機器です。
そのため、販売には所定の許可と管理体制が求められます。
ところが、実際に申請を進めようとすると、保健所や厚生労働省の資料は専門用語が多く、どの手続きが自分に必要なのかが分かりづらいのが現状です。
本記事では、そうした疑問にお答えする形で、カラコンを販売するために必要な許可の概要、申請の流れ、そして注意すべきポイントを、実際の相談事例を交えながら、できる限りわかりやすく解説します。
Contents
関連投稿
第1章 カラコンが医療機器とされる理由
カラコンは、視力補正を目的としない「おしゃれ用」であっても、医薬品医療機器法上は「高度管理医療機器」に分類されています。
これは、レンズが直接角膜に触れる構造であり、誤った使用や衛生管理の不備によって、角膜炎や視力障害などの健康被害を引き起こすおそれがあるためです。
実際、法改正前には、雑貨店などで無許可販売されたカラコンによるトラブルが多発していました。
使用者が洗浄液を使わずに繰り返し装着したり、度なしレンズをファッション感覚で共有したりすることで、感染症を発症するケースが報告されています。
こうした背景から、2009年の法改正以降は、医師の処方や販売業者の管理体制を明確に義務付ける仕組みが整えられました。
つまり、カラコンは「おしゃれの延長」ではなく、正しい管理のもとで販売・使用されるべき医療機器という位置づけです。
販売者は、商品の見た目や流行性よりも、安全性と法令遵守を優先する姿勢が求められます。
【関連リンク】
第2章 必要な許可とその範囲
カラコンを販売する場合には、「高度管理医療機器等販売業許可」が必要です。
この許可は、医療機器のうち特にリスクが高いとされる製品(コンタクトレンズなど)を販売・貸与する際に義務付けられるもので、都道府県知事の許可を受けて初めて事業を行うことができます。
販売業許可にはいくつかの区分がありますが、カラコンの場合は「高度管理医療機器等販売業」に該当します。
許可を取得すれば、実店舗での販売はもちろん、オンラインショップなどを通じた通信販売も可能になります。
ただし、どちらの場合も、営業所として登録された拠点において管理体制が整っていることが前提です。
また、混同されやすいのが「届出」と「許可」の違いです。
一般医療機器や管理医療機器(血圧計や補聴器など)を扱う場合は「届出」で足りますが、高度管理医療機器に該当するカラコンを扱う場合は、必ず許可が必要になります。
この点を誤解して「雑貨扱いで販売していた」と後から指摘を受けるケースも少なくありません。
販売者は、「どのクラスの医療機器を取り扱うのか」によって必要な手続きが異なることを正確に理解しなければなりません。
保健所への相談の際にも、扱う商品の分類を明確に伝えることで、不要な手戻りを防ぐことができます。
参考:医療機器の分類表
| 分類 | 例 | 必要な許可 |
|---|---|---|
| クラスⅠ (一般医療機器) | メス、ピンセット等 | 第三種医療機器製造販売業許可 |
| クラスⅡ (管理医療機器) | 血圧計、補聴器等 | 第二種医療機器製造販売業許可 |
| クラスⅢ (高度管理医療機器) | コンタクトレンズ等 | 高度管理医療機器等製造販売業許可 |
| クラスⅣ (高度管理医療機器) | ペースメーカー等 | 第一種医療機器製造販売業許可 |
第3章 営業所・管理者の要件
高度管理医療機器等販売業許可を取得するには、営業所の構造設備と管理体制の両方が基準を満たしていなければなりません。
どちらか一方でも不足があると、保健所の実地調査で差し戻しになることがあります。
1.営業所の構造設備基準
営業所は、以下の要件を満たす必要があります。
- 採光・照明・換気が適切で清潔であること
- 居住スペースや不潔な場所と明確に分離されていること
- 安全かつ衛生的に商品を保管できる設備があること
営業所は、清潔かつ衛生的であることが求められます。
採光・照明・換気の状態が良好であること、居住スペースや不衛生な場所と区分されていること、安全に商品を保管できる設備があることが基本条件です。
よく「自宅の一室を営業所にできるのでは?」と質問を受けます。
結論から言えば、構造上、生活空間と販売スペースを明確に分けられるなら可能ですが、保健所によって判断が異なるため、事前相談を行うことが確実です。
また、商品を倉庫で保管し、実際の販売をネット上で行う場合でも、その倉庫を営業所として登録する必要があります。
2.営業管理者の設置
営業所ごとに「高度管理医療機器等営業管理者」を1名以上配置しなければなりません。
この管理者は、販売に関する法令遵守や衛生管理を統括する立場であり、形式的な名義貸しは認められません。
営業管理者として認められるのは、次のいずれかに該当する人です。
- 医療機器の販売・貸与業務に3年以上従事した後、指定の基礎講習を修了した者
- 医師、歯科医師、薬剤師などの資格保持者
- 医療機器の製造・修理・販売等に関する実務経験や講習終了者
講習は各地域の指定機関で実施されており、受講料は概ね1万〜2万円前後です。
日数は1〜2日程度が一般的で、修了証が発行されます。この修了証がなければ、申請時に管理者として認められません。
【講習機関一覧】
第4章 申請手続きの流れと注意点
高度管理医療機器等販売業許可の申請は、原則として営業所所在地を管轄する保健所に対して行います。
手続きの流れを理解しておくと、準備の抜け漏れを防げます。
- 保健所への事前相談
- 定款変更や診療所変更手続等(必要な場合)
- 販売業許可申請書の提出
- 営業所の実地調査
- 許可証の交付
1.保健所への事前相談
まずは、図面や管理体制の概要をもって保健所に相談するところから始めます。
構造や設備の基準、申請書類のフォーマット、手数料などは自治体によって細かく異なるため、独自判断で進めるのは危険です。
サロン併設型やネット専業の場合は、判断が分かれやすいので、必ず早めに確認しておきましょう。
2. 申請書類の作成・提出
主な提出書類は、以下のとおりです。
- 高度管理医療機器等 販売業許可 申請書
- 営業所の案内図・平面図
- 構造設備の概要図
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 営業管理者の資格証明書類(修了証など)
- 使用関係証明書(雇用契約書など)
- 医師の診断書(必要な場合)
- 手数料(5,000~20,000円程度、自治体により異なる)
3.営業所の実地調査
書類審査の後、保健所職員による実地調査が行われます。
照明・換気・清潔度、商品保管スペースの区分状況などが確認され、問題がなければ承認に進みます。
ここで「生活スペースと区別がついていない」「管理者の常駐体制が不十分」といった理由で差し戻されるケースがあるため、現場の見た目や説明内容を整えておくことが重要です。
4. 許可証の交付
調査に通過すれば、1〜2週間前後で「高度管理医療機器等販売業許可証」が交付されます。
この許可は営業所単位で発行されるため、新たに店舗を増やす場合や移転する場合は、改めて申請が必要です。
また、有効期間は各自治体で5〜6年が一般的で、更新時も再度の申請・実地確認が行われます。
第5章 よくある誤解Q&A
Q1. ネット販売だけなら、許可はいらないのでは?
いいえ。販売形態にかかわらず、商品を保管・出荷する拠点が営業所として登録されている必要があります。
たとえ店舗を構えずオンラインのみで販売していても、倉庫や自宅の一室などで商品を保管・管理する以上、その場所が営業所扱いになります。
「実店舗がないから大丈夫」と誤解して無許可販売を行うと、行政指導や営業停止処分の対象になり得ます。
Q2. 美容室やサロンで販売することは可能ですか?
可能ですが、販売スペースと施術スペースが明確に分かれていることが条件です。
サロンの一角で販売棚を設ける場合、施術用具や化粧品と同じ場所で保管していると指摘を受けることがあります。
また、保健所によっては、衛生管理責任者との兼任を問題視される場合もあるため、構造図と動線を添えて事前相談するのが安全です。
Q3. 医師や薬剤師でないと販売できませんか?
所定の講習を修了すれば、医師・薬剤師以外でも販売管理者になれます。
講習修了証を提出することで、資格者と同様に管理者として認められます。
ただし、名義貸しや管理者の常駐義務違反は法令違反に該当するため、実際に管理業務を担う人が登録されている必要があります。
Q4. 既に雑貨として販売してしまった場合は?
法的には、販売行為を中止し、速やかに保健所へ相談することが望ましいです。
後から発覚した場合でも、誠実に是正対応を行えば行政指導で済むことがありますが、繰り返し販売を続けた場合には罰則の対象になります。
特に、SNS広告やネットモールでの販売は監視が強化されているため、「知らなかった」では済まされない点に注意が必要です。
まとめ
カラコンの販売は、見た目こそファッション雑貨に近いものの、法律上はれっきとした「高度管理医療機器」の扱いです。
販売には、営業所の構造基準を満たし、営業管理者を設置したうえで「高度管理医療機器等販売業許可」を取得する必要があります。
手続きの流れ自体は難しくありませんが、どの段階で保健所に相談するか、どのような形態で販売するかによって求められる対応は変わります。
特に、サロン併設型やネット専業型の事業では、営業所の定義を誤るケースが多く、申請前の確認が重要です。
この許可制度は、販売者を縛るためのものではなく、使用者の安全を守るための仕組みです。
衛生管理や保管体制をしっかり整えることは、事業者としての信頼にもつながります。
流行や価格競争に流されず、「安全に販売できる環境を整えること」こそが、長く続く店舗経営の基盤になるでしょう。