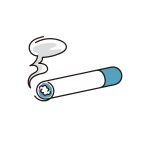当サイトの一部に広告を含みます。
Contents
関連投稿
「副業を始めよう」
「開業届を出そう」
このとき、真っ先に考えるのが屋号やアカウント名ではないでしょうか。
どんな名前にしようか。
どんなイメージで届けようか。
事業のはじまりに立ち会うこの“命名作業”は、特別な時間でもあります。
けれど、ほんの一歩踏み違えたことで、その名前が「すでに他人のもの」だったと発覚するケースが後を絶ちません。
ブログのURL、SNSアカウント、名刺のロゴ、あるいはドメイン名。
それらすべてが「使用中止」となり、やり直しを余儀なくされる。そんな事例を見てきました。
本記事では、屋号に関する商標トラブルの仕組みと、避けるために知っておきたい基礎知識、さらに動画で伝えきれなかった実務目線での対応策まで解説していきます。
「知らなかった」では済まされない時代。
名前を武器にするか、リスクに変えてしまうかの分かれ道において、この記事が小さなヒントとなれば幸いです。
第1章|屋号は「自由に決めていい名前」ではない
開業準備の最初期、多くの人が真っ先に着手するのが「名付け」です。
SNSアカウントやブログのタイトル、名乗る肩書きに至るまで、すべての出発点に“名前”があると言っても過言ではありません。
しかし、この「名前」は、好きなように名乗って良いものではありません。
なぜなら、屋号や名称の使用には“商標権”という壁があるからです。
たった一言の名前にも“所有者”がいる
「商標権」とは、簡単に言えば「名前やマークの使用を独占できる権利」のことをいいます。
特許庁に登録されている言葉やロゴは、登録した人(または法人)が「他人に使わせない権利」を持っているものです。
- 無名の個人でも
- 営利目的でなくても
- 商標登録されている名称と似ているだけでも
上記にような条件であっても、他人の商標を使用しただけで「商標権侵害」として、使用中止や損害賠償を請求されるリスクが生じます。
「個人事業主だから関係ない」は通用しない
個人事業であれば、会社法のような法人登記は必要ありません。
けれど、商標に関しては法人・個人の区別は一切ありません。
有償無償、目的に関わらず、無断使用した瞬間から立派な“権利侵害”です。
そのため、次のようなケースもリスク対象になります:
- 個人で運用するSNSアカウント名
- ハンドルネーム+肩書き(例:○○行政書士)
- ブログのタイトル
- 屋号やサービス名
- 登録したドメイン名
つまり、「副業であること」「お金を取っていないこと」「フォロワーが少ない」等の主張は一切の免責理由にならないということです。
たった1つの名前が“全てを壊す”こともある
実際に、屋号やアカウント名をめぐるトラブルによって
- 使用中止の要請が届く
- ドメインやSNSのアカウント凍結
- 名刺や販促物等の回収と刷り直し
- パクリ扱いされて信用失墜
- 売上激減
という事例が報告されています。
そして、その多くは「知らぬまま使用していた」ことが発端です。
第2章|「名前が被った」だけで起こりうる現実
「商標?大企業の話でしょ?」
「同じ名前でも、うちは個人事業だし大丈夫でしょ?」
そう思っていた人のもとに突然届く1通の警告文。
その瞬間、あなたが築いてきた事業基盤は崩れ始めます。
「使用中止」「損害賠償」「アカウント凍結」…事態は“全撤退”レベルに
商標権の侵害が認められた場合、次のような事態が現実に起こります。
- 名刺、Webサイト、チラシ等の即時差替え
- 既存ドメインやメールアドレスの使用停止
- X、Instagramアカウント等の凍結
- 信用失墜による顧客離れ
- 損害賠償や訴訟対応コストの発生
つまり、ただの「名前かぶり」が、事業の土台を揺るがすリスクに直結する可能性があります。
「こっちが先に使ってたのに!」が通用しない世界
特に注意すべきなのが、商標法では「先に使った人」より「先に登録した人」が保護される点です。
あなたが先に名乗っていても、後にその名称を商標登録した人がいる場合、あなたは“侵害者”として扱われる可能性があります。
これは副業・個人事業主にとって非常に厳しいルールですが、現行の制度上、回避不能な“地雷”でもあるのです。
実際に起きたゾッとする商標トラブルの例
事例①|「ことのは行政書士事務所」→ 使用中止命令
副業として「ことのは行政書士事務所」の屋号で活動を始めたAさん。
名刺、ブログ、SNSアカウントを整え、順調に集客を続けていました。
しかし、ある日「名称の使用を中止するよう求める通知書」が届きます。
「ことのは」は別の事業者によって商標登録済みだったのです。その結果、
- ドメイン+SNSアカウントの削除👉変更
- 名刺・広告の刷り直し
- 検索順位の大幅下落
- 名称の変更に顧客困惑
再起にかかった時間とコストは、事業初期としては致命的でした。
事例②|美容系ブログ「すっぴん堂」→ SNS凍結・信頼喪失
長年コツコツと更新していた美容系ブログ「すっぴん堂」。
フォロワー数も伸び、収益化も進んでいた矢先に、突然のXアカウント凍結。
原因は、既存の登録商標と名称が類似していたこと。
意図せぬ侵害であるにもかかわらず、「偽物」のコメントが相次ぎ、運営者の信用は急落しました。
ブログ自体は継続できたものの、SNS集客の導線が絶たれたことで実質的な「事業終了」状態となってしまったのです。
第3章|“調べれば防げる”――商標リスクの回避術
これまで見てきたように、名前をめぐる商標トラブルは、想像以上に深刻な損失をもたらします。
逆に言えば、きちんと事前調査(商標検索)を行ってから名前を決めることで、そのほとんどを未然に防ぐことができるのです。
商標検索の第一歩:J-PlatPat(ジェイ・プラットパット)
特許庁が提供する「J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)」は、誰でも無料で商標登録の有無を確認できる公式ツールです。
🔍 アクセス方法
「J-PlatPat 商標」などで検索
→ https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
🔧 基本の検索手順(称呼検索)
- トップページから「商標」を選択
- 「称呼(読み)」欄に、カタカナで読みを入力(例:「コトノハ」など)
- 表示された一覧から
・登録番号
・権利者名
・指定商品・役務(=対象業種)
を確認
※ 業種が近いとアウトの可能性があるため、必ず内容まで目を通しましょう。
よくある落とし穴:「同じ名前じゃなければ大丈夫」は誤解
商標上は、「同一」でなくても、以下に該当する場合は「類似」とされます。
- 見た目が似ている(例:kotonohaとcotonoha)
- 読み方が似ている(例:ことのはとコトノハ)
- 意味が似ている(例:すっぴんと素肌など)
つまり、一見違うように見えても、専門家の目には“同一視”される場合があるのです。
そのため、「検索して何も出なかったからOK」ではなく、「似たような響き・表記・意味も含めて確認する」ことが重要です。
他にも見ておきたいチェックポイント
屋号・名称を決める際は、以下もあわせて確認しましょう。
- 取得済みドメインの有無(.jpや.com等)
- X、Instagram、TikTok等 SNSアカウント名の空き状況
- ロゴや肩書きとして使用予定のキーワード検索
また、以下のようなネーミングは特に注意が必要です。
- 映画、アニメ、商品名等を含む名称(例:ジブリ行政書士等)
- 特定の地域名+職業名(※観光地、ブランド知名は要注意)
- 一般的な褒め言葉や願望を含むワード
「オリジナルのつもりでも、すでに登録されている」現実
「完全に自分で考えた名前だから大丈夫」と思っても、まったく同じ発想で先に商標登録されているケースは珍しくありません。
むしろ、“オリジナルのつもり”だった人ほど、調査を怠りがちです。
だからこそ、発想に自信がある人ほど、商標検索を欠かさないでください。
第4章|商標リスクを避けつつ、“育てられる名前”をつくる方法
商標トラブルを避けるために検索することはもちろん重要ですが、そもそも“被りにくい名前”を作っておくことこそ、最大の防衛策です。
加えて、選んだ名前が、長く育てていける“資産”となるかどうかも見極めなければなりません。
ここでは、初心者でも実践しやすいネーミングの基本原則と、工夫のヒントを紹介します。
1|「ありふれた言葉」は避ける:検索ヒットの罠
ひらがなで柔らかく見える単語や、ポジティブな印象の言葉は人気が高く、他人と被る確率も急上昇します。
たとえば、
- ひかり、つばさ、こころ、すこやか等
- 一般名詞や抽象語(例:しあわせ、みらい、希望等)
これらは「検索しても埋もれてしまう」「商標に引っかかる」など、事業名としての独自性が保てないという問題を抱えています。
2|造語や組み合わせで“ひねる”:意味ある違和感をつくる
完全な造語(例:「ファルネス」「ジオララ」)は被りにくい一方で、覚えてもらえなかったり、印象に残らないリスクもあります。
そこでおすすめなのが、意味のある言葉を複数組み合わせる手法です。
例
- 和×法律=なごりつ行政書士
- 空×相談=ソラみち事務所
- 動物×安心=あんどうペット相談室
複数の要素を組み合わせることで、親しみやすさと独自性の両立が可能になります。
3|“自分だけの文脈”を入れる:ストーリーで差別化する
他人が思いつかない名前は、「他人が経験していない文脈」から引き出すのが近道です。
自分だけのルーツや好み、記憶、価値観を軸にすることで、見た目以上に“真似されにくい”名前が生まれます。
ヒント
- 幼少期に暮らした地名
- 好きな色や動物、季節
- 音楽、アニメ、映画の影響(※商標との距離は要確認)
- 自分の心情や座右の銘等の一部
例
- 地元の川の名前+業種
- 好きな紅茶の名称から連想する事務所名
- 飼っていたペットの名前をもじったネーミング
4|名前を決めた後に“すぐやること”:初動で守りを固める
名前が決まったら、以下のステップを“発注前”に必ず済ませましょう。
✅ 商標・ドメイン・SNSの三点確認:
- J-PlatPatで再確認(※スペル違い、語感違いも含めて確認)
- ドメインの空き状況チェック(.jp/.com/.net等)
- X、Instagram、TikTok等のアカウント名の空き状況チェック
✅ その他注意点:
- 名刺やチラシの発注は確認完了後に行う
- Google検索等の結果に自サイトが表示されるよう整備
- 他の事業者が類似の名前で運営していないか実際に検索して確認
「ネーミングなんて、事業の“飾り”」
こう思う人もいるかもしれませんが、現代においての屋号とは「検索性」「識別性」「信頼性」を支える戦略資源です。
だからこそ、「なんとなく」で選ばず、“事業の土台”として丁寧に作る価値があるのです。
おわりに|「名前」を守ることは、自分の事業を守ること
副業でも、開業でも、最初に掲げる「名前」はあなたの想いと覚悟を象徴するものです。
名刺に刻む屋号、SNSのアカウント名、検索されるブログのタイトル。
すべてが、“あなた自身”として認識され、広がっていきます。
だからこそ、その名前がある日突然「他人の権利を侵害している」として奪われてしまうことの重みは、計り知れません。
けれど、今日この瞬間に知ったあなたは、もう“無防備なまま”ではありません。
商標の存在に気づき、調べる手段を知り、そして、育てられる名前の作り方を学びました。
今はまだ、小さな一歩かもしれません。
けれどその一歩が、未来のトラブルを確実に防ぎ、あなたの名前を、あなた自身の力で守る礎になります。
さらに詳しく学びたい方へ
屋号選びの壁打ち相談やネーミング+商標検索のご支援は公式LINEにて対応しています。
公式LINEはこちら