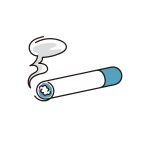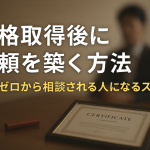当サイトの一部に広告を含みます。
当ページでは、相続人の中に「成年被後見人」がいる場合の相続手続に必要な書類と注意点を解説します。
成年後見人とは
成年後見人とは、ご自身で判断を下すことが難しい人の代わりに、法律や生活の手続を支える人のことをいいます。
具体的には、病気や障害(身体・精神)等により、契約や財産管理を自力で行うのが難しい人(=成年被後見人)がいる場合。
その人を守るために「成年後見人」を選ぶ必要が生じます。
成年後見人が相続手続を行う場合
相続手続において、成年後見人が被後見人の代わりに手続を進めるには、被後見人の登記事項証明書が必要です。
その他にも、手続先の機関から追加書類を求められる場合もありますので、事前に確認しましょう。
以下に、主なものを整理しますので参考にしてください。
- 被後見人(本人)の戸籍謄本
- 被後見人の印鑑登録証明書
- 故人の戸籍一式
- 故人の住民票の除票、または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 後見登記事項証明書
- 後見人の本人確認書類
- 後見人の印鑑登録証明書
- 【預金解約・払戻し】金融機関指定の相続手続依頼書、委任状、残高証明書等
- 【不動産登記】登記原因証明情報、固定資産評価証明書、登記申請書等
成年後見人が相続手続を行う際の注意点
後見人が被後見人と同じく相続人の場合、相続財産清算人の選任申立てを行わなければなりません。
なぜなら、「自分(後見人)の取り分を多くしたい」と「本人(被後見人)の取り分を守りたい」という利害が衝突することになるからです。
そのため、家庭裁判所は後見人任せにせず、本人の代わって公平に相続手続を進められる中立の人(相続財産清算人)を選ぶ仕組みをとっています。
たとえば、親が亡くなった際、後見人の子(本人)と後見人である兄(本人のきょうだい)双方が相続人の場合。兄は、弟の相続分を守る側ですが、自らも相続人である以上、「自分の取り分を決める交渉相手」となってしまいます。
だから裁判所は、「その手続は中立の人に任せましょう」と判断します。
似たような事例として、被後見人が未成年の場合、特別代理人の選任申立てを行う必要があります。
要するに、後見人と本人が同じ相続人の場合、後見人はその相続手続に関わることはできず、代わりに家庭裁判所が中立の人を立てることとなります。
後見人は「本人の財産を守る」立場なので、他の相続人と利害が対立する場合には、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があるんですね。
相続人に被後見人がいる場合の相続手続まとめ
当ページでは、相続人の中に被後見人がいる場合の相続手続について解説しました。