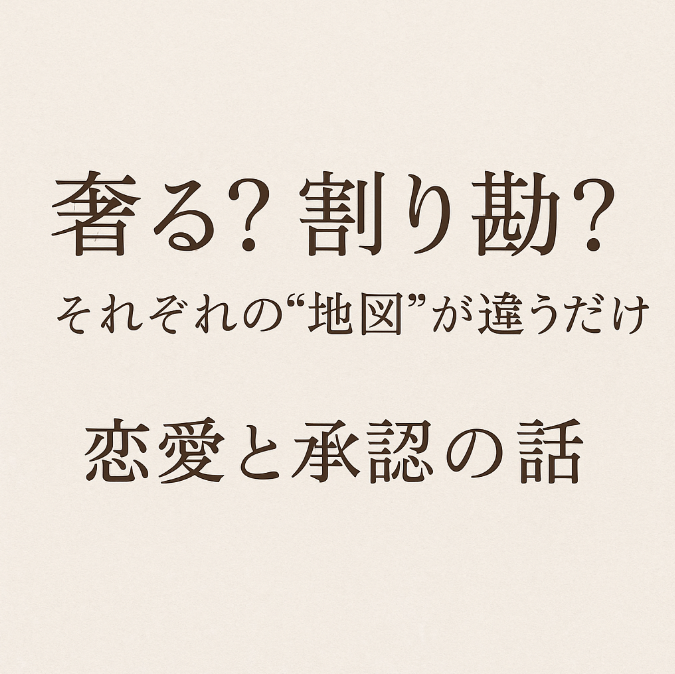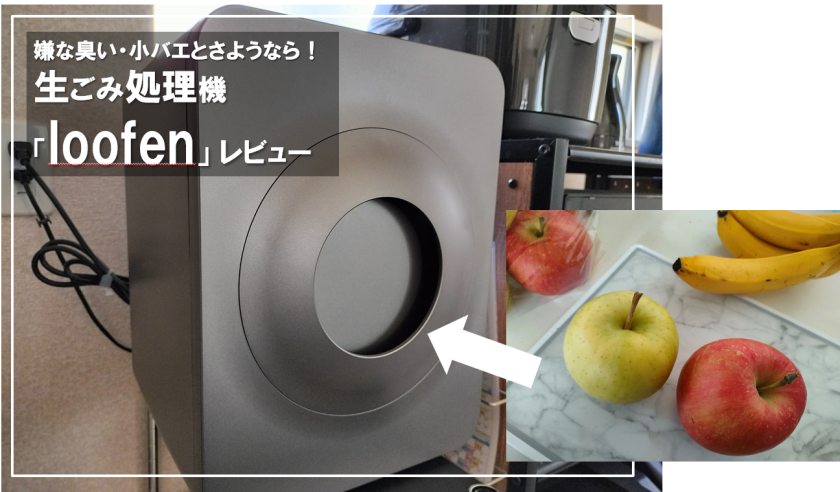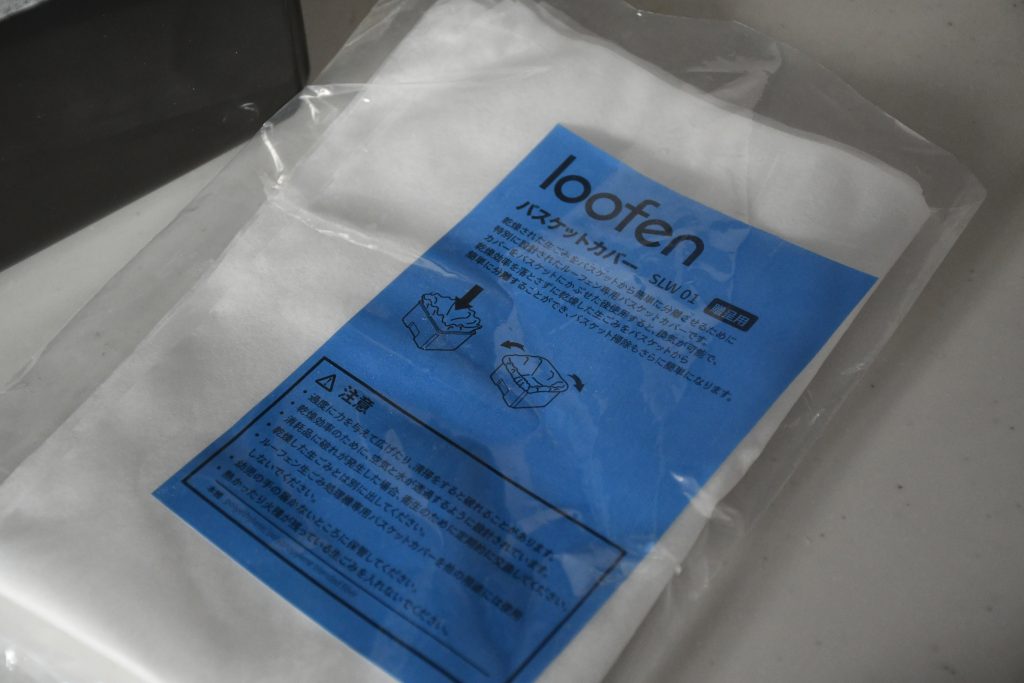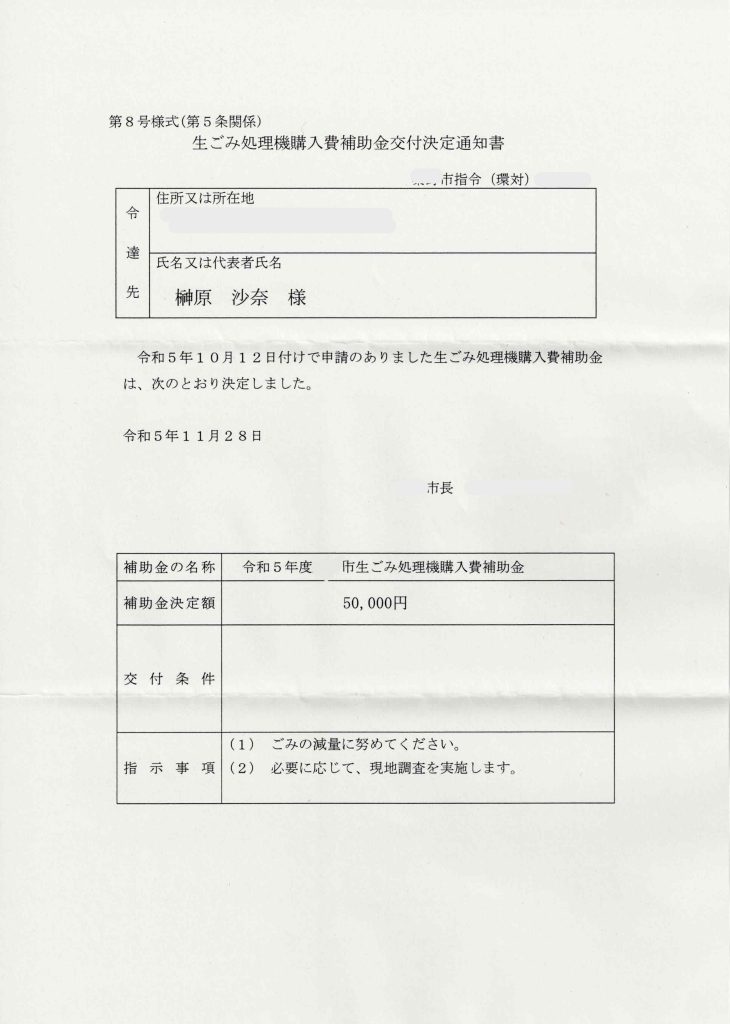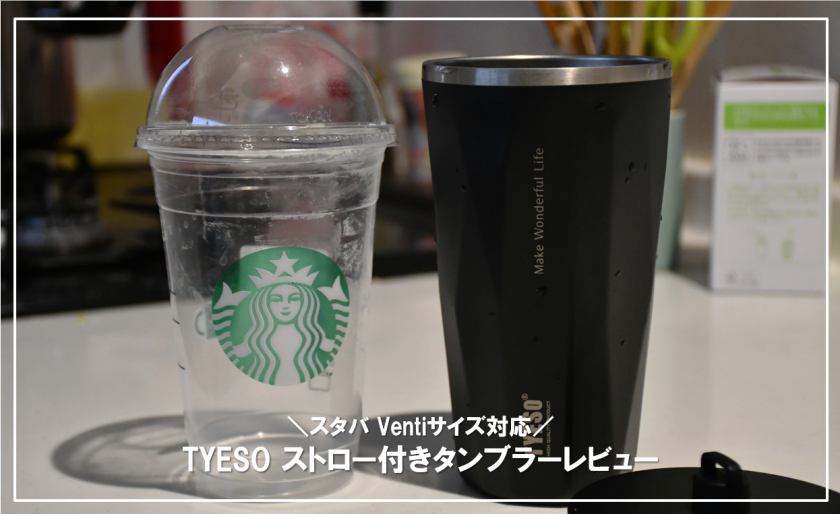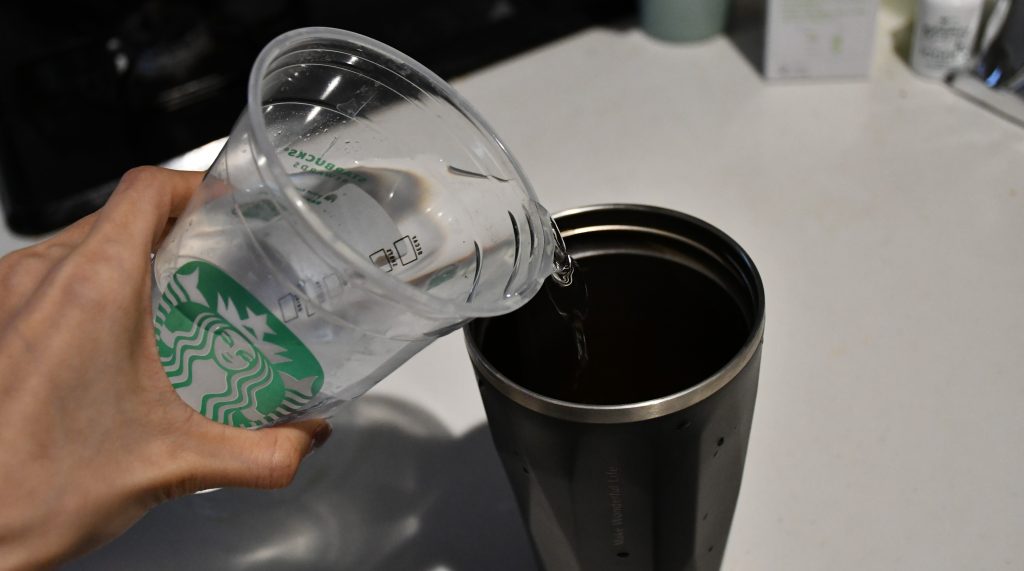当サイトの一部に広告を含みます。
関連投稿
女の子だから天皇になれない
それが制度として決まっていることは、知識として理解していました。
しかし、今になりその言葉を目にして、思わず立ち止まりました。
それは、敬宮愛子さまがご成年を迎えられた際のご挨拶を拝見して以降、私の中にひっかかっていた“ある違和感”とつながったからかもしれません。
「制度上の話」ではなかった
あのとき拝見したご挨拶──ご本人の声で、まっすぐに語られる言葉。丁寧で落ち着いていて、それでいて、どこか内に静かな芯が通っているように感じました。
私はその瞬間、はじめて“敬宮さま”という存在を「天皇陛下のご息女」でもなく「女性皇族」でもなく、“ひとりの人”として意識した気がしたのです。
それまで、私はどこかで「制度の一部としての存在」としてしか捉えてこなかったのかもしれません。
語られ方に感じた“モヤ”
ご挨拶の映像をまだご覧になっていない方へ──
敬宮さまが成年を迎えられた際の記者会見の模様を、以下の動画でご覧いただけます。
その後、SNSなどで目にした反応の中に、こんな言葉がありました。
- 「女の子だから、継げないのは仕方ない」
- 「雅子さまに似ていて安心できる」
- 「帝王教育を受けてきたから優秀に決まっている」
いずれも悪意があるとは思いません。
でも、そこにあるのは「個」ではなく、「背景」や「血統」による“ラベル”です。
たしかに、親の影響や育ちの環境は、人をつくる一因でしょう。
でも、それだけで語られてしまうと、その人がどんな思いで立っているかが見えなくなる。
そしてそれは、皇室に限った話ではなく、私たちの身近にも、当たり前のように起きていることなのだと思います。
「通信制」「片親」「多産家庭」──私が言われてきたこと
私はこれまで、「通信制高校しか出ていない」「片親で育った」「多産家庭だから育ちが悪そう」など、出自や環境だけで判断された経験が何度もあります。
そして、実際にそういう目で見てくる人たちは、私が何を考え、何を積み上げ、どんな言葉を使っているかにはまったく興味がないようでした。
“見る目”は、誰かのためだけじゃなく、自分自身のためにある
一時期、人事の仕事をしていたことがあります。
だからこそ、背景や学歴が「参考情報」として用いられる場面があることは、よく理解しているつもりです。
けれど、その“情報”が“評価のすべて”になってしまうと、その人の「今」や「これから」に光が当たらない。
そしてその構造は、他人に向けられるだけでなく、自分自身の生き方すらも、見誤らせてしまう危うさを含んでいるように思うのです。
誰をどう見るか──それは、どう生きたいかとつながっている
あのご挨拶を拝見したとき、敬宮さまは「評価されるため」ではなく、「言葉を尽くすこと」を選んでいるように感じました。
それは、とても勇気のいることです。
自分の姿勢や考え方を、背景も含めて、丁寧に外に差し出すこと。それを「誰かにどう見られるか」を超えてやるのは、簡単なことではありません。
だからこそ、「この方を、私は“誰かの娘”としてではなく、“ひとりの人”として見たい」
そう思ったのだと思います。
最後にひとつ、問いを置かせてください
あなたは今、誰かを「その人自身」として見ていますか?
肩書きや育ち、過去の環境だけで、その人の“今”や“これから”を測っていませんか?
そして、自分自身もまた、「何者か」で語られることで、本当の姿を隠してしまってはいないでしょうか。
あのご挨拶は、私にとって、“見る目”をほんの少し整えるきっかけを与えてくれました。
もし、あなたの中にも何かが残ったなら、それが“誰かを見る目”だけでなく、“自分を見る目”にもつながっていけば──そんなふうに願っています。
🎥関連記事
📺 このテーマに関する動画は近日公開予定です。