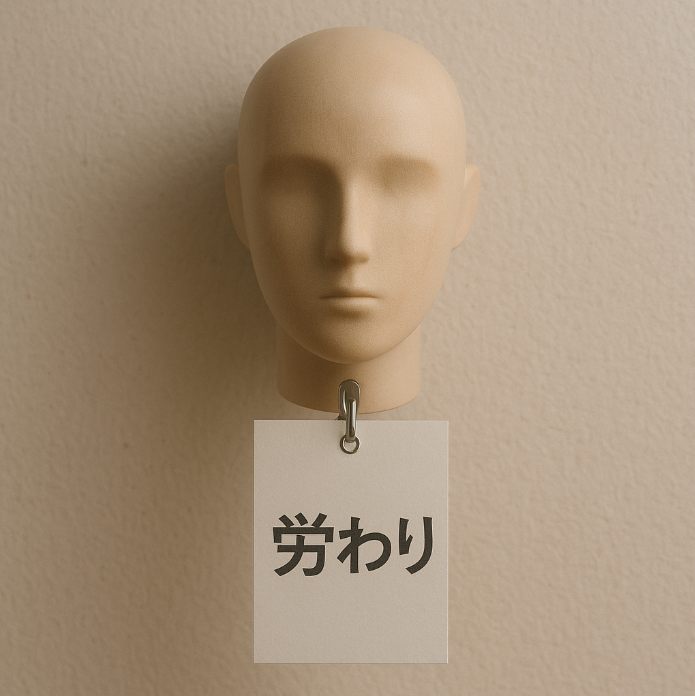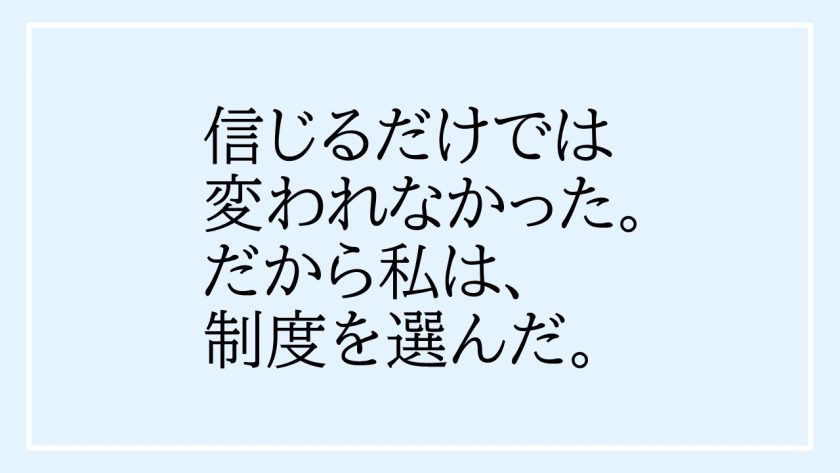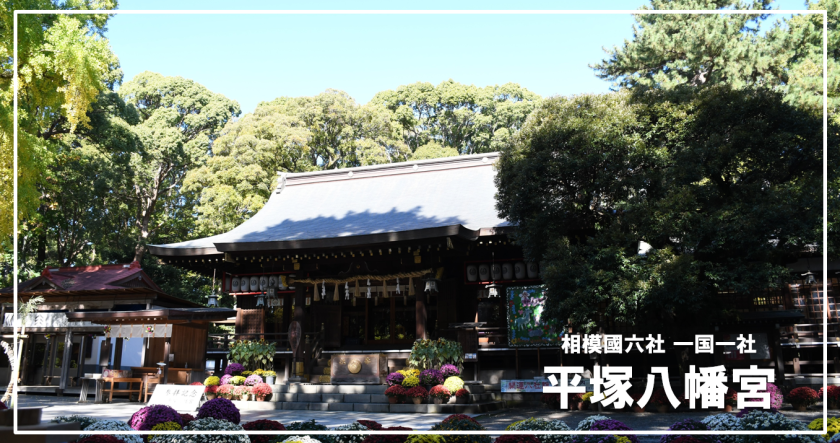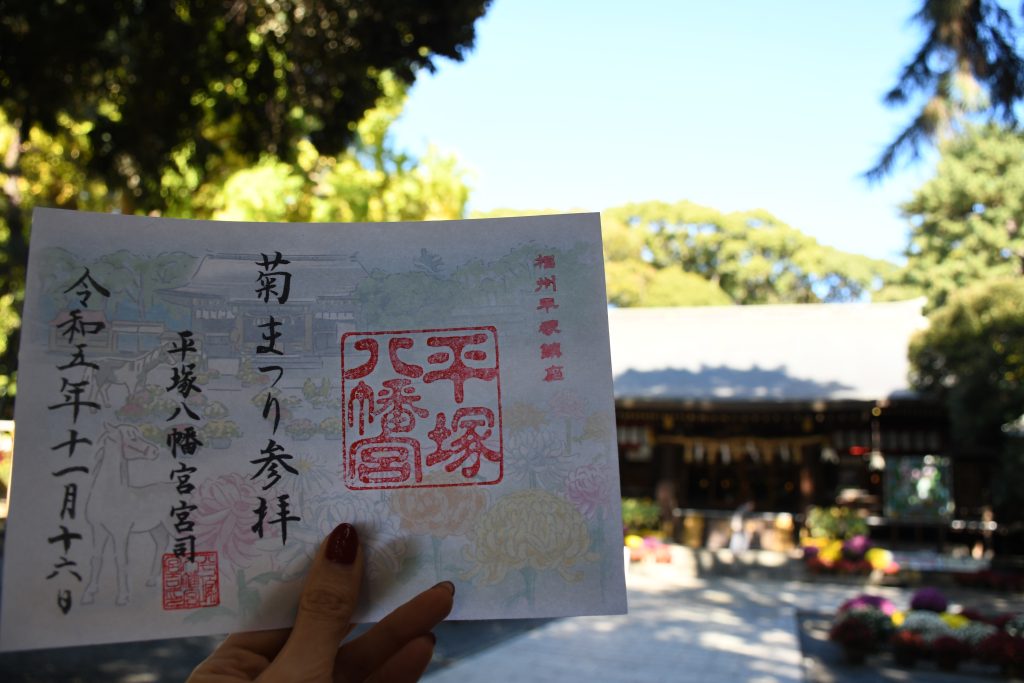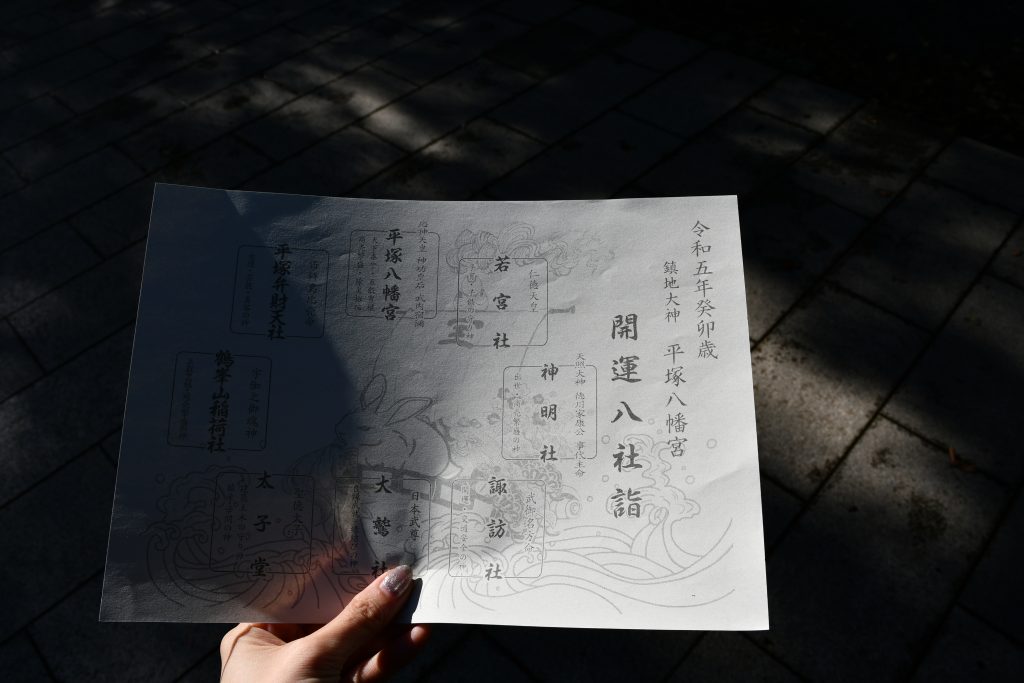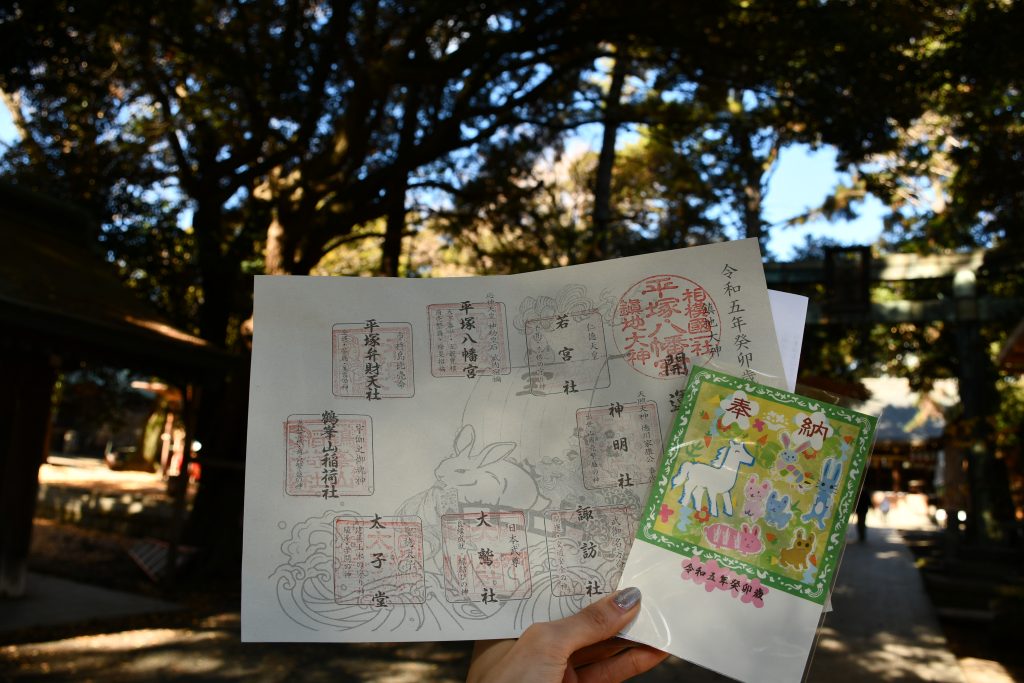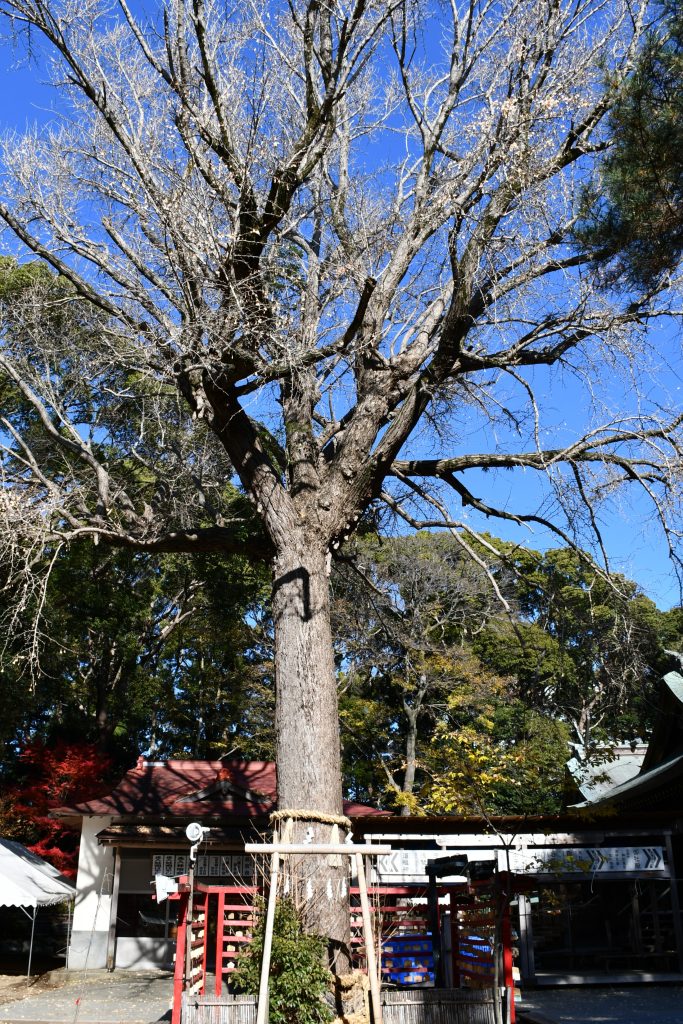当サイトの一部に広告を含みます。
関連投稿
「○○さんは大変そうだから、そっとしておこうね」
職場や地域、どこかの集まりで、そんな言葉を聞いたことはありませんか。
疲れているように見える人、年齢が上の人、なんとなく”しんどそう”に見える人には、たいていの人が自然とやさしく接します。
しかしーその言葉の裏で、実際にどれだけのことをやっていたのか、見られているのでしょうか。
そして黙って、その人のぶんまで働いている誰かが、見落とされていないでしょうか。
私はただ、「しんどそうな人ばかりが得する構造」が当然のようにそこにあると、時々どうしようもなくモヤモヤします。
大変そうな人に注がれる気遣い
たとえば、明らかに業務をサボっている人がいる。
責任は回避し、自分の仕事は他人に押し付けるのになぜか、周囲からは「大変でしょう」「無理しないでね」と気遣われている。
一方で、黙々と働き、そのような人が抜けた穴を埋めている人がいたとしても、そちらには「しっかりしてるね」「頼りになるよ」と声を掛けるだけで終わる。
誰かのしわ寄せを受けているにもかかわらず、”ケアの対象”にはならない。
おかしいと思いませんか。
苦労しているかどうかではなく、しんどそうに見えるかで評価や扱いが決まってしまう。そしてその「気遣い」は、見えるしんどさにばかり集中する。
これは、偶然ではありません。
むしろ、弱っているように振る舞うことが、無意識のうちに特権のように機能してしまう構造なのです。
包帯を巻き続ける人の心理
本当は治っているにもかかわらず、いつまでも包帯を巻き続け、「まだ痛いです」と見せる人がいるます。このような行動は、意識的なものと、無意識なものがある。
しかしどちらにも共通するのは、「弱っていることで得られるものがある」ということ。
これは心理学でいう「二次的利得(セカンダリー・ゲイン)」に近いのではないでしょうか。
つまり、病気や不調そのものではなく、その状態でいることで得られる”まわりの優しさ”や”免除”に価値を感じる構造をいいます。
たとえば、
- 「大変ですね」と声をかけてもらえる
- 責任をもたなくて済む
- 厳しい評価を避けられる
- 周囲が忖度してくれる
一度このポジションについてしまうと、そこから動きたくなる人もいます。
なぜなら、彼らにとって”元気になること”はリスクになるのだから。
元気になると、「じゃあちゃんとやっておいてね」「それはあなたの責任でしょ」と言われてしまいます。
だから、「治った」とは言いませんし、包帯も外しません。
こうして彼らは、自分を”保護される存在”としてキープし続けるのです。
やさしさが歪める構造
もちろん、大変そうな人を気遣い、声をかけることには賛成です。人を思いやる気持ちがあるのは、とても素晴らしいことですから。
けれどそのやさしさが、ろくに何も見ないで発動されたものだとしたらー。
たとえば、高齢者世代の人たちが、何の悪気もなく発する「年下なんだから支えてあげなさい」という言葉。あるいは、「○○さんは疲れているんだから、あまり言わないほうがいいわよ」など。
しかしその○○さんが、実はサボっていて常に責任転嫁。そのしわよせを食らっているのは、声を上げずに堪え、穴を埋め続けている誰かです。
外形的にしんどそうな人だけがピックアップされ、気遣われ、そして気を遣った人たちはどこか良いことをした気になって。
本当に守られるべきは、黙って耐え忍んでいるこの構図が不思議に思えてなりません。
気遣いが見える弱さにのみ集まっている限り、構造は歪んだまま。やさしさは時に、それ自体が無責任な「逃げ」となるのです。
見落としてはいけない「静かにがんばる人」
この記事でお伝えしたいのは、「しんどいアピールをする人がずるい」という単純な話ではありません。
本当に弱っている人や、言葉にできない苦しみを抱えている人がいること。
けれど、声の大きい”弱さ”ばかりに気を取られ、声を上げない”強さ”や”誠実さ”が見過ごされる状況について、やはりおかしいのではないかと思います。
見えない部分で毎日責任を果たし、誰かの文まで背負い、それでも静かに働いている人がいます。
そういう人にこそ目を向け、気づき、労ってあげてほしいと思います。