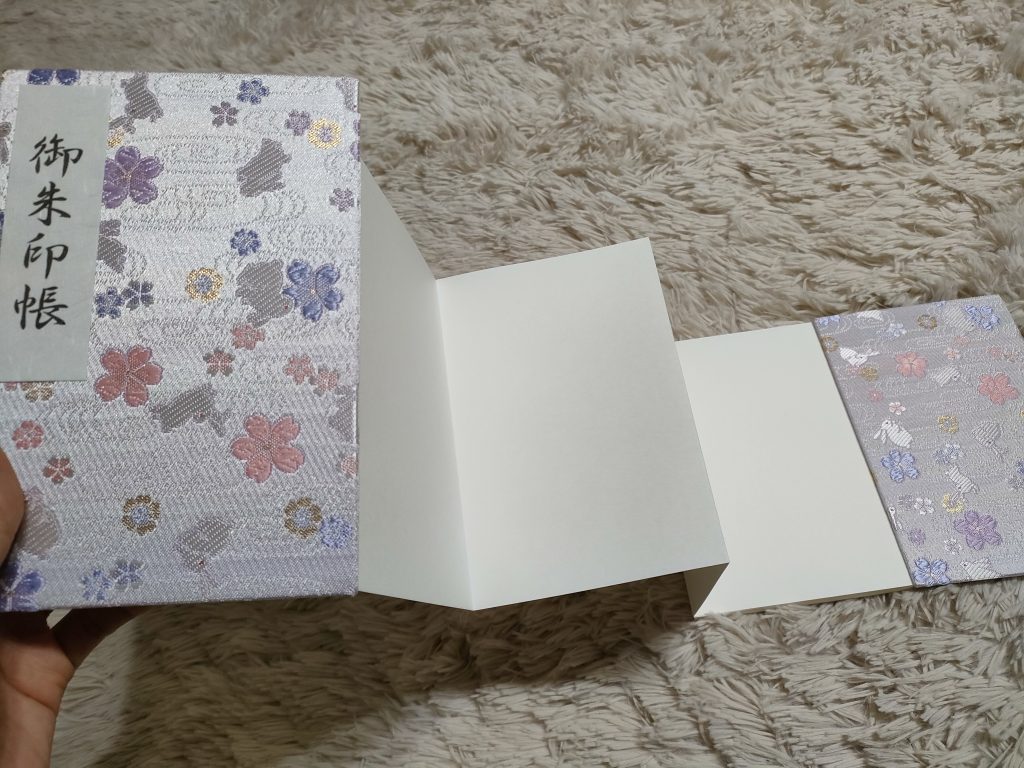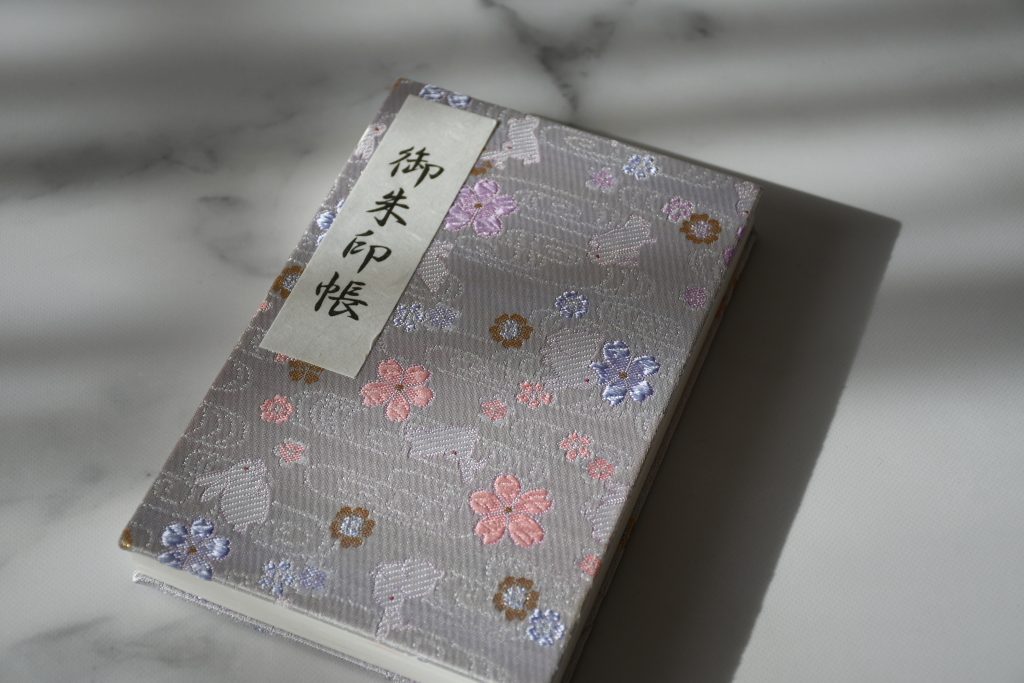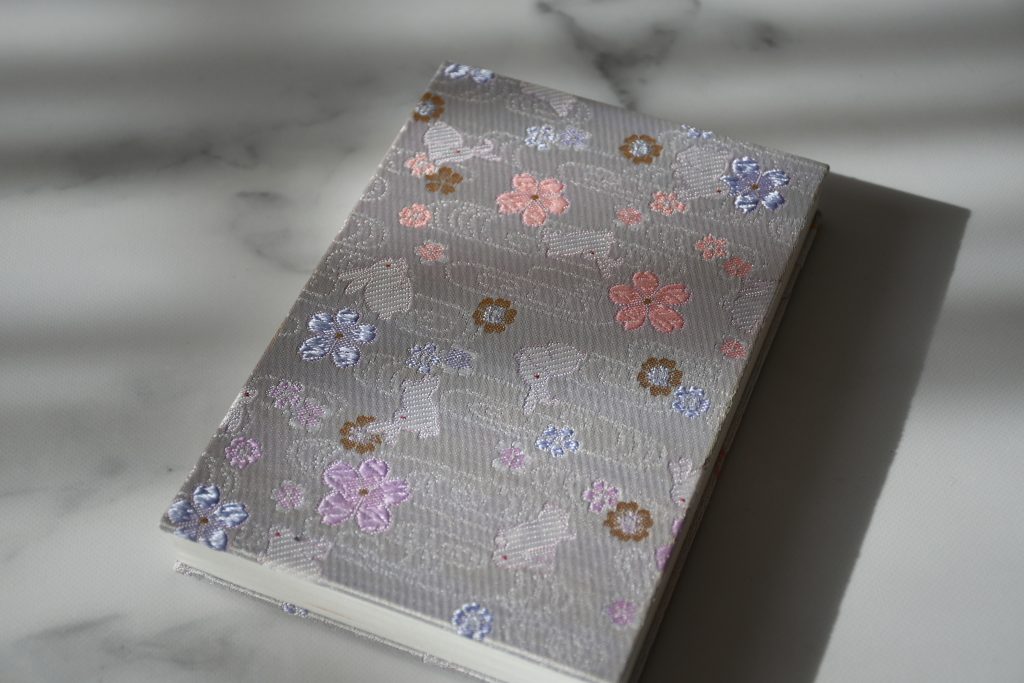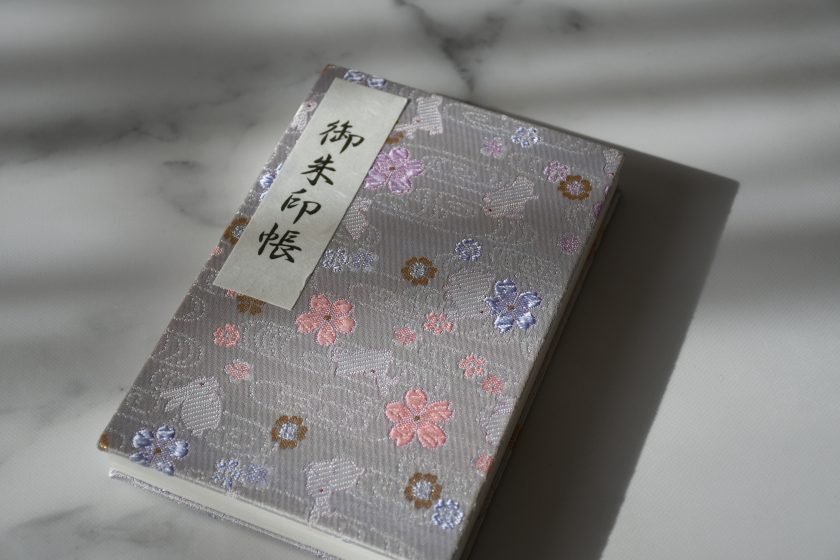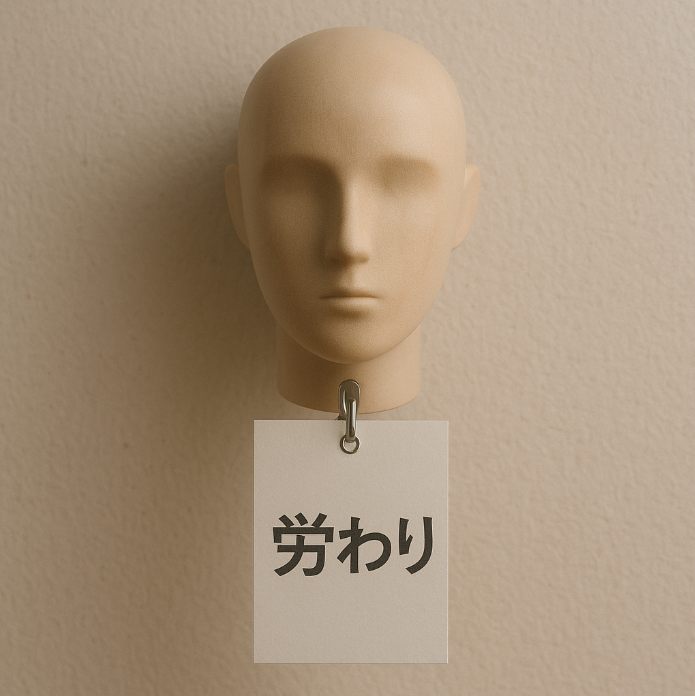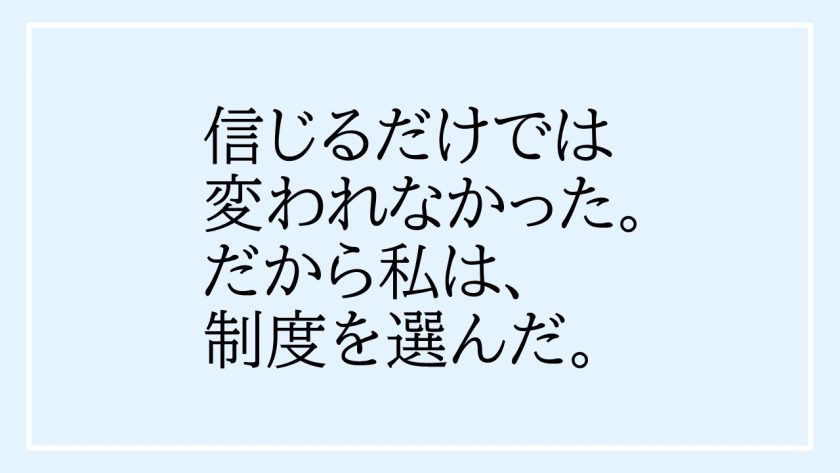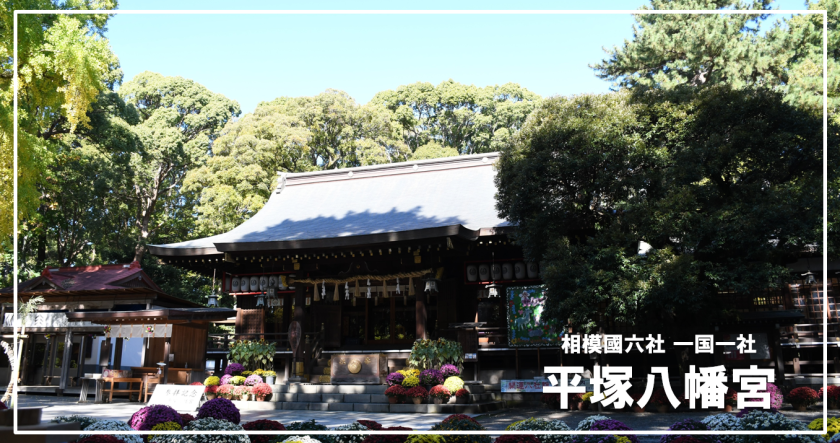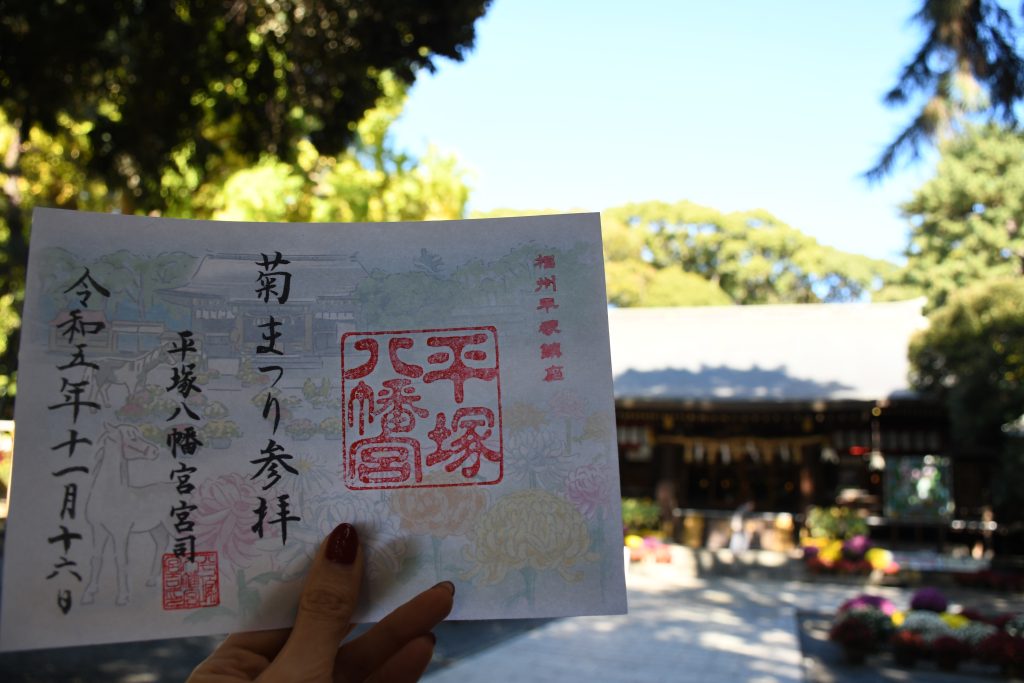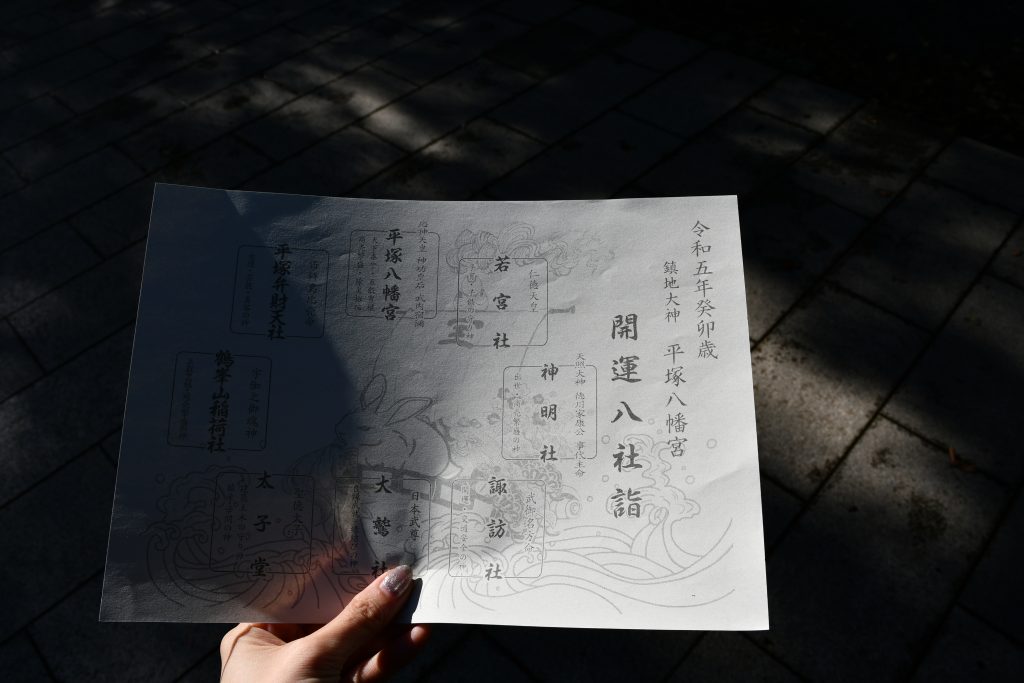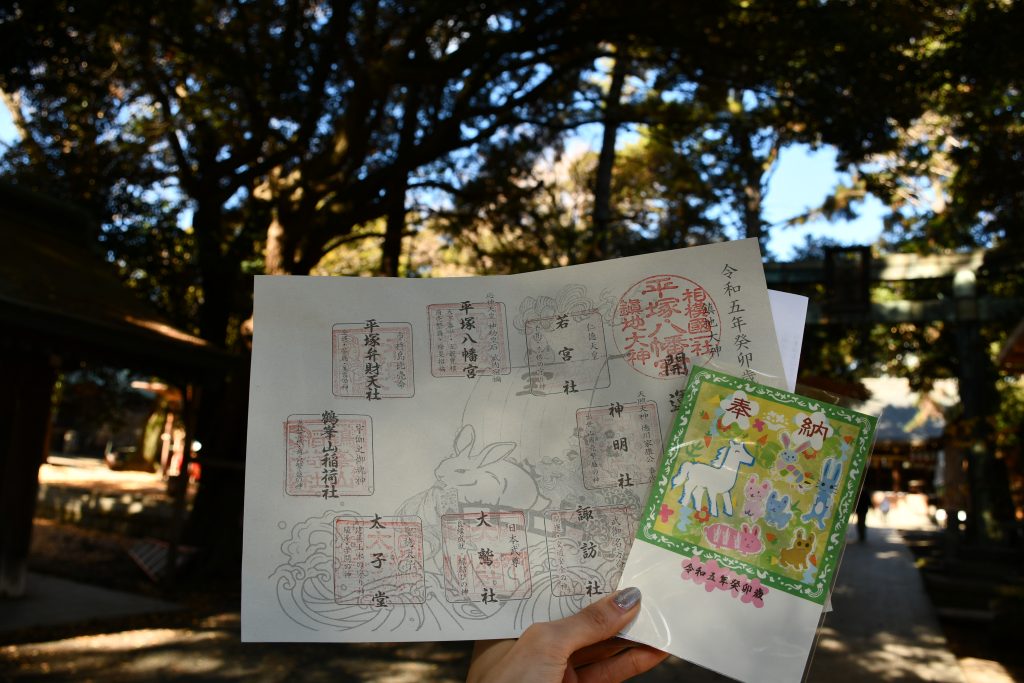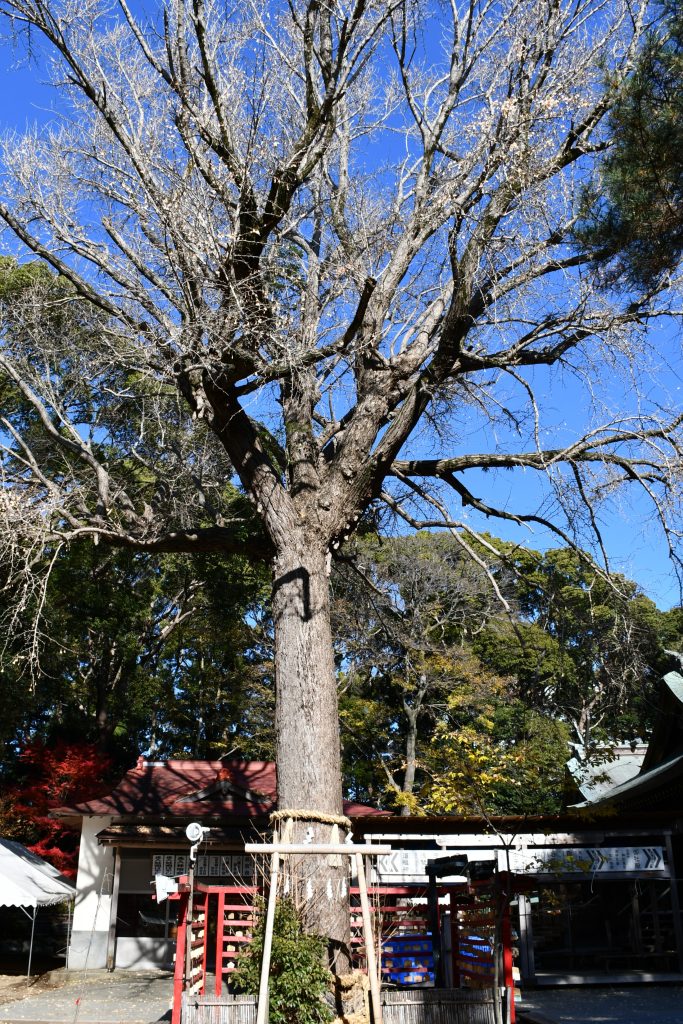当サイトの一部に広告を含みます。
どこにでもいそうな顔で、どこにでもありそうな恋をする。
しかし彼らはなぜか、”特別な愛”を演じたがる。
既婚者の中年俳優と、世間から清純派とみなされていた若手女優。
本気だと言いたげな眼差しで交わす言葉の裏に、本気でないことを互いに知っている空気が透けて見える。
誰のものでもないと言いたげな眼差しを携え、互いに「自分だけは特別」だと信じたがっている。
本当に大切に思っているのならなぜ、堂々と愛せないのか。
なぜ家庭に帰り、なぜ彼女は待ち続けるフリができるのか。
家庭もキャリアも失いたくはない。それでいて、誰かに求められる自分には酔っていたい。
恋人の役を演じることでしか愛を感じられないふたり。
それが叶わぬ現実に目を閉じ、耳を塞いで、”わたしたちだけの世界”で生きているフリをする。
これは恋ではない。自己陶酔という病に冒されたふたりが、”恋をしている自分たち”というドラマに酔いしれているだけだ。
この病の厄介なところは、その芝居に気づかず拍手を送る”共犯者”を生み出すことにある。
📻音声で聴きたい方はこちら(Spotify配信中)
この手の人間の特徴
彼らは本気で「恋をしている」と思い込んでいる。
しかし実際には、自分自身にとって都合の良い感情だけを選び取り、責任もリスクも取らず、”恋をしている気分”に浸るだけ。
よく観察すると、次の共通項が見えてくる。
【特徴1】自分の”感情”を最優先
愛している、辛い、会いたいーそういう感情だけを並べ、相手の立場や背景、傷付ける可能性を見ないし、考えない。
【特徴2】バレないことを前提に成立する恋愛
バレるまでは純愛。バレたら”想定外”。
つまり、逃げ道を確保したまま進む関係にしか踏み込めない。
本当に大事なら、誰にも恥じず互いを守ることができる道を選ぶのではないか。
【特徴3】相手が”自分を肯定してくれる存在”であることが重要
愛しているというより、「自分を必要としてくれる相手」との関係性に酔っている。
恋人がほしいのではない。「恋人役をしてくれる人」がほしいだけ。
以上のことから、「恋」ではないことは明らかである。言うなれば、「甘え」と「自己愛」の循環でしかない。
分類と心理構造
”本気ヅラ人間”は、以下に大別することができる。
【タイプA】癒やし依存型ー「私がいないとダメなんだ」と思いたい
このタイプは、誰かの弱さを見つけるとすぐに寄りかかる。
それは支えることが目的なのではなく、”自分の存在価値”を実感するために他ならない。
たとえば、最近不倫騒動が出た永野芽郁さんが演じるのはこのポジション。
既婚者で、責任ある立場の男性に寄り添い、
だと信じ込もうとする。
けれど実際には、自分が”選ばれし存在”であることを証明するステージに過ぎないにもかかわらず、本人はこれを『海よりも深い愛』と思い込んでいる。
【タイプB】承認型逃避人ー甘えながら責任は絶対に取らない男
典型的な中年の逃避型はこれに属する。
田中圭のように、仕事・家庭・立場という外圧の中で「良い人」を演じ疲れている存在は、その捌け口として、自分を肯定してくれる存在を求める。
でも逃げたいだけで、何かを変える覚悟や行動はない。
責任を取らなくて良い場所でだけ「本音」を語るふりをして、
などとこぼし、理解されたい願望ばかりが前に出る。
そのくせ、別れることも、離婚もできず、家庭を壊さない。ずっと”都合の良い場所”で被害者面をしていたいのが本音だろう。
両者に共通するのは、「他人を使い、自分を満たす構造」にいること。
愛ではない。必要とされたがっているだけ。
しかもその必要性すら、自分の脳内だけで作られた幻であることが多い。
対処法:関わってしまったときの心得
問題は、この手の”本気ヅラ人間”が優しい言葉や、弱っているふりをして近づいてきたときだ。
最初は、「こんなに私のことを求めてくれる人、初めて…」といった錯覚すら抱かせるが、ちょっと待って。よく観察してほしい。
彼らが求めているのは”あなた”ではない。”あなたがくれる安心感”だけだ。
とはいえ、関わってしまっては仕方がない。
【対処1】話を聞いてあげない
愚痴、言い訳、家庭の不満ー垂れ流される感情は、彼らの中では恋愛の前戯だ。
聞くことで相手を理解できると思うのは幻想でしかなく、聞けば聞くほど、
という誤解を加速させる。
こう返した途端、彼らの口数は急激に減る。
【対処法2】かわいそうにーを武器にさせない
弱っている人を突き放すには、罪悪感が伴う。
それを知っているからこそ、彼らはしばしば”被害者ヅラ”をする。
だがここで手を差し伸べると、「私はあなたに救われた」と安い台詞ばかりを吐き、ずるずると依存されるだけだ。
大切なのは、「あなたの問題を私が背負う義理はない」と線を引くこと。この線こそ、相手の”演技”を無効化する武器になる。
【対処3】「で、どうするつもり?」
彼らが最も嫌がるのは、”気持ち”ではなく”行動”を求められること。
- 奥さんに話すつもりあるの?
- いつ離婚するの?
- 私たち、これからどうするの?
こうした質問は彼らに、現実を突きつける鏡となる。所詮はごっこ遊び。鏡の前では成立しない。
”本気ヅラ人間”が最も嫌がること
この手の人間は、責められるよりも、”自分が特別ではない”と気づかされることを何より恐れている。
彼らの恋は、「誰にもわからない、ふたりだけの物語」でなければ成立せず、自分たちが”特別な関係”であるという前提が崩れた途端、一瞬で興味を失う、または自己陶酔が崩壊する。
具体的には、以下の通りだ。
【嫌がらせ1】鏡を差し出す
その瞬間、「選ばれし自分」という幻想が崩れる。
なぜならごっこ遊びは、他人と共有された時点で現実に引き戻されるからだ。
【嫌がらせ2】無関心の演出
同情も共感もせず、あくまで他人事で処理すること。これにより彼らが熱望する”特別な共犯関係”は崩壊する。
彼らにとって最もキツいのは、怒られることでも嫌われることでもない。
無視されること。ドラマから引きずり下ろされることだ。
【嫌がらせ3】役割を与えない
相手を”恋人”として扱わない、”支えてくれる人”として持ち上げない。これに尽きる。
ただの知人、ただの同僚、ただの通行人ー彼らが望む役割つきの関係を徹底して与えないこと。
これにより彼らは、何者でもなくなることに堪えられず、静かにフェードアウトしていく。
彼らは「愛されたい」のではなく「愛されている自分に酔いたい」だけ。その虚構を演出するには、あなたの共犯が不可欠である。
しかしながら、あなたがその舞台から降りてしまえば、彼はひとり芝居しかできず、結果的に沈黙する。
おわりに:虚構に浸る人間が最も怖いのは
恋をしているふり、苦しむふり、愛しているふりーふり、ふり、ふり。そのどれもが自分を傷付けない演出だ。
彼らは傷付くことを怖れているのではない。
”大して特別じゃなかった”と気づくことを怖れている。
自分は誰かに必要とされ、どこかで誰かにしか救えない愛がある。
そう思い込んでいる限り、現実に向き合わなくていいのだから。
けれどその演目は、いずれ終わりが来る。誰かが舞台から降りれば、簡単に幕は下りるのだから。
自己陶酔という病
これは、恋ではない。断言する。単に、誰かを愛している”自分”に恋をしている。
あなたの周りに、”本気じゃないのに、本気ヅラする大人”がいるとすれば、どうかその舞台の照明をそっと落としてあげてほしい。
光の当たらぬ場所で、彼らの特別ごっこは続けられないから。