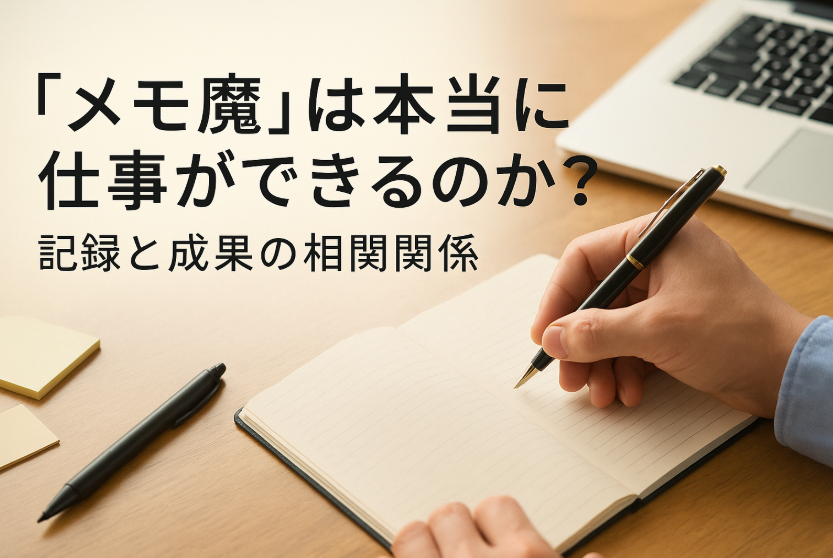当サイトの一部に広告を含みます。
関連投稿
「YouTubeを始めてみようと思ってるんですが、やっぱり大変ですか?」
最近、この手のご相談を承る機会が少しずつ増えてきた。
YouTubeは確かに、発信や収益化の手段として魅力的だ。スマホ1台で始められ、知識や人柄が切り口次第で価値・資産になる。
ただし、「始めること」と「続けること」はまったくの別物だ。
現に、チャンネルを開設して数本で投稿が止まっている人は少なくない。なかには「頑張っていたのに急に更新が途絶えた」ように感じるチャンネルもある。
原因は、才能や根性の問題ではない。YouTubeという環境そのものが、折れやすいのである。
本記事では、なぜ人はYouTubeで折れるのか?
その理由と共通点を、実際に続けている側の視点から分析していく。
第1章:YouTubeが「折れやすい環境」である理由
YouTubeは、始めるだけなら簡単。
スマホで動画を撮影し、アプリで編集(最悪無編集でも◎)、ワンタップで投稿完了。
時間も場所も問わずに発信できる点では、非常に開かれたプラットフォームだ。
だからこそ、誤解されるのだろう。
「誰でもできる」
「やれば伸びる」
「続けるだけで結果が出る」
そのようなイメージが独り歩きしているが実際には、YouTubeの環境そのものが「心を折る構造」になっている。
すべての成果が数値化される
視聴回数、登録者数、高評価、コメント、インプレッション、クリック率など、動画を投稿すると、さまざまな数字が見える。
それ自体はとんでもなく有難いが、同時に「数字で評価され続ける構造」でもある。
自分では手応えのある動画でも、再生数が振るわないこともある。コメント欄に心無い言葉が書き込まれることもあるし、「高評価」が1つもつかぬまま動画が沈むこともある。
このような数字は疲労感となり、確実に蓄積されていく。
比較と沈黙がメンタルを削る
SNS全般に言えることだが、YouTubeは特に「比較」と「沈黙」がえげつない。
他のチャンネルを見ることはできるが、その裏側まで見えるわけではない。とはいえ、
「半年で1万人」
「投稿する度に10万回再生超」
などの投稿・成果ばかりが目に入れば、自分と比較し、無力感に襲われることもある。
さらに厄介なのは、無反応。
再生数ゼロの動画に低評価さえつかない状態は、露骨な批判よりも傷が深まることがある。
第2章:YouTubeで折れる人に共通する5つの特徴
YouTubeへの投稿を辞めた人のすべてが明確に、「辞める」と決めてから行動に移したわけではない。ほとんどの場合、少しずつ離れ、いつの間にか更新が止まっている。
そして、再開のきっかけを掴めぬまま、なかったこととして処理する。
なぜ、そうなってしまうのか。
ここでは、実際に折れやすい人に見られる5つの特徴を紹介する。
① 完璧主義で、全工程を1人で抱え込む
台本作成、撮影、編集、サムネづくり、投稿と告知、コメント対応など、すべて自分で処理しようとした結果、各工程で都度、理想と現実のギャップに苦しむことがある。
これは、はじめから完璧を求める人に多い傾向で、更新頻度が徐々に落ち、最終的には「クオリティを保てないなら出さない方がいい」という思考にすり替わる。
その結果、動画が投稿されなくなり、発信そのものからフェードアウトする。
② 数字に振り回され、承認を求めすぎる
- 再生数を自分の価値と認識する
- 視聴者の反応≒外敵評価に依存する
SNSでありがちなループだが、YouTubeは特に数字が可視化されており、小さな変動も一目瞭然。
これに反応する人は、自ずと感情のアップダウンが激しくなる。
やがて、動画を出すたびに心がすり減り、継続できなくなる。
③ 視聴者に寄せすぎて、自分を見失う
「誰にでも好かれたい」
「批判されたくない」
このような思考だと、発信内容が曖昧になり、全てが無難におさまる。
それ自体は悪いことではないが、無味無臭の動画だと無数になる動画の中で誰にも刺さらず、数字も反応も鈍くなるのは必然である。
その結果、「何を出しても響かない」と自己否定に繋がり、発信意欲が薄れていく。
④ 見切り発車で目的が曖昧
- とりあえず着手するも、何のためにやっているかの点が不明瞭
- 続ける意味を失い、更新が止まる
YouTubeに限ったことではないが、明確なゴール(誰に/何を届け/どこへ導くか)がないまま始めたところで、中盤からタスク地獄に陥るのが関の山。
その結果、日常に押しつぶされてしまう未来が待っている。
⑤ 孤独に戦い、誰にも相談できない
- 周囲にYouTubeをやっている人がいない
- 成果や悩みが共有できず、孤軍状態が続く
特に発信初期にいえることだが、人に相談することさえ怖い状態に陥ることがある。
その点、仲間やサポーター、相談できる相手がいると、ペースを崩したとしても戻ってこられる。
支えがないと、立ち止まったときに再起するのが難しくなる。
次章では、続けられている人との差をその違いを構造面から見ていく。
「折れない仕組み」については、noteでさらに具体的に解説している。
👉【有料note】「YouTubeで折れたくない人へ」続けるための対策とセルフチェックリスト
■第3章:続けられる人は「根性」が違うのではない
ここまでご覧になって、「自分にも当てはまるかも」と感じた人もいるかもしれない。
しかし、該当するからと言ってダメというわけではない。
なぜなら、YouTubeを続けられる人が皆、途中で折れるかもしれない項目にまったく該当せず、特別な才能や精神力を持っているわけではない。
では、淡々と発信を続けている人たちには何があるのだろうか。
彼らに共通するのは、自分と環境に合う仕組みを持っていることだ。
たとえば、
- 数字に関わらず続けられる基準を持っている
- 投稿を続けられる生活リズムがある
- 悩みや迷いを安心して打ち明けられる環境、相手がいる
- 再生数でなく、売上や成約率で評価している
など、折れづらい仕組みを先に作っている。
どんな人でも気持ちが折れそうになることはある。
事実、私自身も「このまま投稿を続けて意味あるのか」と疑った瞬間が何度もあった。
しかし、再起の方法や原因への対処法を知っていれば、いきなりポキッと折れるのでなく、折れても育てられる場所となる。
この点について、noteにて、折れないための構造設計とセルフチェックの方法を具体的に解説していく。
- 自分の急所に気づけるチェック項目
- 心が折れかけても戻れる習慣と仕組み
- 投稿を無理なく続けるテンプレ設計と視点
単なる精神論でなく、継続の技術に興味がある方に読んでいただきたい。
👉【有料note】「YouTubeで折れたくない人へ」続けるための対策とセルフチェックリスト
まとめ
YouTubeは、頑張れば誰でも成功できる。
無責任にそう説いている講師もいるようだが、実際は「継続」そのものが既に、1つのハードルではなかろうか。
それを「気合い」や「根性」で越えられるのなら、誰も苦労はしない。
必要なのは、メンタルが折れづらい構造と、自分を守る仕組みである。
その有無が、途中で消える人と続けられる人を分ける境界線になる。
あなたが今、
「始めたばかりだけど、不安がある」
「やっているのに成果が出なくて焦っている」
「辞めたいほどではないけれど、しんどい」
そんな感覚を抱いているのなら、折れない仕組みを構築する視点を手にしてほしい。
▼具体的な対策とセルフチェックはこちら
👉【有料note】「YouTubeで折れたくない人へ」続けるための対策とセルフチェックリスト
他にも関連コンテンツとして、以下のnoteもあわせてどうぞ。
- ヲタク行政書士®のYouTube裏ばなしマガジン
https://note.com/bokiko_gyosho/m/m0d4fa45dd312 - 副業で月5万を安定化させた3つの導線設計
https://note.com/bokiko_gyosho/n/nabe7709a9fa3 - SNSがんばってるのに伸びない人へ
https://note.com/bokiko_gyosho/n/n5173ce7224d0