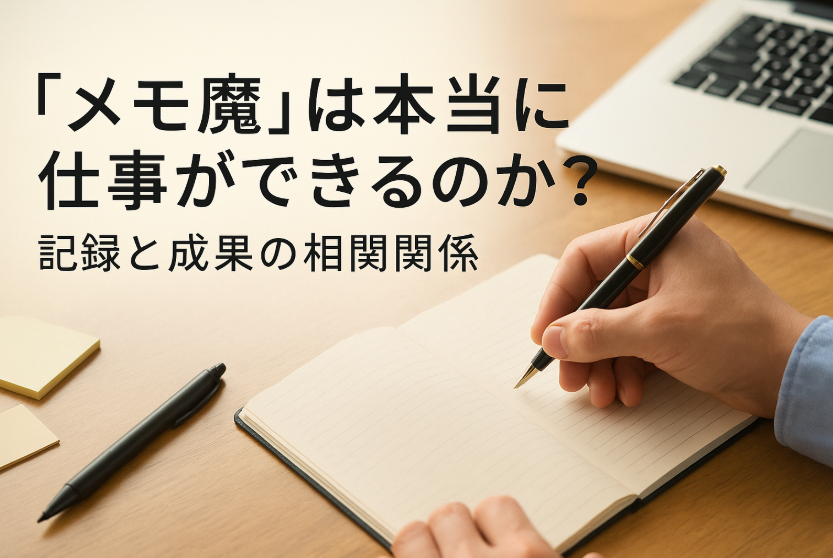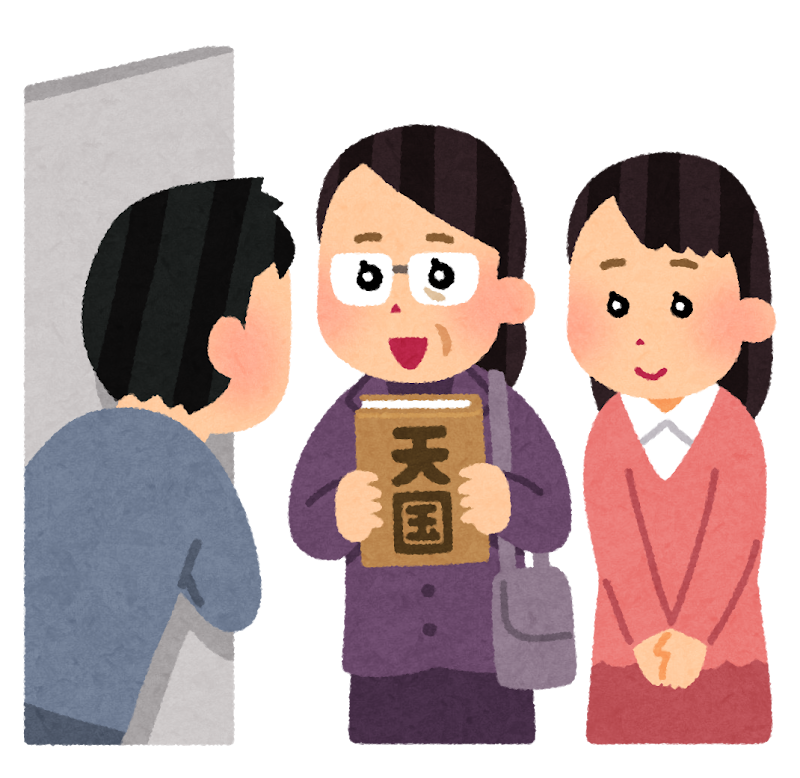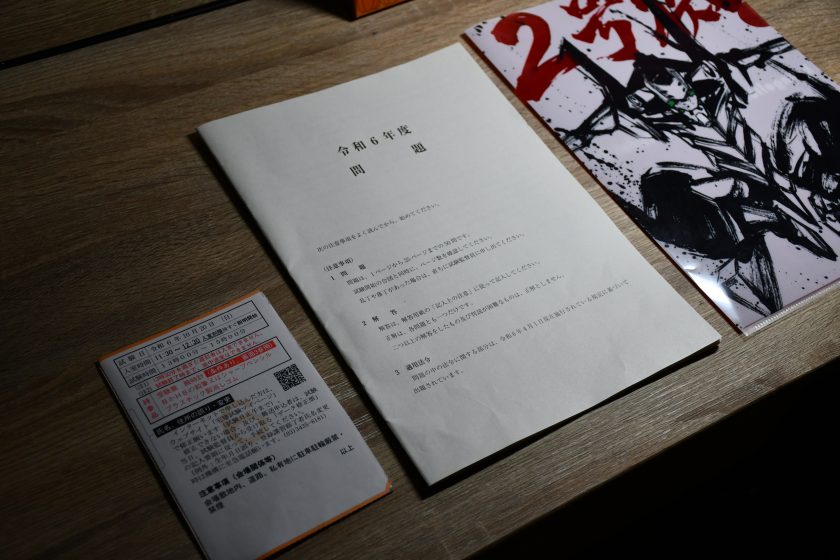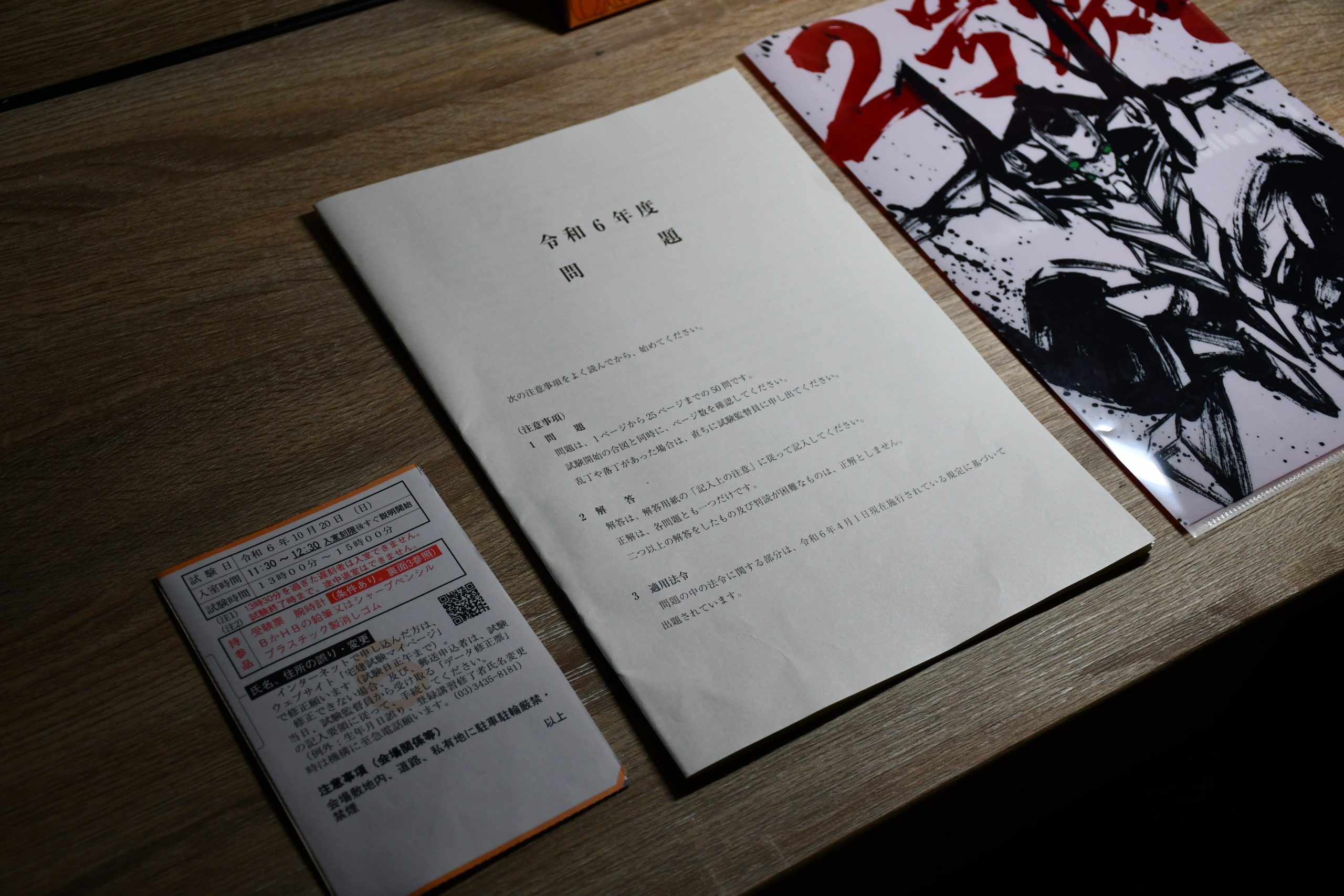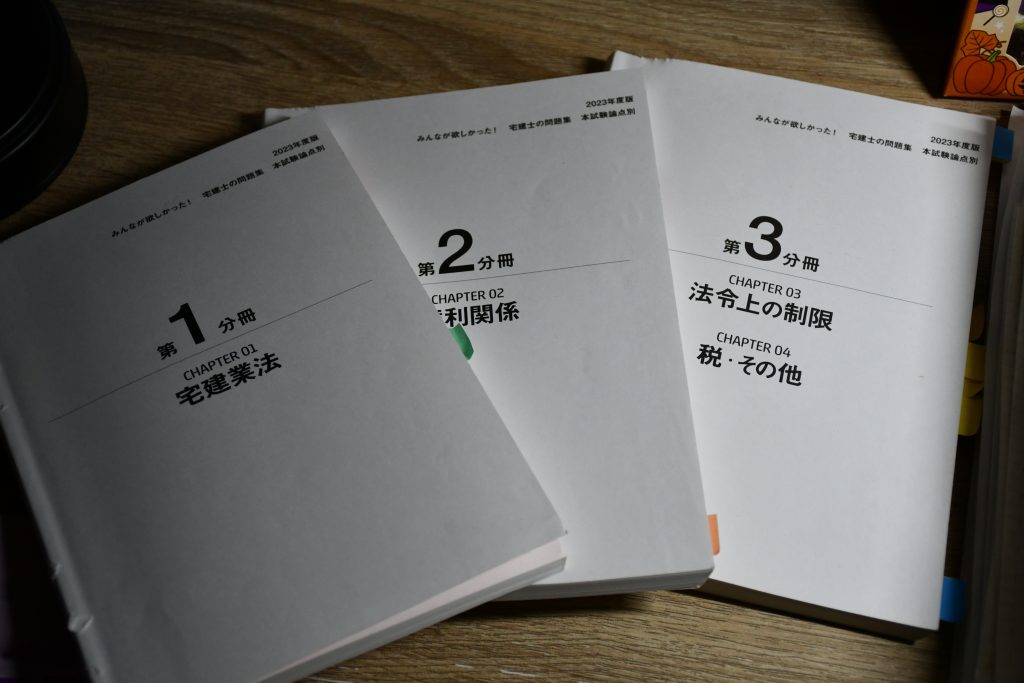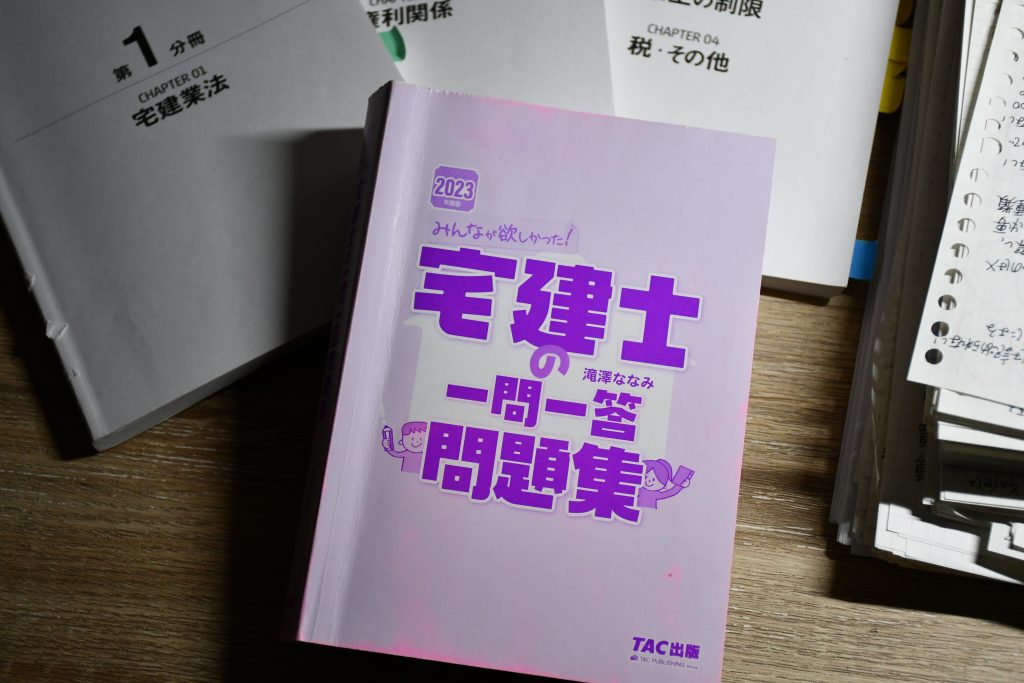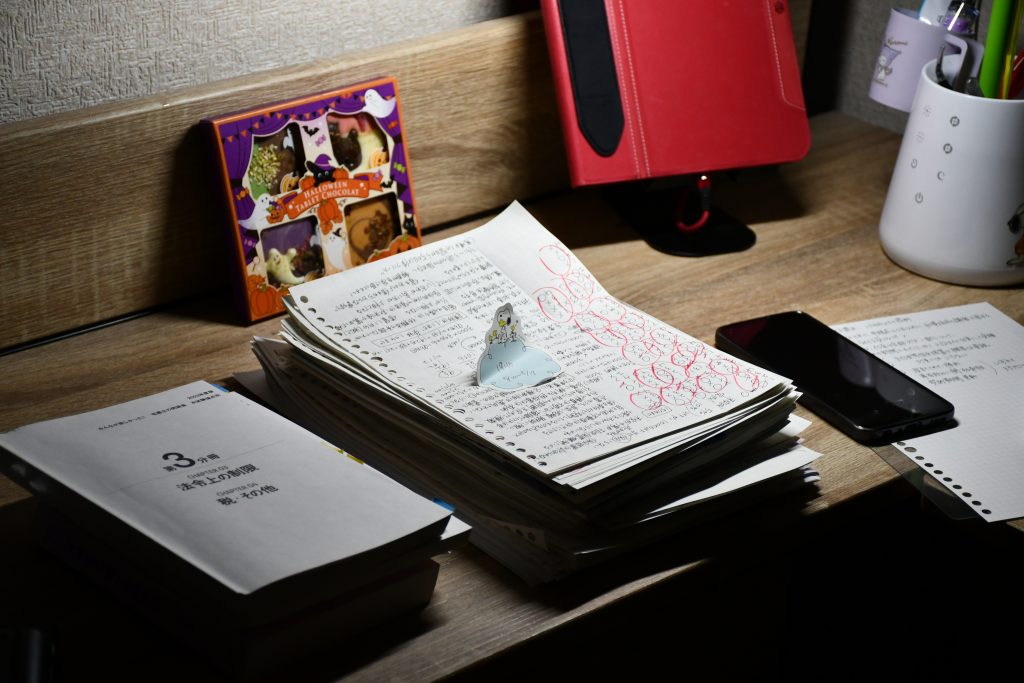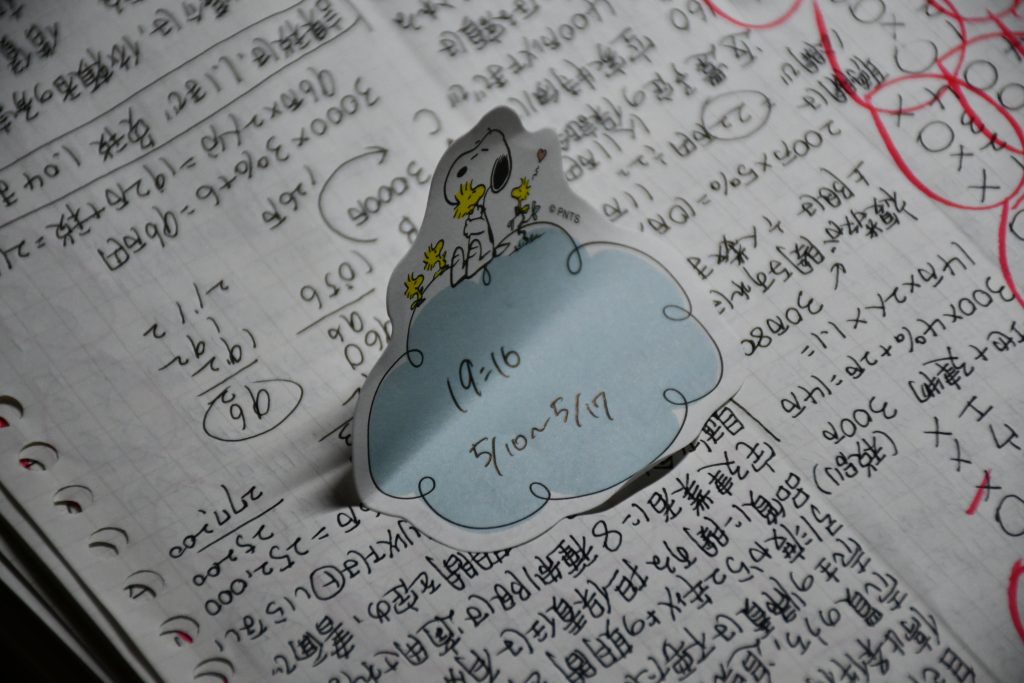当サイトの一部にアフィリエイト広告を含みます。
カルトマーケティングとは
カルトマーケティングとは、カルトに見られる信者がブランドや製品に対して抱く「無条件の信頼」と「絶対的な忠誠心」を意図的に作り上げるマーケティング戦略を指す。この戦略の根本は、顧客がブランドに対し、「教義」や「信念」を持つよう仕向けることだ。
(1)カルトとは
「カルト」とう言葉の取り扱いは難しく、使う人により意味合いは異なる。
ある人は、宗教の発展段階や類型を指し、また別に人は、反社会的な思想集団を指すこともある。
当ページにおけるカルトとは、上記のうち、後者を指す。つまり、特定の教義や指導者を強く信じ、通常の社会的・宗教的枠組みから外れた集団を指すこととする。カルトの特徴として、以下のような要素が挙げられる。
- 狭い範囲の信念体系
- 強いリーダーシップ
- 排他性
- 心理的・感情的支配
- 高い社会的・経済的要求
- 存在する場所や文化
カルトは、信者に対して過度のコントロールを行い、自由な意思決定を奪うことがある。場合により、心理的・経済的な搾取を伴い、信者が集団に対し、完全な依存状態となることもある。
このような背景から「カルト」という言葉は、しばしば否定的な意味で使われ、他の社会的集団と大きく異なる点が問題視されることが多い。
そのため、当ページの目的である「ビジネスへの応用」について説明するのに用いる、カルトのような熱狂的・依存的な状態を生み出し、売上や事業の継続性確保につなげるマーケティングを「カルト的」「カルトマーケティング」と呼ぶ。
カルトとは、宗教に限らず、特定の集団やイデオロギーに対して強い信念や忠誠心を持つ人々を指します。ここでの「カルト」は、宗教に関連しない場合も含む広い概念です。
(2)宗教的信者の心理
宗教的なカルト信者は、指導者や教義に対し、絶対的な忠誠を誓うことが多い。
この点、カルトマーケティングでも、顧客に対し類似の信念を抱かせ、ブランドに対する忠誠心を育て上げる。
結果として、顧客は「ブランド=真実」と信じて疑わず、他者にその信念を広めたくなるのである。
(3)目指すは「信者」
この戦略の最終的な目標は、顧客を「信者」としてブランドと深く結びつけることだ。
顧客がブランドを信じ、それを自らの価値観の一部とすることが、カルトマーケティングの成功のカギを握る。
カルト信者のような忠誠心を生み出す戦略
カルトマーケティングでは、顧客に対し、カルト信者が抱く「帰属意識」や「忠誠心」を植え付けることを目指す。この過程をいくつかの手法に分けて説明したい。
- 信念の共有
- 強い指導者の存在
- 儀式・儀礼の導入
- 排他性の確立
1.信念の共有
信念の共有とは、特定の価値観、信条、目標、または理念を複数の人々が受け入れ、それを基盤にした行動や関係を築くことだ。ここで共有された信念は、個々人のアイデンティティの一部となり、集団に属する意味を強化する。
1-1.信念が共有される仕組み
(1) 明確で強烈なメッセージ
共有される信念は、簡潔かつ強烈なメッセージとして提示される。
一般的に、「世界を変える」「特別な使命を果たす」「私たちだけが真実を知っている」といった内容のものが多い。
例えば、スポーツブランドのNIKEが掲げる「Just Do It」や、Apple社の「Think Different」が掲げるスローガンは、製品以上の価値観を共有する手段だといえる。
ブランドが示す信念に共感し、未来を塑像できることで、当該ブランドを選ぶ理由となり得る。
(2) 排他性の強調
カルトでは、「集団外部の人々では理解できない真実」や「特権的な知識を共有している」という意識が強調される。これにより、メンバーには、「自分たちは選ばれた存在であり、特別な目的を持っている」という意識を持つようになる。
例えば、 カルト宗教における「私たちだけが救われる」「外部は堕落している」という教義がこれに該当する。
(3) 情報や体験の反復
信念を定着させるため、共有する情報・体験を反復継続的に提供し続ける。その方法として、セミナー、ミーティング、儀式、広告など、物理的・心理的な環境による強調が挙げられる。
例えば、 商品発表会やリーダーによる講演会、祈りや瞑想の習慣がこれにあたる。
(4) リーダーシップの存在
カルトにおいて、カリスマ的なリーダーは欠かせない。リーダーは信念の「体現者」として機能し、その信念を信者に伝える役割を担う。
リーダーの言動は信者にとって、信念の正しさを証明し、信者の動機づけとなるのである。
1-2. 信念共有が生む影響
(1) 強い連帯感
カルト信者は、共有する信念を通じ、他の信者との一体感を持つようになる。
例えば、 スポーツチームのファン同士が、共通の試合結果に一喜一憂する一体感などがわかりやすいだろう。
(2) 集団外部との対立
新年の共有は「特別な自分たち」と「外部」の線引きを強め、外部に対する批判的または攻撃的な言動に繋がる場合がある。
例えば、 競合他社の製品や他の宗教に対し、何の情報もないのに「外部」というだけでネガティブな感情を抱く場面などがこれにあたる。
(3) 行動の一貫性
信念が共有されると、信者は集団の価値観に合わせた行動を選択するようになる。
例えば、特定のブランドが出す商品・サービスを使い続ける、グループが推奨する生活様式を取り入れるといった場合が該当する。
(4) 犠牲の正当化
カルト集団の信念を貫くために、信者個人の時間や金銭、自由などを犠牲にすることが正当化されることがある。
例えば、カルト信者による教団に対する多額の寄付行為、安価な競合他社の製品ではなく、高額な特定ブランドの製品を購入し続ける行為などが該当する。
1-3.信念共有のツールと手法
(1) ストーリーテリング
信念を共有するため、多くのカルト集団はストーリーテリングを使う。
ストーリーテリング(Storytelling) とは、物語(ストーリー)を通じ、情報やメッセージを伝える手法を指す。単なるデータや事実を述べるだけでなく、物語として語ることで、受け手に感情的な共感や理解を促し、記憶に残りやすくする効果がある。
例えば、ブランドの創業秘話や、困難を乗り越えた成功体験がこれにあたる。
(2) 儀式やシンボル
多くのカルト宗教では、儀式やロゴ、マークなどを通じ、信念の視覚的・体験的共有を行う。
中には、 特定のポーズや衣装を合わせるものもあるが、商品の包装に統一感を持たせるなどの行動もこれに該当するだろう。
教会や礼拝堂などは仲間意識を高めるうえで重要項であり、ブランドロゴ・独自の儀式などは、仲間同士をつなげ、所属意識を高めるのに必須である。
(3) インフルエンサーの活用
カルト集団は、信念を体現するリーダーやインフルエンサーを通じ、多くの人々に信念を広める。
各企業が広告塔として、スポーツ選手や有名人を起用するのもこれに該当する。起用される側は必ずしも信者とは言えないものの、企業から恩恵を受けられることもあり、契約期間中は信者と同様の行動を見せることもある。
(4) 共通の体験の創出
カルト集団は、信者間でのイベントや体験を共有させ、信念を深めるよう仕向ける。
例えば、ファンミーティングや定期的な集会、カンファレンスがこれにあたる。
中でも、ブランド同士のライバル関係は強い印象を与え、共通の敵を意識したとき、同時に、仲間意識を強く意識することとなる。
1-4. 信念共有時の注意点
カルト集団内部において、信者の熱が高まりすぎると、異論を許さぬ排他的な空気となり、過度な同調圧力により信者が苦しむことがある。
また、集団外部への批判が激化する反射的効果として自分たちを正当化し過ぎるなど、客観性を欠いてしまうリスクが伴うことに注意してほしい。
2.強い指導者の存在
強い指導者の存在は、カルト組織やブランドコミュニティの結束力を高め、フォロワーを引きつける重要な要素である。こうしたリーダーは、単に組織を率いるだけでなく、信念の体現者や象徴として機能する。
2-1.強い指導者の特徴
(1) カリスマ性
強い指導者は、人々を魅了し、従わせる独特の雰囲気や人格的魅力を持っている。
例えば、Apple社のスティーブ・ジョブズ氏は、革新性と情熱的なプレゼンで多くの人を惹きつけた。
(2) 明確なビジョン
指導者は、将来の目標や理想像を具体的かつ明確に描き、それらを熱意をもって語る能力がある。
これの目標は、「地球(環境)を救う」「(革新的なテクノロジーで)世界を変える」など壮大な場合が多い。
(3) 自信と決断力
指導者は、決断を迷いなく下し、自らの信念に対し揺るぎない姿勢を見せ、フォロワーに安心感を抱かせる。
例えば、TeslaやSpaceXのイーロン・マスク氏は、火星移住計画などの大胆な目標を掲げ、実現に向け断固たる行動を取り続けている。
(4) 共感力
指導者は、人々の感情やニーズを理解し、それに応じたメッセージや行動を取る能力がある。
例えば、宗教的カルト集団のリーダーは、孤独や不安を抱える人々の心理を巧みに読み取り、救いや安心感を提供する。
見方によっては、”弱みにつけ込む”とも取れますが、享受する側は「救いの手」と感じる点で一貫性があります。
(5) 物語を作る能力
指導者は、自らの経験やビジョンを感動的なストーリーとして語り、人々を巻き込む力を持っている。
例えば、Virgin Groupのリチャード・ブランソン氏は、自らの冒険的なエピソードを通じ、挑戦の価値を伝えている。
2-2.強い指導者が果たす役割
(1) 信念の象徴
強い指導者ほど、自ら集団の信念や価値観を体現し、フォロワーの行動指針となる。
(2) 団結の促進
信者が抱く指導者への忠誠心は、信者間の結束を強化する。彼らからすると、「共通のリーダー」を持つことは、他の信者との一体感を感じさせる要因の1つなのだ。
これにより、リーダーを中心とした私たち vs. 彼ら(外部)という構図が明確化される。
共通の敵をもつことで、組織内部の熱量は高まるんですね。
(3) 方向性の提示
指導者は、集団が迷ったとき、明確な指示や道筋を示し、行動の統一を図る。
これにより、信者はどのような困難でも、「リーダーについていけば成功できる」と信じ、より依存心を強めていく。
(4) 信頼の醸成
組織内部において、リーダーの選択は常に正しいという信頼感があり、信者の忠誠心を高めている。
しかし、単なるイメージ戦略のみであり、リーダーも失敗するのが現実だろう。
2-3. 強い指導者を支える仕組み
(1) リーダーの「神格化」
カルト集団は往々にして、指導者を通常の人間以上の存在として扱い、尊敬や畏怖の対象にする。
(2) 反対意見の排除
カルト集団は、リーダーの信頼性を維持するため、批判的な意見を排除し、組織内における異論を封じ込めることがある。
(3) シンボルの活用
カルト集団の多くは、リーダーの顔や言葉、行動を象徴化し、視覚的・感情的に訴求する。
(4) 儀式や集会
カルト集団では、リーダーが直接信者に語りかけるイベントや儀式を通じ、影響力を拡大する。
2-4. 強い指導者が与える影響
強い指導者は、信者に対し、ポジティブ・ネガティブ双方の影響を与える。
| ポジティブな影響 | 動機付け | 信者が目標に向かって努力する意欲を高める |
| 革新の推進 | 新しい考え方や行動を取り入れるきっかけを与える |
| 結束力 | 組織やブランドの一体感を強化できる |
| ネガティブな影響 | カリスマ依存 | 集団がリーダーに依存しすぎることで、リーダー不在時に崩壊のリスクを負う |
| 独裁化 | リーダーが自己中心的な決定を下し、組織を悪い方向に導く可能性 |
| 外部との対立 | リーダーを守るために、外部に攻撃的な態度を取る場合がある |
2-5. 強い指導者の成功例と失敗例
強い指導者の成功例・失敗例を下記に挙げる。
| 成功例 | ネルソン・マンデラ
(南アフリカ共和国の政治家) | 人種差別撤廃という明確なビジョンを持ち、南アフリカ国民を団結させた
ビジョンと行動が一致していたため、長期的な信頼を得た |
スティーブ・ジョブズ
(Apple社の共同創業者) | 革新的な製品を通じて「未来を変える」というビジョンを共有し、多くのファンを引きつけた |
| 失敗例 | エリザベス・ホームズ(Theranos創業者) | 技術革新のビジョンを掲げたが、実際には実現不可能な約束をして信頼を失墜 |
| カルト宗教の独裁者 | 組織を外部から隔離し、暴力的な行動を取らせた事例も多い(例: ジム・ジョーンズの人民寺院など) |
3.儀式や儀礼の導入
儀式や儀礼の導入は、個人や集団の行動に秩序を与え、文化や価値観を共有する重要な要素だ。歴史的、現代的にも、さまざまな場面で導入されている。
以下にその目的と方法、メリットについて詳しく説明する。
儀式・儀礼とは
儀式とは、一定の形式に従い行われる宗教的・精神的な行為やイベントを指す。
儀礼とは、社会的な関係を強化する目的で行われる礼儀や形式的な行動を指す。
双方には共通点も多いが、儀式のほうがより象徴的かつ深い意味を持つ点で異なる。
儀式や儀礼を導入する目的
儀式・儀礼の導入目的として、下記が考えられる。
- アイデンティティの確立
- 秩序と安定の提供
- 移行の象徴
- 絆の強化
- 感謝・敬意を表現
1.アイデンティティの確立
アイデンティティとは、個人や集団が持つ自己認識や特徴、他者との関係の中で形成される「自分は何者か」という問いに対する答えだ。心理学、社会学、哲学など様々な分野で議論されることも多い。
儀式・儀礼を導入することにより、信者個人や集団としての価値観、文化の明確化と共有手段としてのアイデンティティは重要な役割を担う。
例えば、企業で行う入社式や新年の決意表明などが挙げられる。
2.秩序と安定を提供
秩序とは、物事が一定の規則や基準に従い整然とした状態にあること、又はそのような状態を維持する仕組みや原則を指す。社会、自然、思想、行動など、さまざまな領域で用いられる概念であり、秩序が存在することで安定と調和が保たれる。
カルト宗教において、儀式・儀礼を繰り返し行うことで安心感や一体感を提供できる。
身近な例では、朝礼や食事の挨拶などが挙げられる。
3.移行の象徴
儀式・儀礼は、個々人のライフステージや役割の変化を示す「節目(移行)」の象徴としても有効だ。
例えば、卒業式や成人式などがこれにあたる。
4.絆の強化
儀式・儀礼という共通体験は、信者同士の関係を深めるのにも役立つ。
例えば、家族で行う慣例行事やチーム発足時の決起集会等が該当するだろう。
5.感謝・敬意を表現
儀式・儀礼を通し、他者や自然に対する感謝の気持ちを形式的に示すこともできる。
例えば、結婚式における誓いの言葉や感謝祭などがこれにあたる。
儀式や儀礼を導入する手順
実際に儀式や儀礼を導入する際の手順は、下記のとおりだ。
- 目的を明確にする
- シンボルを選ぶ
- 一貫した形式を設定
- 参加者の関与を促す
- 繰り返しや記念性の重視
1. 目的を明確にする
なぜおその儀式を行うか、目的を明確化する。
感謝の意を示す、新たな習慣の開始、一体感を生むといった目的が考えられる。
2. シンボルを選ぶ
シンボルには、特定の意味を象徴する「モノ」や「行為」を選ぶ。
たとえば、ろうそくや音楽、特定の言葉や動作が該当する。
3. 一貫した形式を設定
儀式を行う際のプロセスを明確化する。
具体的には、開始の合図→メインの行動→終了の合図と3段階に分けて設定するのが理想的だ。
例として、鐘の音や言葉→誓いの言葉・乾杯→拍手や挨拶などが考えられる。
4. 参加者の関与を促す
カルト集団において、個々人に役割を持たせることは、一体感を生むうえで欠かせない。
儀式中には手をつないだり、拍手を求める、順番に一人一人発言させる場合がこれにあたる。
5. 繰り返しや記念性の重視
儀式・儀礼は、繰り返すことで価値が高まり、開催の都度、記念やシンボルを残すことで次回への期待値を高めることができる。
儀式・儀礼のメリット
儀式・儀礼をおこなうことは、下記のメリットをもたらす。
- 精神的な充実感
- 習慣化の促進
- 社会的なつながり強化
- ストレスの軽減
- 文化の継承 など
4.排他性の確立
カルトマーケティングにおける排他性の確立とは、グループやブランド、文化等の面において、特定の価値観や特徴を共有する人たちを明確化し、その他の人々との差別化を強調する手段・考え方を指す。
これにより、一体感と特別感を生み、コミュニティやブランドロイヤリティの強化・形成をはかることができる。
排他性とは
排他性とは、ある集団やシステムに属する人々が他者との差別化を明確にし、「自分は選ばれた」「自分は特別」といった感覚を促進し、共有することを指す。
排他的であること自体は、決してネガティブな意味をもつわけではなく、ブランドやコミュニティの構築において、戦略的に利用される手法である。
排他性のメリット
排他性を利用することで、下記のメリットが考えられる。
- 結束力の強化
- 特別感の付与
- 高い価値の創出
- 質の向上
排他性を確立する方法
排他性を確立するには、下記の方法が考えられる。
- 条件の設定
- 限定性の強調
- ブランドと価値観の明確化
- 儀式や習慣を取り入れる
- 外部との差異を強調
- 招待制の活用
- ストーリーをつくる
1. 条件を設定する
参加や利用について、特定の条件を課すことで対象者を絞る。
例えば、高額な会費はブランドの価値上昇を助け、資格やスキルの場合は専門性を高める助けとなる。
2. 限定性の強調
カルト集団に関し、限られた人だけがアクセス可能というメッセージを明確にし、強調する。
例えば、数量限定による商品販売や時間限定によるサービス提供などが該当する。
3. ブランドと価値感の明確化
理念や価値観を明確にし、それに共感・賛同する人を中心に集団を形成することで、ブランド力を高めることができる。
例えば、持続可能性を支持する人に対し、環境保護を掲げたブランドをアピールする場合や、アウトドアやミニマリスト向けなど、特定のライフスタイルや趣味に特化したコミュニティ形成も良いだろう。
4. 儀式や習慣を取り入れる
集団の中において、専用のルールや儀式を設けることにより、グループの独自性を強調することができる。
例えば、信者同士の特別な挨拶や合言葉、定期的に実施されるミーティングやイベントなどが挙げられる。
5. 外部との差異を強調
自分たちは特別である理由を明確にし、他者との差異を殊更に際立たせるのも有効だ。
例えば、一般と集団内とを比較した広告や外部から見えない仕組みの構築などがこれにあたる。
6. 招待制を活用する
参加に関し、集団内のメンバーの紹介を条件として導入することで、入会自体の難易度をあげる方法も考えられる。
これにより、入会希望者に「誰でも入れるわけではない」と印象付け、集団の稀少性やステータスの高さを感じさせることができ、他の集団への所属より価値のあるものとして認識させることができるだろう。
また、入会希望者は紹介者を通じた情報を得ることとなり、事前に集団の価値観や雰囲気を理解することができることから、一定の安心感やほどよい緊張感を生むこととなる。
一方、組織から見てもメリットは多い。
新たな参加者を推薦制とすることで、より集団に適合しやすい人材を選ぶことができるほか、紹介者自身が責任を負うことで、適性の低い人を推薦しづらい仕組みとして機能する。
これにより、不適切なメンバーの加入リスクを減らすことができ、入会希望者にかける時間とコスト削減にもつながる。
7. ストーリーをつくる
組織やブランドの背景に特別な物語を持たせ、参加者に感情的なつながりを与える。
最もわかりやすいのは、創設者の特別なビジョンと理念の共有、過去の苦労と成功の強調だろう。
排他性を用いる場面と注意点
実際に排他性を用いる場面と注意点として、下記が考えられる。
排他性を用いる場面
- ブランド戦略
- コミュニティの構築
- マーケティング戦略
注意点
- 過度な排他性は反発を招く可能性がある
- 包括性とのバランスが重要である
- 価値の持続性を保つ必要がある
カルトから学ぶ「説得力」と「影響力」の行使
カルト集団は、そのメンバー・信者に強い影響を与え、行動をコントロールする高度な説得技術を使用する。これらの技術は、ビジネスやリーダーシップ、個人の影響力を高める際に応用することも可能だが、同時に、倫理的な問題を引き起こす可能性もあり、慎重な検討を要する。
下記に、カルトから学ぶ説得力と影響力の行使について詳しく説明したい。
1.感情面への訴求
感情に強く訴えることで、理性より感情的な判断を促進し、行動を引き出すことができる。
具体例として、信念体系の強調により、メンバーに「救世主」や「特別な使命を負う者」という感覚を持たせ、積極的な行動を引き出すことがる。
また、重要性や緊急性の強調により、早急な行動を促進することもあるだろう。
ビジネスや個人に対しては、感情を揺るがすストーリーテリングや情熱的なプレゼンテーションが効果的である。
2.社会的証明(Social Proof)
「他の人が参加するから自分も参加する」という社会的証明の原理を活用する。
活用例として、グループ内で成功した人々の証言やストーリーを強調し、他の信者に「自分にも可能性がある」と信じさせる、集団内における合意形成や信者同士の結束強調などが挙げられる。
ビジネスや個人においては、顧客のレビューや証言、成功事例の活用を通し、他の顧客に対し、強い影響力を発揮することができる。
3.小さな要求(Foot-in-the-door technique)
はじめに小さな要求を受け入れさせ、次第に大きな要求を受け入れさせる方法を活用する。
カルト集団では、最初に少額の寄付を頼み、徐々に高額な寄付をお願いするなどの方法が頻繁に用いられるが、ビジネスにおいては、顧客や部下に対するタスクや要求の受入れが該当する。
4.閉鎖的な環境の作成
出来る限り外部との接触を断ち、信者が組織の価値観や信念体系に固執するよう仕向けるのもカルト集団における常套手段といえる。
具体的には、信者と外界との接触を最大限制限し、当該信者が組織の内輪での価値観に強く依存するよう「外部の情報は信ずるべきでない」と教え、内部の情報やリーダーの指導のみ受け入れるようにする手法が考えられる。
ビジネスにおいては、企業文化の強化や社内の価値観、目標への共感力を深める目的を持ち、ちーーむビルディング活動の導入などが考えられる。
5.カリスマ的リーダーシップ
リーダーは信者に対し、絶対的な信頼を築くことにより、無条件に従わせる力を持つことがある。
ビジネスにおいて、強いリーダーシップの発揮と明確なビジョンの伝達によるチームの結束力向上と、目標達成までの貢献度向上が考えられる。
6.閉じ込め効果(Cognitive Dissonance)
信者が選択する行動を正当化するため、その行動を繰り返すよう仕向ける手法がある。
わかりやすい例を挙げると、テロリストですら正義を自認しているが、元を辿れば、個人的な悩みや義憤であったはずだ。
こうした事象に対し、答えを求めているところに、カルト宗教はいとも簡単に「敵」を持ち出し、「あなたがつらい思いをしているのは○○のせいである」という被害者意識を植え付ける。
これにより、復讐は正当化され、社会を破壊する目的など微塵も持たず、自らを正義だと信じて疑わぬままにテロ行為に及ぶのだ。
ビジネスにおいて、顧客が1度購入した製品に対し、その選択を正当化し続けられるよう仕掛けを行わなければならない。
外界との対立をあおり、攻撃を正当化するストーリーテリングは避けましょう。
実際のカルトマーケティング事例
カルトマーケティングでは、特定のターゲットを操作し、信念体系や消費行動を強く誘導する手法をとるが、当該手法が過度に利用されると倫理的な問題が生じ、犯罪や社会問題への発展が懸念される。
以下に、日本国内で起こったカルト的マーケティングに関する事例を挙げるが、その多くは推奨できない行為であり、批判や問題を引き起こしている。そのため、当ページでは、あくまで事例として取り上げ、悪用を避ける警鐘として参考にしてほしい。
1. オウム真理教と「アセンション」商品
概要
オウム真理教は、1990年代に信者を集めるために過激な教義を展開し、マーケティング活動を通じ、信者を引き込んだ。特に、「アセンション」(覚醒)という概念を販売促進に利用し、高額なセミナーや商品(例えば、特定の書籍や「特別な薬」)を購入させていた。
カルト的要素
当該事案におけるカルト的要素として、下記が挙げられる。
- 精神的な覚醒を促す商品・サービスの購入を促す
- 「真理を知る者」として、商品を通じて選ばれた顧客の証明を与える
問題点
オウム真理教は、1995年に地下鉄サリン事件を起こすなど過激な行動に出た。信者が商品やサービスに多額の金額を費やした結果、破産や家庭崩壊を招いたケースもある。
このことから、カルト的宗教は信者を経済的・精神的に追い込む可能性を含み、カルトマーケティングによる深刻な犯罪や社会問題への接続リスクがあることから、絶対に推奨できるものではない。
2. 自己啓発セミナーと「成功の法則」販売
概要
特定の自己啓発セミナーやビジネスセミナーは、参加者に強烈な「成功信仰」を植え付け、参加費用や書籍、DVD、身に着けられる衣服やステッカー、さらには「メンター契約」など高額商品の購入に繋がることもある。
ここで販売される商品に実用的な価値はほとんどなく、購入者が心酔する組織との一体感を実感でき、かつ、周囲に対し、当該組織への所属を示すことができるという価値をもつ。
カルト的要素
カルトマーケティングが提供する製品には、存在しない機能を謳い、違法販売や悪質商法といえるものも含まれる。
例えば、客観的な証拠はないにもかかわらず、「○○に効く」や「○○に必須」とし、最悪の結末を示して脅す行為は悪質商法だといえる。また、参加者が外部から批判され、組織内の信念に依存するよう仕向けるのも悪質だといえるだろう。
問題点
消費者が安心や平穏を求めて少額、かつ、自発的に買い求める場合と比べ、真剣に脅され、高額商品を購入するよう仕向けられる場合では、社会にいおける需要度が異なる。さらに、深刻な場合には健康被害を及ぼすリスクも負うことから、販売側にも相応の倫理観が求められる。
3. 宗教法人を利用した不透明な商法(例:某宗教団体)
概要
宗教法人として認可された団体が販売する商品・サービスに関し、明言せずとも実質的な高額寄付を強いるケースがある。信者に対し、「貢献すべき」との感覚を抱かせ、商品購入や寄付を行わせる手法だ。
ある団体において、特定のアイテム(例えば、神聖視された物品や書籍)を購入しなければ「精神的に救われない」といったメッセージが伝えられたこともある。
カルト的要素
当事案におけるカルト的要素は、下記の通りだ。
- 精神的な成長と救済に購入や寄付が不可欠であると強調
- 信者は自己犠牲的な支出を続け、精神的安心を得ようとする
問題点
こうした商法では、金銭的な搾取や過剰な献金の促進により、信者を経済的に困窮させることがある。また、信者を組織内に閉じ込め、外界との接触を制限することで独占的支配を行うこともある。
宗教法人や目に見えないものを販売するのに際し、不透明かつ過剰な金銭要求を伴う場合、それは重大な倫理的問題を引き起こす可能性があります。特に、過剰な献金を求める商法は社会的に問題視されています。
【まとめ】カルト信者のような忠誠心をマーケティングに活かす方法
カルトマーケティングの本質は、顧客がブランドに対し、カルト宗教の信者のように、無条件で忠誠を誓うよう仕向けるものだ。カルト宗教の信者が信仰する教義のように、顧客がブランドの「理念」や「価値」に共感・納得し、自分をブランドの一部と認識することは成功の可能性を高めるだろう。
- 外界との違いを強調する
- 明確な目的・ビジョンを示す
- アイデンティティや自己実現をアピールする
- 共通の敵をつくる
- 儀式・儀礼を取り入れる
- 強い指導者を確立する
これらの要素を取り入れることで、あなたのブランドも「信者」のような忠実なフォロワーを作り、マーケティングを成功に導くことができるだろう。