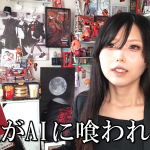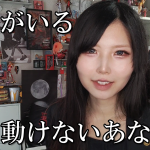当サイトの一部に広告を含みます。

当ページでは、キッチンカー営業に必要な許可と手続き、注意点を解説します。
Contents
著者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
キッチンカー営業開始までの流れ
キッチンカー営業を開始するには、次の流れに沿った手続きが必要です。
- 事業計画を立てる
- 資金を集める
- 保健所への事前相談
- 書類の作成・提出
- 施設検査
- 許可証交付
- 営業開始
1.事業計画を立てる
キッチンカー営業を始めるには、事業計画を作成する必要があります。
事業計画では、事業の理想像と目的を定め、市場分析や財務計画、リスク管理計画を定めていきます。
計画段階で予見できるリスクに備えるのはもちろん、まだ見えていないリスクを炙り出すきっかけになるだけでなく、金融機関から融資を受ける際にも役立ちます。
開業時期と計画から逆算し、必要資金と日数をざっくり算定しましょう。
2.資金を集める
事業計画で算出した創業・運転にかかる資金を集めます。
開業にかかる費用を「初期費用」、軌道に乗るまでの間にかかる費用を「運転資金」と考え、妥協せず集めることをお勧めします。
自己資金での出発が厳しいと感じる場合、融資も検討しましょう。
ただし、融資審査では事業計画と自己資金率から返済可能性を見られますので、地に足の着いた計画を策定しておく必要があります。
3.保健所への事前相談
資金が集まったら、所轄の保健所に事前相談を行います。
キッチンカー営業は、営業予定地を管轄する保健所で「営業許可」を取得する必要がありますが、自治体ごとに許可要件に差異があり、直接確認するほかありません。
事前相談では、一般的に次のことを相談します。
- 販売したいメニュー
- 販売エリア
- 開業時期
詳細まで決める必要はないものの、具体的であるほど進捗もスムーズです。
例えば、クレープ等のスイーツ類の場合、車内で調理したものを販売するのか、あらかじめ調理・梱包した状態で売るのかといった具合です。
エリアは都道府県単位、開業時期は±半年程度まで絞れていれば、相談に応じてもらえるでしょう。
事前相談を怠るということは、キッチンカーとして備えるべき要件を備えられませんので、許可を取得できる可能性が低くなる上に、車両整備後、新たな整備が必要となることもあります。
4.書類の作成・提出
相談時に示される書類等を、作成して提出します。下記は、神奈川県の例です。
- 営業許可申請書
- 施設の図面
- 事業計画書(業務計画書)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
- 法人番号または登記事項証明書(法人の場合)
- 水質検査成績所の写し(井戸水等を使用している場合のみで、採水後6か月以内のもの)
- 製造方法の概要(製造業の場合)
- 申請手数料
この他、「車検証のコピー」「検便検査成績書」を求められる事もあります。
自治体により求められる書類は異なりますので、必ず確認してください。
5.施設検査
保健所の事前相談で確認した要件を基に、キッチンカーを購入します。
購入について、次の入手方法が考えられます。
- 新車を購入
- 中古車を購入
- レンタル
- リース契約を結び、最終的には買い取る
整備にかかる工費等が補助金・助成金の対象となる場合もありますので、申請を検討される場合、着工前に申請要件を確認しておきましょう。
事前相談で指導された内装・設備工事が完了次第、こちらから保健所に連絡し、検査を受けます。
指示内容を遵守していれば、まず不合格になる事はありませんので、リラックスして臨みましょう。
-
- 運転席と調理場が明確に区分されているか
-
- 給水・排水タンクの設置・容量
-
- シンクの数
-
- 水道(蛇口)設備
-
- 収納ケース、棚の設置数
-
- 石鹸等の衛生用品の管理
-
- 換気設備
-
- 冷蔵庫・冷凍庫の設置
-
- ゴミ箱の設置
工事完了後に補正指導を受けた場合、補正後に改めて申請することはできますが、時間・費用ともに大幅なロスは避けられません。
あらかじめ予定している開業時期・資金計画に沿うよう、事前相談はしっかりと行いましょう。
問題なければ許可申請へと進みますが、指摘事項がある場合、修正し、改めて申請を行います。
自治体によりますが、指導に従っていれば問題なく許可をもらえるので、指摘された際は誠実に対応しましょう。
6.許可証交付
申請内容、施設検査時、特に問題がなければ、2~3週間ほどで「営業許可証」が交付されます。
交付された営業許可証は、キッチンカーでの営業時、必ず携帯しなくてはなりません。
また、営業に関する手続きでも求められる場合が多いため、汚損・紛失に注意し、営業中は見やすい箇所に掲示しましょう。
営業許可とは
キッチンカー営業のために取得する「営業許可」は、飲食業を行うための必要条件を満たしていることを証明するものです。
保健所は、公衆の健康を守るため、飲食店での食品の製造や提供において、感染症拡大を防ぐための措置がとられているか、適切な衛生基準を守っているかを確認する機関です。
営業許可が下りると「営業許可証」が交付され、キッチンカーでの営業時には店舗(車内)に掲示する義務があります。
その他さまざまな手続きで必要となるため、営業許可証は大切に扱ってくださいね。
許可の申請先
営業許可の申請先は、営業販売を行う地域を管轄する保健所です。
令和3(2021)年6月以前まで異なっていた各都道府県の保健所ごとに定められる許可要件は、令和5(2023)年現在は統一されました。
しかし、統一後も一定の「ローカルルール」を定めている自治体は存在します。
これは決して違法ではなく、地域ごとに設定される「条例」、その土地に昔からある「慣習」等に対応するための微調整と考え、これから営業する地域へのご挨拶として遵守しましょう。
令和3年より前に取得した人は注意!
令和5(2023)年5月以降、営業許可を新たに取得する人には関係ありませんが、令和3(2021)年5月以前に取得した人は、更新時期を確認しましょう。
現在は、1つの営業許可で 同じ県内すべてのエリアで営業ができるようになっていますので、許可を取得した土地の保健所へ、確認してください。
飲食店に係る営業許可の種類
食品に係る営業許可の申請様式は、全部で32種類です。
このうち、キッチンカー営業は「飲食店営業」に一本化されています。
- 営業許可は、営業する地域の保健所にて取得
- キッチンカー営業に必要なのは「飲食店営業」
- 営業許可の有効期限は5年間
営業開始後に必要な手続
営業開始後、一定の事由が生じた場合には次の手続きが必要です。
変更届
既に受けている営業許可申請書の記載事項のうち、次のものに変更が生じると「届出」が必要です。
- 営業者の住所、氏名
- 営業所の名称
- 営業設備
- 食品衛生者等
神奈川県では、変更が生じた場合は速やかに届出を行うよう指導されます。
「営業許可申請書(変更)」に「営業許可証」「変更事項を確認できる書類」を添付して提出しましょう。
キッチンカー営業に必要な許可・手続 まとめ
当ページでは、キッチンカー営業に必要な許可と手続き、注意点を解説しました。