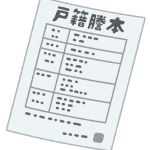当サイトの一部に広告を含みます。

当ページでは、令和5年(2023年)10月1日から導入されるインボイス制度の概要、登録の要否を検討する際のポイントを解説します。
Contents
筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の方式の1つで、正式名称を「適格請求書保存方式」といいます。
インボイス制度の導入後、一定要件を満たす適格請求書を売り手が発行し、買い手側と双方が保存することを条件に消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。
端的に言えば、適格請求書を売り手・買い手のいずれかが保存していない場合、仕入税額控除が受けられなくなる制度です。
注意したいのは、適格請求書は誰でも発行できるわけではなく、「登録事業者」にのみ発行が許される点です。
インボイス制度の導入で変わること
インボイス制度の導入に伴い、下記の変更が必要です。
- 仕入税額控除の適用要件
- 区分記載請求書から適格請求書へ
仕入税額控除の適用要件
仕入税額控除とは、売上時の受取消費税額から仕入時の支払消費税額を差し引いて納税する仕組みをいいます。
インボイス制度の導入後は、適格請求書のある取引のみが控除対象となるため、仕入れ先が適格請求書発行事業者でなければ、買い手は仕入税額控除が受けられず、売上時に受け取る消費税をそのまま支払う事になります。
区分記載請求書から適格請求書へ
旧法の下、発行されている請求書は2つの税率「10%」「8%」に区分された「区分記載請求書」と呼ばれるものです。
インボイス制度の導入後は、適格請求書として定められた下記の項目を記載する必要があります。
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業所の氏名または名称
適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者」のみで、登録を受けていない事業者が発行した場合または紛らわしい書類を発行した場合、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が課される可能性があります。
罰金以上の刑に処された者は、インボイス発行事業者の登録取消し、申請時の登録拒否の可能性があります。
違反行為は経営者にとって何の利益もないので、事前確認をしっかりと行いましょう。
インボイスへの登録を検討する場合
インボイス制度の導入に際し、適格請求書発行事業者として登録するかどうか悩まれるかと思います。
「売り手」「買い手」に分け、検討すべき項目を解説します。
売り手が検討すべきこと
インボイス制度の導入前において、課税事業者となっている個人事業者・法人は、インボイス制度による消費税の納税額・計算方法等に変化はありません。
インボイス制度導入までに、適格請求書発行のための事業者登録を行いましょう。
いっぽう、免税事業者の場合、取引先が課税・免税のいずれかを確認し、課税事業者多数の場合には、下記を検討しましょう。
- 適格請求書の発行、保存
- インボイス制度に対応する帳簿の作成、保存
買い手が検討すべきこと
買い手が注意すべき点は、仕入れ先が課税・免税のいずれに該当するかです。
仕入の際に支払う消費税について、インボイス制度の導入後、取引先が適格請求書を発行してくれなくては控除対象外となります。
これを踏まえ、下記の点を検討します。
- 取引額の見直し
- 取引先の変更
繰り返しになりますが、適格請求書を発行できるのは登録事業者のみです。
取引先が免税事業者の場合には、適格請求書を発行することができず、仕入税額控除が受けられません。
相手が登録事業者の場合と比較すると、少なからず損をします。
取引先が課税事業者の場合、下記を検討しましょう。
- 受け取った適格請求書の保存方法
- 適格請求書、その他の請求書の保管方法
免税事業者が登録する場合の負担軽減対策
インボイス制度に対応する目的で課税事業者になる場合、下記の経過措置・支援措置の対象となります。
- 消費税納税額の2割特例
- 適格請求書発行事業者の登録申請期限の延長
- 小規模事業への持続か補助金上乗せ
消費税納税額の2割特例
政府では、一定期間は消費税納税額を「売上税額の2割まで軽減」する措置をとります。
- 消費税額=売上にかかる消費税額×20%
- 対象:適格請求書発行事業者となった免税事業者
- 期間:令和5年(2023年)10月から令和8年(2026年)の申告分まで
インボイス制度への対応を前提に課税事業者になった場合、確定申告の際、「本則課税」「簡易課税」「2割特例」から納税方法を選択できます。
2割特例を選ぶ場合、他の方法を選択すると選べなくなることに注意しましょう。
適格請求書発行事業者の登録申請期限を延長
インボイス制度の発表当初、導入開始の令和5年(2023年)年10月1日から適格請求書発行事業者になることを希望する事業者は、令和5年(2023年)3月31日までに登録申請をしなければなりませんでした。
しかし、中小企業からの声により法改正が行われ、令和5年(2023年)9月30日まで申請期限が延長されています。
インボイス制度が導入される前日までになったんですね。
小規模事業者への持続化補助金上乗せ
小規模事業者持続化補助金への申請を検討している事業者のうち、適格請求書発行事業者として登録した申請者は、補助金上限額に50万円が上乗せされます。
ただし、補助率の「原則2/3以内」に変更はありませんので、申請前に最新の情報を確認しましょう。
インボイス制度の概要、登録の要否を検討する際のポイントまとめ
本記事では、インボイス制度の概要、登録事業者への登録を検討する際のポイントを解説しました。