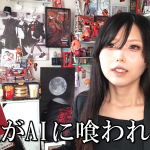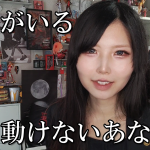当サイトの一部に広告を含みます。

当ページでは、社会保険における「被扶養者」に該当する人と、必要な手続を解説します。
Contents
筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
社会保険とは
社会保険とは、国や地方自治体等が提供する社会福祉サービスの1つで、下記に分類されます。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
「社会保険」という名の保険があるのではなく、上記5つをまとめて「社会保険」と呼びます。
社会保険の目的
社会保険は種類ごとに対象が異なるものの、社会に潜在するリスクに対し、被保険者やその家族が安定した生活を送れるよう支援し、社会全体の福祉を促進することを共通目的としています。
社会保険の被扶養者
社会保険の被扶養者とは、一定の要件を満たす被保険者の家族や近親者を指します。
被扶養者となることで、被保険者の健康保険に加入できるだけでなく、厚生年金や雇用保険等の受給ができる場合があり、被保険者側にとっても、医療費等の負担を軽減することができます。
被扶養者の要件
社会保険の被扶養者として認められるのは、次の要件を満たす人です。
- 被扶養者の対象範囲にいること
- 被扶養者の収入額が一定額未満であること
1.被扶養者の対象範囲にいること
社会保険の被扶養者として認められるのは、原則、下記に該当する人です。
- 配偶者(事実婚含む)
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
上記のほか、叔父叔母等の3親等内親族、内縁者の父母や子も認められますが、この場合、被保険者と同居している等の要件を満たす必要があります。
75歳以上の父母または祖父母は、後期高齢者医療制度の適用対象となるため、社会保険の不要対象外となります。
2.被扶養者の収入額が一定額未満であること
社会保険の被扶養者と認められるには、原則、年間の収入額が130万円未満であることが求められます。
ただし、60歳以上または障害がある場合、年間収入額180万円未満まで認められます。
- 同居の場合:収入が被保険者の半分未満
- 別居の場合:収入が被保険者の仕送り額未満
被扶養者となるために必要な手続
社会保険の被扶養者となるためには、被扶養者として認められるための要件を満たした日から5日以内に、下記の手続を行う必要があります。
必要な書類
被保険者は事業者を経由し、下記の書類を日本年金機構に提出します。
- 被扶養者(異動)届 第3号被保険者関係届
- 被保険者との続柄を証明する書類(戸籍謄本、住民票の写し等)
- 収入がわかる書類
- 仕送りの事実、金額がわかる書類
「3.収入がわかる書類」には、(1)事業主の証明、(2)退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し、(3)年金受取額がわかる改定通知書等の写し、(4)直近の確定申告書の写し、(5)課税(非課税)証明書等のうち、事例に応じたものを提出する必要があります。
「4.仕送りの事実、金額がわかる書類」は、送金者名、受取人名、金額がわかる書類を添付する必要があります。
被扶養者となった後の注意点
下記に該当する場合、被扶養者として認められないため、削除の届出を行う必要があります。
- 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- 被扶養者の年間収入が130万円以上見込まれるとき
- 同居の場合、被扶養者の収入が被保険者の収入の半分以上になったとき
- 別居の場合、被扶養者の収入が被保険者の仕送り額を超えたとき
- 健康保険、船員保険の被保険者または共済組合の組合員になったとき
- 婚姻等により、他の被保険者に扶養される場合または離婚したとき
- 離縁、死亡、同居が要件の場合は別居したとき
- 日本国内に住所を有しなくなったとき
社会保険の「被扶養者」に該当する人と必要な手続まとめ
当ページでは、社会保険上の「被扶養者」に該当する人、被扶養者となるために必要な手続を解説しました。