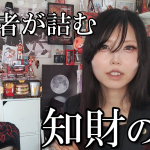当サイトの一部に広告を含みます。

当ページでは、農地法第3条許可申請において満たすべき要件、申請時の注意点を解説します。
Contents
筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
農地法第3条許可とは
農地法とは、農地の適正な利用・管理を促進する目的で定められた法律を指します。
この法律の第3条に、農地の所有権を他人に移転、設定する場合、農業委員会の許可を必要とする規定が定められています。
このことから「3条許可」と呼ばれることもあります。
出典:e-Gov法令検索「農地法」より
3条許可の対象
農地法第3条許可の対象となるのは、下記の取引です。
- 売買
- 贈与
- 賃貸借
- 共有物の分割
- 譲渡担保や買い戻しなど
3条許可取得が不要な取引
下記に該当する事例による取得時は、農地委員会への「届出」は必要ですが、亜農地法第3条許可は不要です。
- 相続
- 時効
- 法人等の合併
- 包括遺贈等
許可取得の要件
農地法第3条許可の取得を検討する場合、下記の要件を満たす必要があります。
- 全部効率利用要件
- 農作業常時従事要件
- 下限面積要件
- 地域との調和要件
1.全部効率利用要件
全部効率利用要件とは、所有する農地の全てを効率良く利用し、耕作を行うことをいいます。
耕作に必要な労働力、設備、技術の適正性を求められます。
農地の一部でも荒れてしまえばアウトになる点に注意しましょう。
2.農作業常時従事要件
農作業常時従事要件とは、所有する農地が常に稼働していることをいいます。
要するに、農地が「遊んでいる状態」を避けることが要件です。
常時とは、年間日数150日以上をいいますが、実質従事日数が150日未満の場合でも、農作業を行う必要性が認められる限りは「常時従事」として扱われます。
従事者は申請者(所有者)本人に限らず、申請者の親族でも認められるため、複数人で協力してクリアすることも可能です。
3.下限面積要件
農地法第3条許可における下限面積とは、農地取得者が耕作する農地の面積が5,000㎡(≒50a)以上であることを指します。
取得者が所有する農地がある場合、双方を合計して構いません。
自治体により下限値は異なるため、事前に確認しましょう。
4.地域との調和要件
地域との調和とは、近隣の農地所有者と良好な関係を保つことをいいます。
一般的に、農地の所在地は近隣も農地である場合が多く、農薬の散布、水利調整等、少なからず協力を求められる場面もあります。
このような場合、取得者のみが非協力的であると他の耕作者が困るため、最低限度の協力体制は示す必要があります。
農地法第3条許可申請の流れ
農地法第3条許可申請は、下記の流れで行います。
- 農業委員会へ事前相談
- 申請書作成、添付書類の収集
- 申請
- 農地転用許可証交付
1.農業委員会へ事前相談
農地の所在地を管轄する市区町村役所にある農業委員会に、事前相談を行います。
この際、農地転用の可否、必要書類等を確認しましょう。
2.申請書作成、添付書類の収集
事前相談で教示された必要書類を作成、添付書類を取得します。
申請時に必要な書類は各自治体により異なりますが、下記に一例を挙げます。
- 農地転用許可申請所
- 公図等の図面
- 登記事項証明書
- 譲渡人、譲受人の住民票など
申請は、譲渡人と譲受人が協力して行う必要がありますが、委任することも可能です。
3.申請
全ての書類が整ったら、農業委員会に申請します。
ほとんどの農業委員会は、申請後、実地調査を行った後、月に1度審査会議を行います。
ここで問題がなければ、農地転用許可証が交付されます。
4.農地転用許可証交付
申請先の農業委員会より、許可証交付の連絡が入ります。
原則、窓口での受取のみですが、どうしても受取に行けない事情がある場合、農業委員会までご相談ください。
農地法第3条許可申請の要件、注意点 まとめ
当ページでは、農地法第3条許可申請の要件と申請時の注意点を解説しました。