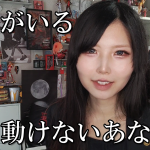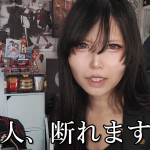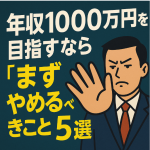当サイトの一部に広告を含みます。

当ページでは、法務局で実施している自筆証書遺言書保管制度の概要、申請から死亡後の手続を解説します。
Contents
筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言書保管制度とは、法務局において、遺言書を原本として預け、画像データと併せて長期間管理してもらう制度です。
原本は、遺言者の死亡後50年間、画像データは150年間保管されます。
保管を申請できるのは自筆証書遺言に限られ、本制度を利用する場合、遺言者の死後に必要な「検認手続」が不要です。
検認手続とは
検認手続とは、遺言者の死後、発見した遺言書を家庭裁判所において開封、内容の確認を行う手続です。
自筆証書遺言書保管制度のメリット
自筆証書遺言書保管制度のメリットは、下記の通りです。
- 紛失、改ざんのおそれがない
- 法務局職員が方式を確認してくれる
- 相続開始後の検認手続不要、相続人等へ通知
1.紛失、改ざんのおそれがない
自筆証書遺言書を作成した場合、一般的な保管場所は自宅です。
自宅で保管する際、最も気を付けたいのは紛失ですが、複数の相続人がいる場合、特定の相続人による改ざん、破棄、隠匿のおそれがあります。
自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、法務局で厳重に保管してもらうことができ、紛失や改ざん等のおそれがありません。
2.法務局職員が方式を確認してくれる
遺言者1人で作成した場合、一定の割合で無効となります。
これは、民法上に定められる遺言書に備えるべき内容が欠けていることが原因で、遺言者の苦労は水の泡です。
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、申請書そのものが民法に定められる遺言書の形式に沿った内容であり、申請時に法務局職員が不備の有無を確認してくれるので、無効になるリスク低減に繋がります。
とはいえ、遺言書の有効性まで確認してくれるわけではないため、正しい知識をもって、遺言書を作成しましょう。
3.相続開始後の検認手続不要、相続人等へ通知
遺言者の死後、遺言書が見つからない場合、相続人全員により遺産分割協議へと進みます。
遺言書があれば省略できる手続も多いため、せっかく用意したのに無駄な手間と時間を割くことになるうえ、後から遺言書が出て来ると、1からやり直し…ということもあります。
この点、自筆証書遺言書保管制度を利用すると、法務局に遺言書が保管されていることを、法務局から相続人等に通知してくれるため、手間や時間を大幅にカットすることができます。
自筆証書遺言書保管申請の流れ
自筆証書遺言書の保管申請手続は、下記の流れで進めます。
- 遺言書を作成
- 申請書を作成
- 添付書類等を準備
- 遺言保管所(法務局)に予約
- 法務局にて保管申請
- 保管証の受取
1.遺言書を作成
1-1.遺言書の要件
民法上の要件は下記の通りです。
- 遺言書全文の自書
- の作成日付の自書
- 遺言者の署名・押印
1-2.財産目録の要件
財産目録を添付する場合、下記を満たす必要があります。
- コピー等による財産目録を添付する場合、すべてのページに署名・押印
- コピー等による財産目録を添付する場合、本文とは別の用紙で作成する
1-3.遺言書の内容を変更・追加する場合
変更する場合、従前の記載に二重線を引き、押印しましょう。
加えて、上下左右いずれかの余白に変更場所、変更した旨、署名が必要です。
1-4.様式上の要件
自筆証書遺言書保管制度における様式は、下記の通りです。
| 概要 | |
|---|---|
| 用紙 | A4サイズ 文字の判読を妨げるような地紋、彩色等のないものを使用(無地が無難です) |
| 余白 | 上側5mm以上 下側10mm以上 左側20mm以上 右側5mm以上 |
| 記載面 | 片面のみに記載 |
| ページ番号 | 遺言書本文、財産目録について、各ページにページ番号を記載 例:1/1 |
| その他 | 遺言書本文、財産目録が複数ページにわたっても、綴じないこと |
1-5.その他
その他、下記の要件を守りましょう。
- 推定相続人以外に対しては「遺贈する」と記載
- 受贈者等は、申請書に記載が必要
- 遺言執行者を指定する場合、申請書に記載
2.申請書を作成
2-1.申請先
遺言書の保管申請は、下記のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)であればどこでも可能です。
- 遺言者の住所地
- 遺言者の本籍地
- 遺言者が所有する不動産の所在地
2-2.申請書の入手方法
申請書は、最寄りの法務局窓口または法務省ホームページよりダウンロードすることができます。
2-3.申請書作成時の注意点
自宅で申請書を作成・印刷する場合、下記に注意しましょう。
- 両面印刷はしないこと
- 拡大、縮小印刷はしないこと
- A4サイズ以外の用紙で印刷しないこと
- 用紙に汚れ、曲がり、濡れ、破損、変色等がないようにすること
- 印刷した申請書を再度コピーしないこと
2-4.記載項目
申請書に記載が必要な項目は、下記の通りです。
3.添付書類等を準備
遺言書、申請書が作成できたら、添付書類を準備します。
- 顔写真付の官公署から発行された身分証明書
- 本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し等
- 3,900円分の収入印紙
4.遺言保管所(法務局)に予約
自筆証書遺言書保管制度の利用において、全ての手続につき予約制です。
Web、電話、窓口のうちから予約方法を選んで予約しましょう。
当日予約はできないことと、遺言書1通につき1件の予約が必要な点に注意しましょう。
5.法務局にて保管申請
法務局にて保管申請を行います。
申請前に、下記を確認しておきましょう。
- 作成した遺言書が民法上の要件、様式上のルールに適合するか
- 申請書の記載事項をすべて満たしているか
- 遺言書に受遺者・遺言執行者を定めた場合、申請書に記載しているか
- 指定者通知の申出を希望する場合、情報の取扱いに関する同意事項欄にチェックを入れたか
- 指定者通知の申出を希望する場合、通知対象者は3名以内か
- 申請書は拡大・縮小していないか
- 遺言者の本籍および戸籍筆頭者の記載がある住民票の写しを添付しているか
- マイナンバーカードや運転免許証等、顔写真付の身分証明書を携帯しているか
- 3,900円分の収入印紙は用意したか
- 法務局に予約したか
6.保管証の受取
提出書類に不備がなければ、当日中に保管申請手続は終了し、保管証を受け取ります。
保管証に関する注意点は、下記の通りです。
- 保管証には、保管した遺言書を特定するために必要な「遺言者氏名」「出生年月日」「手続を行った遺言書保管所の名称」「保管番号」が記載される
- 保管証の再発行は認められない
自筆証書遺言作成の注意点
変更の届出
法務局に遺言書を預けた後、下記について変更が生じた場合、速やかに法務局に届出る必要があります。
- 遺言者の氏名、出生年月日、住所、本籍および筆頭者
- 遺言書に記載した受遺者等、遺言執行者の氏名または名称、住所等
- 指定者通知対象者の氏名、住所等または通知対象者を変更・追加する場合
変更の届出は、
1.変更の届出先を確認
2.届出署を作成
3.予約
4.法務局にて届出
という流れで行います。
自筆証書遺言書保管制度よくある質問(FAQ)
1.法務局で遺言書の書き方を教えてくれるか
法務局において、遺言書の内容に関する相談には、一切応じてもらえません。
このため、自分で調べるか、専門家の手を借りて作成しましょう。
2.保管申請を代理人に頼めるか
令和6年(2024年)現在、本人出頭義務に代わる運用は認められず、代理人による申請は不可能です。
何らかの事情があり、本人が法務局に出向けない場合、公正証書遺言の作成が考えられます。
公正証書遺言の場合、公証人が病院や自宅まで出張してくれるほか、専門的な知見を期待できます。
3.申請後に遺言内容を変更したい場合
保管申請の撤回手続を経て、遺言書を返還してもらった後、新たな遺言書を作成したうえで保管申請する、または、撤回手続をせず、新たに遺言書の保管申請を行うことができます。
いずれの場合も手数料がかかることに注意しましょう。
自筆証書遺言書保管制度の申請要件、方法、注意点まとめ
当ページでは、自筆証書遺言書保管制度の申請要件、申請方法、手続上の注意点を解説しました。