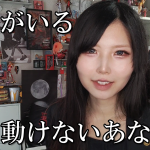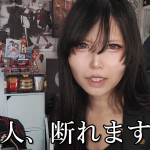当サイトの一部に広告を含みます。

当ページでは、個人事業主が廃業する際に必要な手続と費用、注意点を解説します。
Contents
筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
個人事業の廃業に必要な手続
個人事業主が廃業する場合、「廃業届」を提出する必要があります。
廃業届とは
廃業届は、個人事業主が廃業するにあたり、国や地方自治体に対し、事業を辞めることを知らせるために提出する書類を指します。
廃業時に提出する書類
廃業する場合、廃業届の他に下記の書類を提出する必要があります。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書
- 個人事業税の事業開始(廃止)等届出書
- 給与支払事務所等の解説・移転・廃止の届出書
- 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書
1.個人事業の開業・廃業等届出書
事業を廃業した場合、廃業した日から1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出しましょう。
廃業手続の後に行う支出は経費と認められない場合もあるため、廃業日は慎重に検討しましょう。
廃業届を提出した場合でも、廃業年度に対象となる取引がある場合は、確定申告が必要です。
2.所得税の青色申告の取りやめ届出書
青色申告を選択している場合、廃業届と一緒に「所得税の青色申告の取りやめ提出書」を提出しましょう。
提出期限は、事業を廃止しようとする年の翌3月15日までです。
実務上は、廃業届と同時に提出する場合が多いです。
3.個人事業税の事業開始(廃止)等届出書
個人事業を廃業する場合、都道府県税事務所に「事業開始(廃止)等申告書」を提出しましょう。
提出期限は、事業廃止の日から10日以内です。
原則、廃業年分の事業税は、納付が翌年となるため、特例として、課税見込額を廃業年分の必要経費に算入することができます。
4.給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
従業員(専従者も含む)を雇用し、給与の支払がある場合、税務署に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書」を提出しましょう。
提出期限は、事業を廃止した日から1か月以内です。
事業を廃業する際、給与から預かった源泉所得税について、廃業日の翌月10日までに納付しなければなりません。
半年に1度、まとめて支払う特例を受けていた場合でも、廃業時は翌月10日までに納付する義務を負います。
従業員から個人住民税を特別徴収していた場合、市区町村宛てに「異動届」の提出も忘れずに行いましょう。
5.所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書
廃業する個人事業主が予定納税を行っている場合において、予定納税額が実際を上回ると予測される場合に減額申請を行うことができます。
予定納税とは、事業所得等で発生した所得税について、翌年支払う一部の所得税の一部につき、先に納付するものです。
この場合、下記の期限内に「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」を税務署に提出しましょう。
- 第1期分及び第2期分の減額申請:当該年の7月1日から7月15日まで
- 第2期分のみ減額申請:当該年の11月1日から11月15日まで
減額申請後、予定納税の金額と確定した所得税額との差額分のみを納付することになります。
廃業にかかる費用
個人事業の廃業に際し、下記の費用がかかります。
- 機械設備等の処分費用
- 在庫処分にかかる費用
- 従業員の退職金等
- 原状回復費等(賃貸物件の場合)
1.機械設備の処分費用
事業で使用していた機械設備について、廃業すれば不要となるため、処分を行います。
対象となる設備により処理方法は異なりますが、専門業者への買取、同業者への譲渡、廃棄処分等が考えられます。
2.在庫処分にかかる費用
小売業等を廃業する際、抱えている在庫の処分に費用がかかる場合があります。
廃業まで時間がある場合、原価割れを選んででも売り切ることができれば、数値は赤字でも、それ以上に費用がかかることはありません。
ただし、市場価値がある場合には買い取りを検討し、最後に処分費用を見積もる方法も大いにあり得ます。
3.従業員の退職金等
従業員を使用している場合、廃業による「解雇」として扱います。
就業規則上、退職金の規程を定めていない場合でも、廃業に至った理由が事業者都合なら、後のトラブル防止の観点から退職金等を準備しておくのが望ましいといえます。
4.原状回復費等(賃貸物件の場合)
事業所として賃貸物件を使用していた場合、退去時に原状回復を求められる場合があります。
入居時の契約内容を確認し、廃業までにある程度の資金を用意しておくと安心です。
事業を休業したい場合
一時的な経営難の場合、いきなり廃業を選ぶのではなく、休業という選択肢があります。
休業する場合、特別な手続は必要ありませんが、特定の自治体では、個人事業に関し「事業休止届」の提出を求めるところもありますので、事前に確認しましょう。
青色申告の場合は注意
確定申告は、対象となる事業で所得がある場合に必要な手続なので、休業により事業以外の所得が生じていない限り、申告義務はありません。
ただし、青色申告事業者が純損失の繰越を希望する場合、休業中であっても、確定申告書を提出する必要があります。
純損失の繰越要件に「毎年連続して確定申告書を提出すること」とあるため、休業を理由に提出を行うと、純損失が消えてしまうことが理由です。
個人事業の廃業に必要な手続と費用、注意点まとめ
当ページでは、個人事業の廃業に必要な手続と費用、注意点を解説しました。