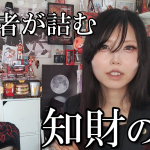当サイトの一部に広告を含みます。

当ページでは、他人の著作物を適法に利用する方法と手続、注意点を解説します。
Contents
筆者プロフィール
他人の著作物を利用する場合
他人の著作物を利用する場合、次の内容を検討します。
- 国内における保護の有無
- 著作権の保護期間
- 使用許諾の要否
- 著作者の特定可能性
1.国内における保護の有無
下記のいずれかに該当するものは、国内で保護されます。
- 日本国民の著作物
- 日本国内で最初に発行(公表)された著作物
- ベルヌ条約等により、日本が保護の義務を負う著作物
いずれにも該当しない場合、著作権者への許諾なく使用できる可能性もありますが、著作権以外の知的財産権等により保護されている場合もあります。
事前確認を怠らないようにしましょう。
(1)憲法、法令
(2)国・地方公共団体等が発する告示、訓令、通達等
(3)裁判所の判決、決定、命令、審判、行政庁の裁決、決定
(4) (1)から(3)の翻訳物・編集物で、国・地方公共団体等が作成するもの
に該当する場合は、著作権法による保護の対象外なので、自由に使用することができます。
2.著作権の保護期間
原則、著作権や著作隣接権等の権利には保護期間が定められています。
令和6年(2024年)3月現在における保護期間は、下記の通りです。
| 種類 | 保護期間 |
|---|---|
| 著作物 (原則) | 著作者の死後70年 |
| 無名・変名の著作物 | 著作物の公表後70年 |
| 団体名義の著作物 | 著作物の公表後70年 |
| 映画の著作物 | 著作物の公表後70年 |
| 実演 | 実演が行われた後70年 |
| レコード | レコードの発行後70年 |
著作権法では、原則、1度保護がきれた著作物等について復活措置はとらないため、一部の例外に該当する場合を除き、期間を満了した著作物は「パブリックドメイン」として、許諾なく使用することができます。
3.使用許諾の要否
日本国内で著作物を利用する際、下記に該当する場合、著作権者の許諾を得ず使用することができます。
- 私的使用のための複製
- 付随対象著作物の利用
- 検討過程における利用
- 著作物に表現された思想、勘定の享受を目的としない利用
- 図書館等における複製
- 引用
- 教科用図書等への掲載等
- 学校教育番組の放送等
- 学校その他の教育機関における複製等
- 試験問題としての複製等
- 視聴覚障害者等のための複製等
- 営利目的ではない上演等
アメリカでは、「フェアユース(公正利用)」を理由に著作権を利用することもあるようですが、日本国内での主張立証においては難しそうです。
4.著作者等の特定可能性
一定の努力をしても、使用を希望する著作物等の著作者等を特定することが困難な場合、文化庁長官による裁定制度を検討しましょう。
他人の著作物を利用する際の手続
利用を希望する他人の著作物等が保護状態にある場合、次の手続を行います。
- 著作権者等から許諾を得る
- 出版権の設定を受ける
- 著作権を譲受ける
- 裁定制度を活用する
1.著作権者等から許諾を得る
著作権者等が特定できる場合、本人に連絡をとり、利用について許諾をもらいましょう。
許諾方法に規定はなく、口頭でも成立しますが、後のトラブルを回避するためにも、下記を書面化しておくことをオススメします。
- 目的となる著作物の特徴
- 利用方法
- 許諾される範囲
- 使用料の金額、支払方法
- 支払期限など
2.出版権の設定を受ける
他人の著作物を利用した著作物を出版する場合、競合他社による出版を防ぐには、著作権者から独占的に許諾(出版権の設定)を得る方法があります。
出版権の設定を受けると、当該著作物の著作権者による同一作品についての許諾を重複することができ、二次著作者は安定的な創作活動を行うことができます。
この場合、文化庁に対し、出版権の設定登録を行いましょう。
3.著作権の譲渡を受ける
著作権は財産権の1種で、全部または一部を他人に譲渡することも可能です。
許諾は単なる「利用許可」に過ぎませんが、譲渡の場合、譲受人自らが著作権者として使用することができ、より広範な利用が可能となります。
ただし、第三者に対抗するには、文化庁に著作権の移転登録を済ませておくことをオススメします。
4.裁定制度を活用する
著作権者等が特定できたものの、その居所・連絡先等が特定できず、交渉を行うことが困難な場合、または、文化庁が定める「相当な努力」をしても著作権者等が特定できない場合、裁定制度の活用が考えられます。
著作権の裁定制度とは、文化庁長官の裁定を受け、通常、利用者から著作権者等へ支払う使用料相当額を補償金として供託することにより、適法に、著作物の利用ができる制度をいいます。
他人の著作物を適法に利用する方法、注意点まとめ
当ページでは、他人の著作物を適法に利用する方法、手続、注意点を解説しました。