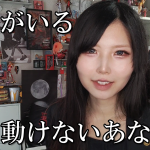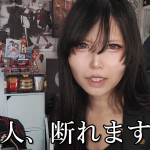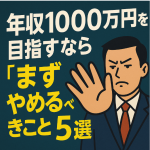当サイトの一部に広告を含みます。

本記事では、配偶者居住権についてわかりやすく解説します。
Contents
筆者プロフィール
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、被相続人(死亡人)と配偶者が済んでいる建物について、配偶者の死亡まで、または、期間を決めて無償で使用することができる権利をいいます。
配偶者居住権の要件
配偶者居住権を設定するには、下記の要件を満たす必要があります。
- 被相続人の配偶者であること
- 死亡時において、被相続人が所有していた建物に配偶者が居住していたこと
- 遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判により取得したこと
被相続人が配偶者以外の第三者と共有していた建物については、配偶者居住権を設定することができません。
配偶者居住権の効果
配偶者居住権を設定すると、原則、住んでいる建物の全てに権利が及びます。
配偶者の住む建物の一部が店舗や賃貸物件の場合、これらについても使用・収益することができます。
ただし、元々住むために利用していた部分について、賃貸など収益目的に利用する事はできない点に注意しましょう。
相続開始時に収益物件の一部を賃貸している場合、そこに住んでいる賃借人に対し、配偶者から明け渡しを求めることはできません。
さらに、その賃料は建物の所有権を相続する他の相続人が受け取ることになります。
配偶者短期居住権とは
被相続人の配偶者が、相続開始時点において、被相続人所有の建物に住んでいる場合、下記のうちいずれか遅い日まで無償で使用することができます(これを「配偶者短期居住権」といいます)
- 遺産分割で建物の帰属が確定するまで
- 相続開始の時から6か月を経過する日まで
配偶者短期居住権は、相続開始時に自動で発生します。
配偶者が相続放棄した場合でも認められますが、使用できるのは、元々配偶者が無償で使用していた部分のみです。
配偶者居住権の設定方法
配偶者居住権は、要件を満たすことで発生する権利なので、登記は必須ではありません。
しかし、登記を経なければ第三者に権利を主張することはできませんので、発生後は早めに登記手続をされることをオススメします。
登記に必要な書類
配偶者居住権の登記は、下記の書類を提出し、建物の所有者と共同して行います。
- 登記申請書
- 登記原因証明情報(遺言書または遺産分割協議書等)
- 登記識別情報
- 建物所有者の印鑑登録証明書
- 固定資産評価証明書
登記識別情報は、相続登記をした際、書面またはオンラインにて通知されるものです。登記完了証と間違えないようにしましょう。
登録免許税額
登記に必要な登録免許税の額は、固定資産評価証明書をもとに算出します。
計算方法は「建物の固定資産評価額×0.2%」です。
配偶者居住権設定後の手続
配偶者居住権の設定期間は、原則、配偶者の死亡までですが、下記に該当する場合、生きている間でも消滅します。
- 設定期間の満了
- 建物の使用方法に違反があった場合
- 配偶者が死亡した場合
- 建物全体が使用できなくなった場合
- 配偶者居住権を放棄した場合
1.設定期間の満了
配偶者居住権について、遺言者、遺産分割協議書により期間を限定した場合、当該期間の満了により、配偶者居住権は消滅します。
2.建物の使用方法に違反があった場合
配偶者居住権を取得した配偶者は、所有者に無断で増改築、他人への賃貸借を行うことはできません。
こうした行為を行った場合、所有者は、配偶者に相当の期間を定めて是正を催告することができますが、期間内に是正されない場合には、配偶者居住権を消滅させることができます。
3.配偶者が死亡した場合
配偶者が死亡した場合、配偶者居住権も消滅します。
この際、配偶者居住権に関して相続対象となることはありません。
4.建物全体が使用できなくなった場合
配偶者居住権が設定された建物が倒壊する等の理由で、その建物全体が使用できなくなった場合、配偶者居住権は消滅します。
5.配偶者居住権を放棄した場合
配偶者居住権を取得した配偶者は、その権利を放棄することができます。
建物を解体、売却したい場合、所有者側から代償金を支払い、放棄してもらうよう交渉する場面が想定されます。
配偶者居住権を設定するメリット
配偶者居住権を設定する場合、次のメリットがあります。
- 遺留分問題のリスク低減
- 配偶者が生活資金等を相続できる
1.遺留分問題のリスク低減
法定相続人のうち、兄弟姉妹を除く相続人には「遺留分」が定められています。
遺留分とは、法律で定められた最低限度の相続分で、相続人が複数いる場合等に他の相続人の遺留分を侵害する分割、遺贈等が行われた場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
配偶者が不動産を相続することで、他の相続人の遺留分を侵害することになれば、他相続人から遺留分侵害額請求を受けるほか、代償金を支払わなければならない場合があります。
いっぽう、配偶者居住権を設定する場合、不動産に関する権利を「所有権等」「居住権」に分けることになり、他者の遺留分を侵害リスクが極めて低くなります。
2.配偶者が生活資金等を相続できる
配偶者の相続分は、原則、遺産の2分の1です。
この相続分のなかで、土地・建物を取得した場合、預貯金等を相続できず、それどころか、他人の遺留分を侵害し、金銭を請求されるおそれがあります。
こうなると、配偶者は当面の生活資金が賄えず、結果的に建物を売り払うしかありません。
この点、配偶者居住権を設定する場合、制度上、通常の評価額より下がるため、相続税を抑えられるメリットがあります。
配偶者居住権は、居住建物について
相続税評価額-相続税評価額×(耐用年数-経過年数-存続年数÷耐用年数-経過年数)×存続年数に応じた法定利率による福利原価率
にて評価額を算定します。
配偶者居住権を設定する際の注意点
配偶者居住権を設定する場合、次の点に注意しましょう。
- 相続税の課税対象であること
- 配偶者の生存中は自由度が低い
- 配偶者居住権の譲渡、売却はできない
1.相続税の課税対象であること
配偶者居住権は、建物所有権、敷地利用権と比べると評価自体は低いです。
しかし、経済的価値があるものは相続税の課税対象となるため、配偶者の年齢が若い場合、存続年数も長くなるため、相続税が高くなる可能性があることには注意が必要です。
相続税の他、配偶者居住権を放棄した場合、子に贈与税がかかる可能性があるほか、配偶者に対し、譲渡所得税が課される可能性があります。
2.配偶者生存中の自由度が低い
配偶者居住権が設定されている場合、土地・建物の所有者は売却することができません。
これは、所有者、配偶者双方にいえることです。
例えば、配偶者が老人ホーム等の福祉施設に入居するため、土地や建物の売却を検討した場合、配偶者居住権が理由で売却することができません。
認知症等により、配偶者の判断能力が低下した場合、配偶者居住権の放棄を成年後見制度の利用が考えられますが、手間とコストがかかるため、慎重に検討しましょう。
3.配偶者居住権の譲渡、売却はできない
配偶者居住権について、配偶者は、譲渡・売却をすることができません。
法律で定められているものなので、当事者同士で合意に至ってもダメです。
配偶者居住権の要件、設定方法、注意点まとめ
当ページでは、配偶者居住権の要件、設定方法、注意点を解説しました。