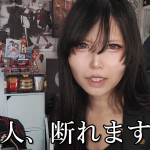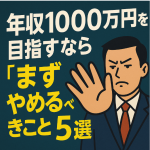当サイトの一部に広告を含みます。

当ページでは、遺贈の種類、贈与との違い、メリットと注意点を解説します。
Contents
筆者プロフィール
遺贈とは
遺贈とは、遺言書で指定した人や団体に対し、自身の財産を残すことをいいます。
遺贈の種類
遺贈は次の種類に分けられます。
| 1.包括遺贈 | 特定の財産を遺贈するのではなく、相続財産の割合を示し、遺贈することをいいます。 |
| 2.特定遺贈 | 相続財産のうち、特定の財産のみを指定して遺贈することをいいます。 |
1.包括遺贈
包括遺贈を受けた人(受遺者)は、相続財産の割合のみを示されるため、相続人と共に遺産分割協議に参加する必要があります。
相続財産にマイナスが含まれる場合、これについても、示される割合で承継しなければならない点に注意しましょう。
1-1.包括受遺者と相続人の違い
包括受遺者の場合、遺言者より先に死亡すると、遺贈されるはずだった遺産は相続人の分割対象となります。
また、遺言書により指定された割合が絶対で、相続人が相続放棄をした場合でも変動しません。
対して、相続人の場合、遺言者より先に死亡すると代襲相続(本来の相続人の子、孫が相続権を承継する制度)が発生し、相続放棄をした相続人がいると、相続分が増加する点で異なります。
1-2.包括遺贈は拒否できる
包括遺贈について、受遺者は拒否する権利があります。
ただし、相続開始を知ったとき及び包括遺贈の存在を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所において、遺贈の放棄を申述する必要があり、これを過ぎると遺贈の受取りを承認したものとみなされますので注意しましょう。
1-3.包括遺贈が向いている場合
次に該当する場合、遺言者は包括遺贈を検討する余地があるかもしれません。
- 財産に価額が変動する資産が含まれる場合
- 受遺者に取得する財産を選ばせたい場合
2.特定遺贈
特定遺贈は、遺贈する財産が特定されているため、遺産分割協議に参加する必要はなく、原則、マイナスの財産を承継することはありません。
2-1.特定遺贈も受取りを拒否できる
特定遺贈の場合も、受遺者には拒否する権利があります。
特定遺贈を拒否するには、相続開始後、いつでも相続人に放棄の旨を示し、放棄することができます。
ただし、受遺者を除く相続人や利害関係者は、受遺者に対し、相当の期間を定めて催告する権利をもっています。
この期間内に意思表示をしなければ、特定遺贈の受取りを承認したものとみなされますので、早めに確答しましょう。
2-2.特定遺贈が向いている場合
下記に該当する場合、特定遺贈を検討しましょう。
- 遺贈したい財産が明確な場合
- 受遺者にマイナスの財産を承継させたくない場合
- 遺産分割協議に受遺者を参加させたくない場合
遺贈する際の注意点
遺贈を行う場合、次の点に注意しましょう。
- 遺贈者より先に受遺者が死亡すると無効になる
- 指定先により、受遺者になれない場合がある
- 遺留分侵害額請求をされる可能性がある
- 遺言書への記載方法
- 特定遺贈の場合、相続税の債務控除が受けられない
- 特定遺贈の場合、不動産所得税の課税対象となる
1.遺贈者より先に受遺者が死亡すると無効になる
遺贈を行う際、遺言者よりも先に受遺者が死亡すると、遺贈そのものが無効となります。
相続人の場合は代襲相続が発生しますが、受遺者が相続人以外の場合には、子や孫がいても代襲相続することができません。
「受遺者の相続人へ遺贈する」等の一文を加えておくと、先に受遺者が死亡している場合に相続人が遺贈を受けることができます。
2.指定先により、受遺者になれない可能性がある
遺贈の目的となる財産について、現金や換価価値の高いものなら問題ありませんが、売却見込のない山林等の土地、共有状態の不動産の場合、受遺者が困る場合があります。
このほか、受遺者(団体を含む)により適用される税目等が異なるため、かえって負担をかける可能性もあります。
遺贈を検討する際は、お近くの税務署または税理までご相談ください。
3.遺留分侵害額請求をされる可能性がある
遺贈割合が相続人の遺留分を侵害する場合、相続人から受遺者に対し、遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。
この場合、遺言者が希望する分割は実現が困難となり、予期せぬトラブルを招く要因となります。
遺言書を作成する際は、相続人と遺留分の確認をされることを強くオススメします。
4.遺言書への記載方法に注意
遺贈は、遺言書により行います。
遺言書に記載する際は、包括遺贈、特定遺贈の区別がわかるよう明確に記載し、特定遺贈の場合、目的となる財産が特定できる情報を記載しましょう。
預貯金の場合、金融機関名、支店名、口座の種別、口座番号、不動産の場合は登記簿謄本の記載通りが望ましいです。
難しい場合は原本またはコピーを財産目録として記載することもできます。
5.特定遺贈の場合、相続税の債務控除が受けられない
特定遺贈の場合、受け取る財産に債務が含まれる場合でも、相続税の債務控除を受けることができません。
なぜなら、債務控除の対象は、相続財産に含まれる債務を負担する相続人、包括受遺者だからです。
ただし、ローンの残る土地建物等の不動産を遺贈された場合、不動産価額から残債務を引いた価額を課税価格として採用することができます。
6.特定遺贈の場合。不動産取得税の課税対象となる
原則、相続や包括遺贈で取得した不動産については、不動産取得税はかかりません。
しかし、特定遺贈の場合には不動産取得税の課税対象となるため、受遺者に負担がかかる可能性がある点に注意しましょう。
遺贈の種類、メリット、注意点まとめ
当ページでは、遺贈の種類とメリット、注意点を解説しました。