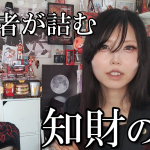当サイトの一部に広告を含みます。

当ページでは、遺留分侵害額請求の流れ、手続と注意点を解説します。
Contents
遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、相続できる財産が遺留分よりも少ない場合、遺留分を侵害している相手に対し、不足額相当の金額を請求する制度をいいます(民法 第1046条第1項)
遺留分とは、法律により定められる「最低限度の相続分」をいいます。
遺留分侵害額の算出方法
遺留分侵害額は、相続財産に自身の遺留分割合をかけた「遺留分」から、実際に相続・遺贈(贈与を含む)によって相続した財産額を差し引いて算出します。
| 遺留分 | (みなし相続財産)× 相対的遺留分率 × 遺留分権利者の法定相続分 |
| 遺留分侵害額 | 遺留分 – 遺留分権利者が受けた遺贈・特別受益の額 – 遺留分権利者の相続財産の価額 + 遺留分権利者が負担した相続債務の額 |
「みなし相続財産」は、相続開始時の財産価額+贈与財産の価額-相続債務にて算出します。
総体的遺留分とは、財産全体に占める遺留分の割合を指します。
相続人が直系尊属のみであれば3分の1、それ以外は2分の1となります。
遺留分侵害額請求の対象となる遺贈・贈与
遺留分侵害額請求の対象となるのは、遺贈・贈与を受けた人のうち、下記の順序により行います。
| 受遺者・受贈者がいる場合 | 1. 受遺者 2. 受贈者 |
| 受遺者が複数いる場合、または 受贈者が複数いる場合 | その贈与が同時に行われた場合、目的価額に応じて負担 |
| 受贈者が複数いる場合 | 後に贈与を受けた人から順に、遡って負担する |
生前贈与の場合、相続人に対して行われた場合は10年間、相続人以外に対して行われたものは1年間に限り、相続開始の時から遡って遺留分侵害額請求の対象となります(民法 第1044条第1項)
遺留分侵害額請求権の消滅時効と請求期間(除斥期間)
遺留分侵害額請求権の消滅時効は、遺留分請求者が、相続の開始 及び 遺留分を侵害する贈与 または 遺贈があったときから1年間です(民法 第1048条)
また、相続開始から10年間が経過すると、遺留分侵害額請求ができなくなるため、早めに対応する必要があります。
遺留分侵害額の請求方法
遺留分侵害額請求を行う場合、下記のように進めます。
- 相続人同士の話し合い
- 内容証明郵便の送付
- 遺留分侵害額請求 調停
- 遺留分侵害額請求 訴訟
1. 相続人同士の話し合い
遺留分侵害額請求について、必ず裁判を行わなければならないルールはなく、はじめは相続人同士での話し合いとなります。
2. 内容証明郵便の送付
相続人同士による話し合いがまとまらない場合、調停の申立てを検討しましょう。
内容証明郵便とは、郵便局が「差出人」「受取人」「内容」「差出日」等を証明してくれる郵便を指し、遺留分侵害額請求権の時効を止める役割と、客観的な証拠能力を備えるのに役立ちます。
内容証明郵便により催告した場合、消滅時効までの期間が6か月猶予される(民法 第150条第1項)ほか、猶予期間内に調停 または 訴訟を起こした場合、消滅時効が完成することはなくなります。
3. 遺留分侵害額請求 調停
内容証明郵便による催告に相手が応じない場合、遺留分侵害額の請求調停を検討しましょう。
3-1. 調停の流れ
遺留分侵害額請求の調停は、下記の流れで進みます。
- 調停の申立て
- 証拠・主張書面の提出
- 調停期日の話し合い
- 調停成立 または 不成立
3-2. 調停申立てに必要な書類
調停を申立てる際、下記の書類を提出します。
- 申立書
- 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言書の写し または 検認調書謄本の写し(遺言書がある場合)
- 遺産に関する証明書
- 収入印紙 1,200円分
- 連絡用の郵便切手
上記以外の書類を求められる場合もあるため、連絡用の郵便切手とあわせ、申立て先となる家庭裁判所まで事前に確認しましょう。
4. 遺留分侵害額請求 訴訟
遺留分侵害額請求の調停が成立しなかった場合、遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。
- 訴状の提出
- 証拠・準備書面の提出
- 口頭弁論
- 和解勧告
- 判決
- 判決の確定
原則、遺留分侵害額請求訴訟を提起するには、調停を経る必要があります(家事事件手続法 第257条)
例外として、全く話し合いにならない等の理由がある場合は、いきなり訴訟を提起することも認められます。
4-1. 判決と確定
訴訟の係属中、裁判所から「和解勧告」が行われることがあります。
双方がこれを受け入れれば、そこで裁判上の和解成立となり訴訟は終了しますが、そうでない場合は、口頭弁論において主張・立証を繰り返し、最終的に判決が言い渡されます。
判決書の送達から2週間は、双方が控訴することができますが、控訴がなければ判決が確定します。
4-2. 必要な書類
遺留分侵害額請求訴訟を提起する際は、下記の書類を提出します。
- 訴状の正本・副本
- 証拠書類の写し
- 収入印紙
- 郵便切手代
4-3. 必要な費用
訴訟の場合、請求額に応じ、下記の金額を納めることになります。
| 100万円まで | 10万円ごとに1,000円 |
| 500万円まで | 20万円ごとに1,000円 |
| 1,000万円まで | 50万円ごとに2,000円 |
| 1億~10億円まで | 100万円ごとに3,000円 |
| 10億円を超える部分 | 500万円ごとに1万円 |
| 50億円を超える部分 | 1,000万円ごとに1万円 |
遺留分侵害額請求の流れ、注意点 まとめ
当ページでは、遺留分侵害額請求の流れと注意点を解説しました。