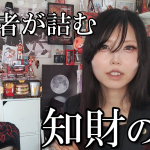当サイトの一部に広告を含みます。

当ページでは、経営者がとるべき相続対策、注意点を解説します。
Contents
経営者死亡時のトラブル
被相続人が経営者の場合、下記のトラブルが頻出です。
- 遺産分割でもめる
- 相続税が払えない
- 事業を承継する人が決まらない
相続対策の前に必要なこと
相続への備えを検討する前に、下記を行いましょう。
- 相続財産の特定・分類
- 債務・担保等の整理
1. 相続財産の特定・分類
経営者の相続において、相続財産に含まれるもの・含まれないものを分けましょう。
個人事業主の場合、原則、すべての事業用資産は個人資産として相続財産に含まれます。
いっぽう、法人の代表者の場合、法人名義の資産は相続財産に含まれません。
2. 債務・担保等の整理
担保とは、融資を受ける際に、債務者が返済出来なくなる可能性に備え、債権者に提供する資産や権利を指します。
借入額が高額な場合のほか、資本金や自己資本率が少ない場合、支払期限まで猶予がある場合に設定されるため、相続財産に下記が含まれる場合には、担保の設定有無も含めて確認しましょう。
- 不動産(土地、建物)
- 債権
- 有価証券(株券、債権等)
- 車両・事業用機械器具など
- 連帯保証人
個人事業や小規模法人の場合、被相続人が連帯保証人になっている債務に注意しましょう。
遺産分割、後継者の検討
相続財産が特定したら、相続時の分割割合、事業の後継者について検討します。
1. 遺産分割
相続において、遺産の分割方法は3つあります。
- 法律にしたがった分割
- 被相続人による指定
- 相続人同士の話し合い
(1) 法律にしたがった分割
法律にしたがい遺産を分割する場合、特別準備するものはありません。
ただし、相続人が法律に詳しくなければ困る場面も多く、手続が難航する可能性があります。
(2) 被相続人による指定
生前に備える場合、遺産の分割割合、相続する人を指定することができます。
代表的なのは「遺言」ですが、決められた様式が備わっていない場合、無効になる可能性がある点に注意しましょう。
(3) 相続人同士の話し合い
被相続人が遺言書を作成していない場合のほか、遺言書の内容と異なる方法での分割を希望する場合には、相続人全員で話し合って決めることになります。
遺言書に記載されていない遺産については、都度、相続人同士で話し合って決めることになる点に注意です。
2. 後継者
事業存続を希望する場合、後継者を検討します。
代表の死亡後、何の定めもない場合には、残された役員・従業員等で後継者を決めることになります。
あくまでも筆者の経験則ですが、当事者間での話し合いによる後継者選出は、概ねもめるので、生前に後継者を指名しておく等の対策は必要かと思います。
2-1. 円滑な事業承継に有効な制度
事業承継を円滑にするため、下記を検討しましょう。
- 遺留分に関する民法の特例
- 事業承継税制
- 社長貸付金として処理する
① 遺留分に関する民法の特例
遺留分とは、法律に定められた相続人の権利で、相続分の最低保障分を指します。
親族経営を行っている場合、後継者が親族で相続人に含まれる場合も多く、遺留分が問題になる場面が見られます。
これについて、一定要件を受けることで、下記の適用を受けることが出来ます。
| 除外合意 | 生前贈与した株式・事業用資産の価額を遺留分の算定基礎となる遺産額から除外する合意 |
| 固定合意 | 法人株式の価額について、相続人全員の合意時に評価して固定する合意 |
| 付随合意 | 除外合意・固定合意とあわせて行う合意 後継者が被相続人から贈与を受けた財産を遺留分の対象から除外する、後継者以外の相続人が被相続人から受けた財産を遺留分から除外する等 |
② 事業承継税制
事業承継税制とは、承継に伴う税負担を軽減する特例のことをいいます。
当制度も一定要件を満たさなければ適用が受けられない他、ルールを守らなければ途中でも適用外となる点に注意しましょう。
③ 社長貸付金として処理する
社長貸付金とは、経営者が個人名義で法人に課した金銭を指します。
事業資産から見ると「負債」となり、個人資産から見ると「資産」に含まれるため、生前に債権放棄等の手法をとって相続財産から除外する等の方法が考えられます。
経営者の相続対策、注意点 まとめ
当ページでは、経営者の相続対策に必要なこと、注意点を解説しました。