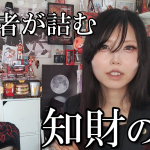当サイトの一部に広告を含みます。
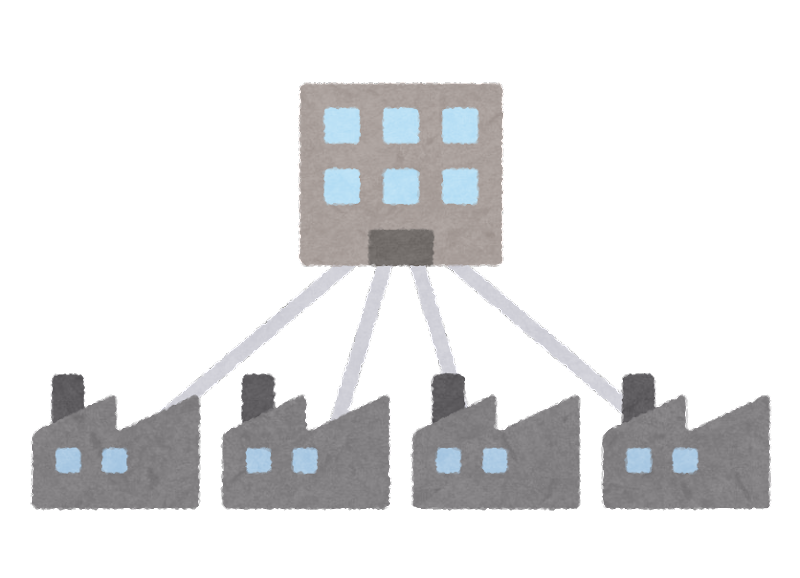
当ページでは、業務を外注する前に知っておくべき「下請法」の内容と、注意点を解説します。
Contents
下請法とは
下請法(正式名を「下請代金支払遅延等防止法」といいます)は、発注者に対し、立場が低くなることの多い下請事業者を保護する目的で制定された法律を指します。
この法律は、クライアントが私欲を肥やす「プラス」ではなく、下請事業者が被るであろう「不利益」を重視し、回避を目指すものです。
下請法の対象事業者
下請法の対象となるのは、下記の事業者です。
| 目的 | 親事業者 | 下請事業者 |
|---|---|---|
| (1) 物品の製造・修理委託 及び 政令で定める情報成果物・役務提供委託の場合 | 資本金3億円超 | 資本金3億円以下 (個人を含む) |
| 資本金1千万円超3億円以下 | 資本金1千万円以下 (個人を含む) | |
| (2) 情報成果物作成・役務提供委託を行う場合 ( (1)の情報成果物・役務提供委託を除く ) | 資本金5千万円超 | 資本金5千万円以下 (個人を含む) |
| 資本金1千万円超5千万円以下 | 資本金1千万円以下 (個人を含む) |
下請法の対象取引
下記に該当する場合、下請法の対象となります(下請法 第2条第1項~第6項各号)
| 区分 | 概要 | 例 |
|---|---|---|
| 製造委託 | 物品の製造・販売を行う事業者が、品質・規格・デザイン等を指定し、他の事業者に物品の製造・加工等を依頼するもの | 自動車メーカーから部品メーカーへ、部品の製造を委託 |
| 修理委託 | 物品の修理を請け負う事業者が修理を他社に依頼する場合や、自社で使用する物品の修理を他社に依頼するもの | 家電メーカーが販売した製品の修理に必要な部品の製造を部品メーカーに委託 |
| 情報成果物の作成 | 情報成果物の作成・提供事業者が他社に作業を依頼するもの | ゲームソフト・汎用アプリソフトメーカーが、開発を他社に委託 |
| 役務の提供 | 各種サービスの提供を行う事業者が請け負ったサービスを他社に依頼するもの | 貨物運送業者が請け負った運送業務のうち、一部経路の業務をトラック運送会社に委託 |
1. 製造委託
製造委託とは、物品の製造・販売を営む製造業者・販売業者等の事業者が、規格、品質、形状、デザイン、ブランド等を指定し、他の事業者に物品の製造・加工等を依頼することを指します(下請法 第2条第1項)
ここでの「物品」とは動産をいい、家屋等の建築物は含みません。
2. 修理委託
修理委託とは、物品の修理を請け負う事業者がその修理を他の事業者に委託する場合や、自社で使用する物品を自社で修理する際、その修理の一部を他の事業者に委託するものを指します(下請法 第2条第2項)
3. 情報成果物作成委託
ソフトウェア、映像コンテンツ、各種デザイン等、情報成果物の作成・提供を営む事業者が、他の事業者に作成作業を委託するものを指します(下請法 第2条第3項)
情報成果物とは、ゲームソフト・会計ソフト・家電製品の制御プログラム等のプログラム、テレビ・ラジオ番組やCM、映画等の映像・音声・音響等から構成されるもの、設計図、各種デザイン、雑誌広告、報告書等の文字・図形・記号等から構成されるものを指します(下請法 第2条第6項)
- プログラム
- 映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの
- 文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩の結合により構成されるもの
- 前3号に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの
4. 役務提供委託
役務提供委託とは、運送・ビルメンテナンスをはじめ、各種サービスを提供する事業者が請け負った役務を、他の事業者に委託するものを指します(下請法 第2条第4項)
ただし、建設業法に規定される建設業を営む事業者の請負工事は対象外となります。
自動車・船舶による貨物運送、ビル・自動車・機会等のメンテナンス、アフターサービスやコールセンター等の顧客サポート等、幅広い分野が含まれます。
5. 建設工事は適用外
原則、建設業法に規定する建設業を営む事業者が請け負う建設工事は規制対象外ですが、建設資材や部材を販売する建設業者が、商品の製造を外部委託する場合には「製造委託」に該当し、規制対象となります。
また、建設業者が外部に設計図面の作成を委託する場合は「情報成果物作成委託」の対象となる点にも注意が必要です。
親事業者が遵守すべき義務
親事業者は、下記を遵守しなければなりません。
- 発注書面の交付義務
- 支払期日を定める義務
- 取引記録の書類を作成・保存する義務
- 遅延利息の支払義務
1. 発注書面の交付義務
親事業者が、口頭発注によるトラブル防止のため、発注内容に関する具体的な内容をすべて記載した書面を交付する義務を負います(下請法 第3条各項)
ただし、試作品の製造、修理委託等、事前に下請代金が算定できない場合には、正式単価の代わりに「下請代金の算定方法」の記載が認められます。
(1) 発注書面に記載すべき内容
発注書面には、下記を記載しなければなりません。
- 親事業者 及び 下請事業者の名称(番号、記号等による記載も可)
- 委託をした日
- 下請事業者が給付すべき内容
- 依頼内容の提供日(作成依頼の場合は受領日)
- 受領(提供)場所
- 給付内容について検査する場合、検査を完了する日
- 下請代金の額(算定方法の記載も可)
- 代金の支払期日
- 手形を交付する場合、手形の金額(支払比率でも可)と満期日
- 一括決済で支払う場合、金融機関名、貸付または 支払い可能額、親事業者が代金相当額 又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日
- 電子記録債権で支払う場合、電子記録債権の額 及び 電子記録債権の満期日
- 原材料等を有償支給する場合、品名、数量、対価、引渡し期日、決済期日 及び 決済方法
2. 支払期日を定める義務
親事業者は、下事業者と合意の上、事前に下請代金の支払期日を定める義務を負います。
この場合、支払期日は納入された物品の受領後60日以内、かつ、できる限り短い期間になるように定めなければなりません。
互いに合意し、受領から60日経過日よりも先を設定した場合でも、当該条項は無効となり、受領から60日を経過する日の前日を支払期日とみなします。
3. 書類作成・保存義務
親事業者は、下請取引が完了した場合に、給付内容、下請代金の額等の取引に関する記録を書類として作成し、2年間保存する義務を負います。
4. 遅延利息の支払義務
親事業者が支払期日までに下請代金を支払わなかった場合、下請事業者に対し、遅延利息を支払う義務を負います(下請法 第4条の2)
遅延利息は、受領日から60日を経過した日から実際に支払う日までの期間について、未払金額に年率14.6%をかけて算出します。
親事業者の禁止行為11項目
下請法では、親事業者に対し、下記の行為を禁止しています(下請法 第4条)
- 受領拒否
- 下請代金の支払遅延
- 下請代金の減額
- 返品
- 買いたたき
- 物の購入・役務の利用強制
- 報復措置
- 有償支給原材料等の対価早期決済
- 割引困難な手形交付
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 不当な給付内容・やり直し
1.受領拒否
受領拒否とは、下請事業者に責任がないにもかかわらず、親事業者が発注した物品等の受領を拒否することを指します。
発注の取消し、納期の延期等により納品物を受け取らない等の行為は受領拒否に該当します。
ただし、下請事業者が親事業者の注文を無視して作成したものを納品しようとする場合や、約束の期日を過ぎ、委託した物品等が不要になったことを理由とした受取りの拒否は、当該規定の対象外となります。
また、納品期日よりも前の納品を断ることも受領拒否とはなりません。
実務上、期日前の納品でも受け取る親事業者は多いかと思いますが、この場合、下請代金の支払期日は本来の期限で構いません。
2.支払い遅延
支払遅延とは、親事業者が発注した物品等の受領日から60日以内に定めた支払期日までに支払わない場合を指します。
物品等の検査・検収等に日数がかかる場合でも、支払期日を過ぎれば「支払遅延」となる点に注意しましょう。
(1) 受領日の起算点
「受領」と「期日」について、「納品締切制度」「検収締切制度」のいずれかで運用されるかと思いますが、一般的には「検収締切制度」を採用し、納品▶検収▶支払いの流れになります。
検収時に不具合があり、下請事業者にやり直しを依頼する場合、支払遅延の起算日は、やり直し後の納品日となります。
委託内容が「役務提供」の場合は、実際に働いた日を納品日として取り扱い、契約期間最終日の終了時を起算点とします。
(2) 完成度の評価方法
情報成果物作成委託契約の場合、納品物の完成度を評価するのが難しいことから、
- 品物が委託した水準をクリアしているかわかりづらい
- あらかじめ当事者間で「成果物の内容が一定水準をクリアしていることを確認した時点に受領する」
という要件を満たした場合、上記の時点を受領日として取り扱うことも可能です。
逆に言えば、このような取り決めがなければ、実際の納品日を「受領日」として算定します。
(3) 振込のタイミング
下請代金の支払を金融機関経由で行う場合、振り込むタイミングにより土日祝日をはさむ場合があります。
この点、当事者間での取り決めが優先されますが、何の取り決めもない場合は、「60日ルール」を厳格に適用することになります。
3.下請代金の減額
下請代金の減額とは、下請事業者に責任がないにもかかわらず、発注時に決定した下請代金を発注後に減額することを指します。
「協賛金の徴収」「原材料価格の下落」等、名目・方法・金額にかかわらず、あらゆる減額行為が禁止される点に注意しましょう。
ただし、下記に該当する場合には減額が認められる可能性があります。
- 下請事業者の過失・納期遅延により、受領拒否をしなくてはならない場合
- 下請事業者の過失・納期遅延により、受領拒否はしないものの、親事業者自ら修正を施し、契約の目的となる期日に間に合わせた場合
- 納期遅延・あからさまな欠陥等により、納品された商品価値が低下している場合
(1) 振込手数料、端数処理
原則、振込手数料は発注者(親事業者)負担となります。
このため、下請事業者の合意を得ることなく下請事業者負担として入金した場合、身勝手な減額とみなされ、下請法違反の判断を受ける可能性があります。
また、下請代金に端数が生じる場合、一定額未満の端数を無断で切り捨てる行為も下請代金の減額とみなされますので、契約時、または支払前に確認しておくと安心です。
4.返品
返品と、下請事業者に責任がないにもかかわらず、発注した物品等を受領後に返品することを指します。
納品された物品等について、委託の内容と明らかに異なる品物や、品質の劣る物品のほか、納品後、すぐに見つけるのが難しい問題が後になって判明した場合には、受領から6か月以内に限り、返品が認められます。
契約において、受領から6か月を超える保証期間等を定めている場合は、これに従います。
5.買いたたき
買いたたきとは、発注した物品・役務等に対し、通常支払われる対価に比べ、著しく低額での取引を強いることを指します。
通常支払われる対価とは、同種または類似品等の市場価格をいい、原則、親事業者と下請事業者との間で、契約前に協議して定めることが求められます。
6.物の購入強制・役務の利用強制
物の購入強制・役務の利用強制とは、下請事業者に発注する物品の品質維持等の目的がないにもかかわらず、親事業者の指定する製品・原材料等の物や役務を強制的に購入、利用させることを指します。
親事業者は選択肢の1つとして提示した場合でも、下請事業者が強制と感じ、本来は不要な商品・役務を利用した場合もこれに該当します。
いわゆる「忖度」ですね。
7.報復措置
報復措置とは、親事業者の違反行為について、下請事業者が公正取引委員会や中小企業等に通報したことを理由に、取引数量の削減・取引の停止といった不利益な扱いをすることを指します。
器の小さな親事業者にすがる必要はありませんが、仕事となるとそうもいかない場面も多く、このような横暴を許さないために敷かれた規則です。
8.有償支給原材料等の対価の早期決済
有償支給原材料等とは、親事業者が有償で支給する原材料等を指します。
下請事業者が物品の製造等を行う場合、その原材料等を使用した物品の下請代金の支払日よりも先に、原材料等の対価の支払日を定めるような場合が「有償支給原材料等の対価の早期決済」に該当します。
物品の完成には原材料ありきですが、完成しなければ商品代金も入金されず、材料費の支払は厳しいですよね。
親事業者が支払を求めなかった場合でも、下請事業者に支払う下請代金から無断で材料費を控除することも禁止されています。
9.割引困難な手形の交付
割引困難な手形の交付とは、下請代金を手形で支払う際、銀行・信用金庫等の一般的な金融機関での割引が困難な手形を交付することを指します。
具体的には、長期手形を指していて、繊維業は90日超、その他は120日を超える手形をいいます。
振出手形が現金に換金できなければ、下請事業者はたいへん困るため、支払方法は契約前にしっかり確認しましょう。
10.不当な経済上の利益の提供要請
不当な経済上の利益の提供要請とは、親事業者が自己のために、下請事業者に金銭・役務、その他経済上の利益を不当に提供させることを指します。
当該規定は、実際に提供させた場合だけでなく、提供を要請した場合でも規制対象となる点に注意が必要です。
下請代金の支払は、協賛金や従業員の派遣等とは完全に独立して行われるものでなければなりません。
11.不当な給付内容の変更・やり直し
不当な給付内容の変更・やり直しとは、発注の取消し、発注内容の変更を行うほか、受領後にやり直しや追加作業を行わせる際、下請事業者が負担する費用を親事業者が負担しないことを指します。
ただし、下請事業者が納品した物品等に欠陥があった場合や、追加注文した内容につき、親事業者が正当な対価を支払ったにもかかわらず、下請事業者が応じない場合は適法です。
取引記録の作成・保存義務
親事業者は、給付内容、下請代金の金額等、取引に関する記録を書類として作成し、2年間保存する義務を負います。
記録内容は下記の通りです。
- 下請事業者の名称(番号,記号等による記載も可)
- 製造委託,修理委託,情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日
- 下請事業者の給付の内容
- 下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は,役務が提供される期日・期間)
- 下請事業者から受領した給付の内容及び給付を受領した日(役務提供委託の場合は,役務が提供された日・期間)
- 下請事業者の給付の内容について検査をした場合は,検査を完了した日,検査の結果及び検査に合格しなかった給付の取扱い
- 下請事業者の給付の内容について,変更又はやり直しをさせた場合は,内容及び理由
- 下請代金の額(算定方法による記載も可)
- 下請代金の支払期日
- 下請代金の額に変更があった場合は,増減額及び理由
- 支払った下請代金の額,支払った日及び支払手段
- 下請代金の支払につき手形を交付した場合は,手形の金額,手形を交付した日及び手形の満期
- 一括決済方式で支払うこととした場合は,金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとした額 及び期間の始期並びに親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払った日
- 電子記録債権で支払うこととした場合は,電子記録債権の額,下請事業者が下請代金の支払を受けることができることとした期間の始期及び電子記録債権の満期日
- 原材料等を有償支給した場合は,品名,数量,対価,引渡しの日,決済をした日及び決済方法
- 下請代金の一部を支払い又は原材料等の対価を控除した場合は,その後の下請代金の残額
- 遅延利息を支払った場合は,遅延利息の額及び遅延利息を支払った
違反行為の取締り
公正取引委員会や中小企業庁では、下請取引が公正に行われていることを確認するため、毎年、親事業者・下請事業者に対する定期調査を実施しています。
(1) 違反行為があった場合
公正取引委員会は、親事業者が下請法に違反した場合、差止め・原状回復請求、再発防止措置の実施を勧告し、勧告した旨を公表します(下請法 第7条~第9条)
(2) 罰則規定
親事業者の行為が下記に該当する場合、違反者個人・親事業者である法人に対し、最高50万円の罰金が科されます(下請法 第10条~第12条)
- は中内容等を記載した書面の交付義務違反
- 取引内容を記載した書類の作成・保管義務違反
- 報告徴収に対する報告拒否・虚偽報告
- 立入検査の拒否、妨害、忌避
下請けに関する相談窓口
下請けに関するご相談は、弁護士、司法書士、行政書士等の専門家のほか、下記窓口で受け付けています。
| 担当課 | 所在地 | ||
|---|---|---|---|
| 公正取引委員会 事務総局 経済取引局 取引部 企業取引課 | 〒100-8987 千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟 | 電話 | 03(3581)337(直) |
| FAX | 03(3581)1800 | ||
| 中小企業庁 事業環境部 取引課 | 〒100-8912 千代田区霞が関1-3-1 | 電話 | 03(3501)1732(直) |
| FAX | 03(3501)1504 |
外注前に確認すべき下請法の内容、注意点まとめ
当ページでは、外注前に確認すべき下請法の内容と注意点を解説しました。