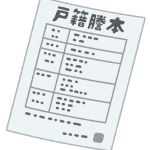当サイトの一部に広告を含みます。

当ページでは、離婚時の親権決定方法、注意点を解説します。
Contents
親権とは
親権とは、未成年の子について、監護・教育・財産管理・法律行為の代理等の権利を指し、下記に大別されます。
- 身上監護権
- 財産管理権
- 身分行為の代理権
親権は、父母の婚姻中は父母が共同して行う「共同親権」を原則としますが(民法 第818条第3項)、離婚後は一方のみが親権を取得することになります。
1. 身上監護権
身上監護権とは、民法 第820条から第823条に定められるものをいいます。具体的には、下記の通りです。
| 監護教育権 (第820条) | 子の利益のために、子の監護 及び 教育をする権利と義務 |
| 居所指定権 (第821条) | 子の生活場所を指定できる権利 |
| 懲戒権 (第822条) | 子の監護 及び 教育に必要な範囲において、その子を懲戒できる権利 |
| 職業許可権 (第823条) | 子の職業について、許可・取消し・制限できる権利 |
2. 財産管理権
親権のうち、財産管理権とは、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為につき、その子を代表する権利を指します(民法 第824条)
ただし、その子の行為を目的とする債務を生じる場合、子 本人の同意が必要です。
3. 身分行為の代理権
一定の身分行為について、親権者には法定代理人として代理権が認められます。
本来は自己決定に関する内容ですが、子の利益のために必要がある場合に限り、認知の訴え(同法 第787条)や、養子縁組の承諾(同法 第797条)等が認められます。
離婚時の話し合いでの注意点
両親が離婚する場合、いずれか一方を親権者と定める必要があります。
このため、離婚前に話し合わなければなりませんが、できる限り、冷静な話し合いを心がけましょう。
財産分与・慰謝料請求等に関する取り決めは離婚後でも構いませんが、親権者は、離婚時に決定しなければならない点に注意しましょう。
親権者が決まらない場合の対処法
親権者が決まらない場合、下記の方法を検討しましょう。
- 離婚調停
- 離婚審判・訴訟
1. 離婚調停
離婚調停とは、裁判官と調停委員の力を借り、話し合いによる解決を目指す方法です。
2. 離婚審判・訴訟
離婚調停での話し合いが決裂した場合、審判 または 訴訟に場を移し、親権を争うことになります。
原則、調停手続を経なければ訴訟は起こせない点に注意しましょう。
離婚時の親権者決定基準
家庭裁判所が親権者を指定する場合、下記の事情を考慮します。
| 親について | (1) 年齢 (2) 職業・収入 (3) 履歴(学歴、職歴、犯罪歴、婚姻歴等) (4) 健康状態 (5) 性格 (6) 生活態度 (7) 監護の実績 (8) 居住環境・教育環境 (9) 子と接する時間 (10) 監護を協力援助する親族の有無 (11) 兄弟姉妹が一緒に暮らせる可能性 (12) 監護を希望する動機 (13) 養育方針 (14) 子への愛情 (15) 面会交流への姿勢 など |
| 子について | (1) 年齢 (2) 性別 (3) 健康(身体的・精神的) (4) 性格 (5) 兄弟姉妹との関係 (6) 学校・交友関係 (7) 非監護者との交流等 現状に対する順応 (8) 親権者が変わることによる影響 など |
上記のほか、子が15歳以上の場合、家庭裁判所は陳述を聴く必要があります(家事事件手続法 第169条第2項)
また、調停・審判手続において、子の意思を把握するよう努め、子の年齢・発達の程度に応じ、その意思を考慮する義務を負います(家事事件手続法 第65条 / 第258条)
(1) 監護態勢について
監護態勢について、収入が多ければ子を養育できるわけではありません。
また、どんなに愛情深くても金銭的に不安定な場合には、父母だけでなく、周囲のサポート態勢まで勘案して指定されることになります。
(2) 現状維持を優先
家庭裁判所は、指定する親権者により 子の監護環境に大きな影響を及ぼす場合、新たな環境が現状よりも優れている等の事情がない限り、原則、現状維持を優先する傾向にあります。
この辺りは、一概に結論づけることが難しく、個々の事情を勘案した指定がなされることになります。
(3) 兄弟姉妹は一緒が理想
家庭裁判所は、特別な事情がある場合を除き、幼い兄弟姉妹が離れて暮らす選択をしません。
この場合、兄弟姉妹同士の年齢や環境を考慮して決定されますし、絶対にバラバラにならないとも言い切れません。
(4) 面会交流について
家庭裁判所は、親権者になる側が、他方の親との面会交流に協力的であるかを確認します。
両親の間に事情はあれど、面会交流は子のために行うものであり、相手を尊重する姿勢がない場合は親権者として不適格と判断される可能性があります。
面会交流を拒絶するだけの事情がある場合は別です。
(5) 子の意思について
子が15歳以上の場合、本人の陳述を聴く義務がありますが、10歳以上で、ある程度の意思表示ができる場合は、本人の意思が反映される可能性があります。
ただし、必ず反映されるものではなく、あくまでも判断基準の一要素に過ぎない点には注意しましょう。
離婚時の親権決定方法、注意点 まとめ
当ページでは、離婚時に定めるべき親権の決定方法、注意点を解説しました。