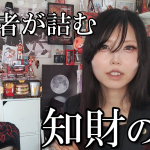当サイトの一部に広告を含みます。

当ページでは、住宅宿泊事業に関し、頻出傾向にある質問と回答をご紹介します。
Contents
- 1. 共通事項・制度関連
- 2. 住宅宿泊事業関連
- 2-1. 新築のマンション・戸建住宅でも、住宅宿泊事業を行うことはできますか。
- 2-2. トレーラーハウスにより民泊を実施する場合、旅館業法が適用されますか。
- 2-3. トレーラーハウスは、住宅宿泊事業法上の住宅に該当しますか。
- 2-4. 台所にシンクは必要ですか。
- 2-5. 「台所」「浴室」「便所トイレ」「洗面設備」のいずれかの設備を複数の届出住宅で重複して利用することは可能ですか。
- 2-6. 届出者の住所地が届出住宅と異なる場合、「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」に該当しませんか。
- 2-7. 居住要件に「事業の用に供されていない」とありますが、お金をもらっていなければ営利性なく、事業に該当しないと判断されますか。
- 3. 事業の定義
- 4. 届出方法
- 4-1. アパート・マンションは全体で1つの届出をするのですか。
- 4-2. 管理業者が決まらないと届出はできませんか。
- 4-3. 登記されていない住宅は届出できませんか。
- 4-4. 建築基準法上の用途が事務所である施設を、住宅宿泊事業として届出したい場合、用途変更は必要ですか。
- 4-5. 共有状態にある建物を住宅として届け出る場合、共同所有者の承諾は必要ですか。
- 4-6. 管理規約がないマンションの届出は可能ですか。
- 4-7. 登記簿の業務内容に住宅宿泊事業を加える必要はありますか。加える場合、どのような文言で記載しますか。
- 4-8. 届出者が外国人の場合、添付書類はどうなりますか。
- 4-9. 届出時に消防法令適合通知書の提出は必須ですか。
- 5. 変更・廃止の届出
- 6. その他
- 7. 宿泊者名簿
- 8. 標識の掲示
- 9. 宿泊実績の定期報告
- 10. 管理業者・仲介業者への委託
- 住宅宿泊業に関するFAQ
1. 共通事項・制度関連
1-1.「民泊」には、どのようなものがありますか。
一般的に「民泊」と呼ばれるものには、住宅宿泊事業法に基づいた届出をするもの以外に、旅館業法に基づく許可を取得しているもの、特定の自治体で特区民泊の認定を得ているものが含まれます。
1-2. 住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理事業者、住宅宿泊仲介業者を兼ねることはできますか。
可能です。
ただし、各業種に必要な届出、登録等を行う必要があります。
1-3. 「家主居住型」「家主不在型」の違いは何ですか。
住宅宿泊事業法において、これらの分類・定義はされていないものの、一般的な特徴は下記のとおりです。
| 家主居住型 | 宿泊者が滞在する間、家主が届出住宅にいる場合 |
| 家主不在型 | 住宅宿泊管理業者に委託し、宿泊者が滞在する間に家主が不在となる場合 |
1-4. オンラインによる届出・登録はどうやって行いますか。
「民泊ポータルサイト」より、「民泊制度運営システム」にログインし、必要な手続きを行います。
1-5. 自治会等の規則により、住宅宿泊事業を禁止できますか。
禁止規定を置くことは可能ですが、住宅宿泊事業法による効力発生は認められません。
要するに、強制力を持たない規定となります。
2. 住宅宿泊事業関連
2-1. 新築のマンション・戸建住宅でも、住宅宿泊事業を行うことはできますか。
住宅宿泊事業法による民泊は、「人の居住の用に供されている家屋」で実施することが求められます。
このため、家屋が新築・中古かに関わらず、下記のいずれかに該当する必要があります。
- 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
- 入居者の募集が行われている家屋
- 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
民泊専用物件の場合、マンション・戸建等の建物自体の形態等に関わらず、上記の該当せず、住宅宿泊事業上の民泊を行うことはできない点に注意が必要です。
2-2. トレーラーハウスにより民泊を実施する場合、旅館業法が適用されますか。
旅館業法が適用される可能性はありますが、トレーラーハウスだからという理由のみで適用対象となる法律が異なるわけではありません。
旅館業法の対象となるのは、下記に該当する場合です。
- 住宅の貸付期間が1か月未満
- 貸室業を営業する意思を対外的に明示せず、貸室業を行う前提での利用者の募集を継続的に実施していない場合
- 上記1、2に該当しない場合でも、1か月に到達する前に当該サービスの提供終了を繰り返す場合
- 住宅の貸付期間が1か月以上の場合でも、部屋の清掃、寝具類の提供等を施設提供者が行うなど、施設の衛生上の維持管理責任を施設管理者がもつ場合 など
2-3. トレーラーハウスは、住宅宿泊事業法上の住宅に該当しますか。
該当する可能性はあります。
トレーラーハウスについて、土地に定着する状態である場合、屋根・壁があるものなので、住宅宿泊事業法第2条第1項の「家屋」に該当する可能性があります。
住宅宿泊事業法 第2条(定義)
この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。
- 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。
- 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。
2-4. 台所にシンクは必要ですか。
必要です。
台所を洗面設備とみなすことができる可能性もありますが、給排水以外にも、調理・洗面それぞれの機能が必要となります。
2-5. 「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」のいずれかの設備を複数の届出住宅で重複して利用することは可能ですか。
複数の届出にて、1つの住宅を重複して届け出ることは認められません。
2-6. 届出者の住所地が届出住宅と異なる場合、「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」に該当しませんか。
住民票に記載される住所地が届出住宅の住所と異なる場合でも、「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」として認められる可能性はあります。
当該要件への該当性は、住民票等の記載のみではなく、実態に応じた判断がなされます。
2-7. 居住要件に「事業の用に供されていない」とありますが、お金をもらっていなければ営利性なく、事業に該当しないと判断されますか。
お金をもらっていない事実のみで、事業の用に供されていないとの判断がされるとは限りません。
法令上、事業に関する定義は置かれていませんが、一般的には、社会性、営利性、反復継続性等の面から判断されることになります。
3. 事業の定義
3-1. どのようなサービスを提供するものが住宅宿泊事業に該当しますか。
宿泊料を受け、住宅に人を宿泊させるサービスを提供する場合、住宅宿泊事業に該当する可能性があります。
3-2. 「宿泊料」ではなく、「体験料」等の名目で料金を徴収すれば、住宅宿泊事業法の届出は不要ですか。
原則、旅館業法に基づく許可が必要かどうかで判断します。
宿泊料とは、その名目を問わず、実質的に寝具・部屋の使用料とみなされるものを指し、旧軽量、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、水道光熱費、室内清掃費等が含まれます。
このため、これらの費用を徴収し、人を宿泊させる営業を行う場合には、住宅宿泊事業法に基づく届け出が必要となる可能性が高いといえます。
3-3. 旅館業法の許可との違いは何ですか。
原則、旅館業法に基づく許可の取得が必要な宿泊事業が、住宅宿泊事業法の定義に該当する場合、届出を行うことにより、旅館業法の許可を得ず、宿泊事業を行うことができます。
旅館業法の簡易宿所は、年間の営業日数に制限はありませんが立地規制があり、住宅宿泊事業法では、立地規制がない代わりに、年間の営業日数を180日以下に制限されるなど、それぞれ異なるルールが敷かれています。
3-4. 旅館業の許可を取得している施設につき、住宅宿泊事業の届出はできますか。また、反対も可能ですか。
旅館業許可を取得している施設について、住宅宿泊事業の届出をすることはできません。
反対に、住宅宿泊事業の届出住宅について、旅館業許可を取得することは可能ですが、許可取得後は住宅宿泊事業ではなく、旅館業として取り扱われることになります。
住宅宿泊事業法において、事業を廃止したときから31日以内に届出が必要な点には注意が必要です。
3-5. 事業者が変わった場合、180日制限は引き継がれますか。
原則、引き継がれます。
年間営業日数の上限180日規定は、届出住宅を基準に算出されます。
このため、年間の途中で住宅宿泊事業者に変更があった場合でも、180日の算定は引き継がれることになります。
宿泊実績の確認は、届け出先の自治体で可能です。
4. 届出方法
4-1. アパート・マンションは全体で1つの届出をするのですか。
アパート・マンションの届出については、各住戸ごと、または 全体で1つの届出をすることも可能です。
届出住宅の範囲は、「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」をそれぞれ含む範囲を最小単位として扱うため、これらが揃っていれば範囲は自由に選択することができます。
4-2. 管理業者が決まらないと届出はできませんか。
管理業者への委託が必要な場合に該当するとしても、届出時に管理業者が決まっている必要はなく、届出自体は可能です。
この場合、届出時点で管理業者が決まらなくても、実際の事業開始日までに管理業者と管理受託契約を締結し、変更届を提出することになります。
4-3. 登記されていない住宅は届出できませんか。
原則、できません。
届出事項には、不動産番号が含まれ、登記しなければ当該要件を満たすことができません。
ただし、住宅を登記しても不動産番号が付与されていない場合には、地番・家屋番号を代替使用し、物件を特定することで届出ができる可能性があります。
4-4. 建築基準法上の用途が事務所である施設を、住宅宿泊事業として届出したい場合、用途変更は必要ですか。
必要です。
現在、建築基準法上の用途が「住宅」「長屋」「共同住宅」「寄宿舎」以外の施設につき、当該施設の一部を住宅宿泊事業法の届出住宅としたい場合、これらへの用途変更が必要です。
一方で、建物全体については「住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの」とすることも可能です。
4-5. 共有状態にある建物を住宅として届け出る場合、共同所有者の承諾は必要ですか。
住宅種k箔事業法において、共同所有者の承諾は必要とされていません。
ただし、トラブル等を防止する目的から、共同所有者間での権利関係等の整理を行ってから届出を行うことをオススメします。
4-6. 管理規約がないマンションの届出は可能ですか。
可能です。
規約がないマンションについて、専有部分の用途を限定されていないと解釈できるため、当該マンションは「住宅宿泊事業を禁止する旨の定めはない」として扱われます。
これにより、届出時には「規約に住宅宿泊事業を営むことを禁止する旨の定めがない場合」として手続きを行いましょう。
4-7. 登記簿の業務内容に住宅宿泊事業を加える必要はありますか。加える場合、どのような文言で記載しますか。
住宅宿泊事業法において、登記簿の業務内容に当該事業が追加されていることは求められていないため、必須ではありません。
登記簿の業務内容については、会社法に基づき、必要な対応を行いましょう。
追加する場合の文言に指定はありませんが、「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業」等が考えられます。
4-8. 届出者が外国人の場合、添付書類はどうなりますか。
届出者が外国人の場合、下記のいずれかにより取得した書類を添付します。
- 当該国において、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないこと(以下、当該事項という。)を証明する制度がある場合、当該事項を証する書類
- 当該国に制度がない場合、当該事項を記載した書類に、当該国における公的機関の認証を受けた書類。
例えば、アメリカの場合、アメリカの公証役場または在日大使館・領事館において認証を受けた宣誓供述書(Affidavit) - 日本の公証役場において、当該事項を記載した書類に、公証人の宣誓認証を受けた書類
4-9. 届出時に消防法令適合通知書の提出は必須ですか。
必ずしも必要なわけではありませんが、都道府県知事は提出を求めるよう、住宅宿泊事業法施行要領にて定められているため、そのように指導される可能性はあります。
当該通知書は、事業を行うにあたって消防法令に適合していることを示すものなので、当事務所でも取得をオススメさせていただいております。
消防法令に適合しない状態で民泊事業を開始した場合、下記のリスクが考えられます。
- 火災発生時、宿泊者の安全を守るために必要な設備の設置、防火管理体制が適切に行われず、宿泊者の人命が損なわれる可能性がある
▶火災が発生しても、火災警報が鳴らない、消火器がない、避難口がわからない等により、初期消火や避難が遅れる危険性が高い - 消防用設備等や防火管理体制に不備があることについて、消防署からの行政指導、行政処分の対象となる可能性がある
5. 変更・廃止の届出
5-1. 届出後、管理規約が変更された場合にはどうなりますか。
マンション等の住宅を届出した後、管理規約等が変更された場合、管理組合に対し、必要な対応をとる必要があります。
住宅宿泊事業の営業を禁止される変更があった場合には、事業廃止の届出を自治体に行わなければなりません。
5-2. 事業者が変更する場合、何をすればいいですか。
事業者が変更となる場合、現行の事業者が事業廃止届出を行い、新たな事業者が新規届出を行う必要があります。
5-3. 将来的に住宅宿泊事業を継続する見込がなく、事業を辞める場合の手続を教えてください。
事業を廃止する場合、廃止した日から30日以内に事業廃止届出を行う必要があります。
実務上、届出住宅に人を宿泊させていない場合でも、事業廃止の届出を行うまで、定期報告等の義務は継続する点に注意しましょう。
6. その他
6-1. マンションで住宅宿泊事業を行う場合の留意点はありますか。
マンションの場合、管理規約等で住宅宿泊事業の営業が認められるかどうかを確認する必要があります。
規約に住宅宿泊事業に関する規程がない場合には、管理組合に確認し、当該確認書類を添付しなければなりません。
6-2. 借家で住宅宿泊事業を行う場合の留意点はありますか。
借家で住宅宿泊事業を行う場合、賃貸人からの承諾書等を得る必要があります。
賃貸借契約上、天体が認められる場合でも、「住宅宿泊事業を行うことが可能」と明記されていなければ、承諾を示す書類が必要となります。
6-3. 近隣住民への説明・許可は必要ですか。
住宅宿泊事業法において、近隣住民への説明・許可は要件となっていませんが、トラブル回避の目的から、ガイドライン内で事前説明を推奨されています。
説明内容についても規定はありませんが、一般的には下記事項を説明するのが望ましいでしょう。
- 事業を実施する者の氏名(法人の場合は商号または名称)
- 住宅の所在地
- 事業内容
- 苦情等の問い合わせ窓口
- 廃棄物処理の方法 など
6-4. 届出をすると氏名、住所が公表されますか。
自治体により運用が異なりますが、公表されると考えていただいて差し支えありません。
ガイドラインにおいて、宿泊者や近隣住民が住宅宿泊事業の届出状況を確認できるよう、公表が推奨されています。
7. 宿泊者名簿
7-1. 宿泊者名簿の備付について、具体的にはどのようなものを備え付ければいいですか。
宿泊者名簿は、宿泊契約ごとに下記の事項を記載する必要があります。
- 宿泊者の氏名、住所
- 職業
- 宿泊日
- 日本国内に住所のない外国人の場合、国籍と旅券番号 など
7-2. 廃業後、宿泊者名簿はどうすればいいですか。
住宅宿泊事業を廃業後について、最低でも3年間は保存しましょう。
宿泊者名簿は、作成日から3年間の保存が義務づけられています。
廃業が、住宅宿泊事業から旅館業への移行である場合、住宅宿泊事業に関する記載内容が確認できる状態であれば、旅館業における宿泊者名簿として転用が認められる場合があります。
7-3. 宿泊者の本人確認とは、どのようなものですか。
宿泊者の本人確認とは、宿泊者名簿に正確な記載をするため、宿泊開始までに、宿泊者それぞれを対象に実施する本人確認を指します。
本人確認の方法について、対面、または下記を満たすICTによる方法等が考えられます。
- 宿泊者の顔・旅券が画像により鮮明に確認できること
- 当該画像が住宅宿泊事業者や営業所、届出住宅内、届出住宅の近傍から発信されていることが確認できること
- 届出住宅等に備え付けたテレビ電話・タブレット端末等による確認
スマートフォン等の機器による本人確認は、レンズの破損、充電不足等、住宅宿泊事業者の管理の及ばない要因により、適切な業務遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、必ず、住宅宿泊事業者が適切な代替措置を用意する必要があります。
7-4. 宿泊者が在日の米軍人等の場合、どのように本人確認を行えばいいですか。
米軍人の場合、身分証明書としてミリタリーID等による本人確認を行うことになります。
ただし、ミリタリーIDの写しや、番号を記載するのは控えましょう。
8. 標識の掲示
8-1. 標識はどこでもらますか。
各自治体により運用が異なり、自治体から支給される場合もあれば、ご自身で用意していただく場合もあります。
標識には、届出番号、住宅宿泊事業者等の連絡先等の正確な記載を確保し、届出を受け付けた都道府県等が長の名称を記載したものを発行することが規定されています。
8-2. 休業中は標識を外しても構いませんか。
休業中、賃貸物件に人が入居している期間中も、事業の廃止を行わない限り、届出住宅への標識掲示は必要です。
9. 宿泊実績の定期報告
9-1. 都道府県知事への定期報告は、どのようにすれば良いですか。
都道府県知事への定期報告は、原則、民泊制度運営システムを利用して行います。
毎年、2・4・6・8・10・12月の15日までに、前2か月分について、下記を報告します。
- 届出住宅にに人を宿泊させた日数
- 宿泊者数
- 延べ宿泊者数
- 国籍別の宿泊者数の内訳
9-2. 延べ宿泊者数とは何ですか。
延べ宿泊者数とは、実際に届出住宅に宿泊した宿泊者について、「1日宿泊するごとに1人」と算定した数値を合計したものを指します。
例えば、宿泊者1人が3日宿泊すれば3日ですが、宿泊者3人が3日宿泊すると9日となります。
9-3. 報告対象の期間中に、宿泊実績がない場合は報告不要ですか。
必要です。
9-4. 国籍別の宿泊者数について、日本に居住する外国人はどこに分類しますか。
日本に住所がある外国人は「日本」に分類します(官公庁「宿泊旅行統計調査」の算定方法による)
反対に、日本に住所がない日本人は「その他」に分類します。
10. 管理業者・仲介業者への委託
10-1. 住宅宿泊管理業務を管理業者に委託する場合、事業者に一部のみを任せることは可能ですか。
原則、認められません。
住宅宿泊事業法 第11条に基づいた委託は、管理業務を一括して委託することを要件とし、一部のみを委託せず、事業者自らが行うことはみとめられません(住宅宿泊事業法 第11条)
ただし、一括委託をしたうえで、当該管理業者のもと、事業者自らがその一部を「手伝う」ことは差し支えありません。
住宅宿泊業に関するFAQ
当ページでは、住宅宿泊業に関し、よくある質問をご紹介しました。