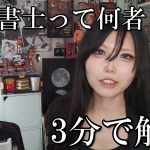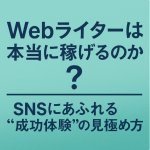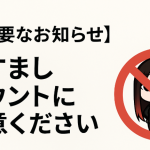当サイトの一部に広告を含みます。
Contents
関連投稿
はじめに
行政書士に業務を依頼するというのは、多くの場合、人生の節目や決断のタイミングに関わる出来事です。
たとえば、会社を立ち上げようとするとき、親の相続を考え始めたとき、副業をきちんと形にしたいと思ったとき。
こうした「これから」の局面で、行政書士がサポートに入る場面は少なくありません。
しかし、「行政書士に依頼すると、実際にどうなるのか?」という点については、なかなか想像しづらいのが現実です。
専門家に依頼する価値は、結果が出て初めて実感できるものでもあります。
本記事では、実際に行政書士に依頼をされた方々のケーススタディを通じて、どのような背景から依頼に至り、行政書士がどのように関わり、結果として何が得られたのかを、可能な限り具体的にご紹介いたします。
この記事をお読みいただくことで、将来的に「依頼される立場」として活動することを考えていらっしゃる方にも、“行政書士の仕事がどのように人の転機と関わるのか”を実感していただければ幸いです。
「でも、本当に行政書士にお金を払うだけの価値ってあるの?」
そう感じるのは、ある意味とても自然なことです。
依頼の判断を誤れば、時間もお金も無駄になりかねません。
そんな疑問に真正面から向き合い、「どこまでが自力で、どこからが依頼すべきか」を明確にした記事をこちらにまとめています:
👉 行政書士にお金を払う意味があるのか|判断基準と損失回避の戦略
依頼するかどうか悩むすべての方に読んでいただきたい、実務者視点の“損しない選択”ガイドです。
第1章:会社員から独立へ:建設業許可を取得したAさんのケース
Aさんは40代の技術系会社員。長年、建設現場で実務を積んでこられた方でした。
勤め先では主に下請け業務を担当しており、工事の実質的な管理を任されることも多かったそうですが、あるとき「いっそ自分でやってみたい」という思いが強くなり、独立を決意されました。
とはいえ、建設業で独立するとなれば、最初に立ちはだかるのが「建設業許可」の取得です。
元請け案件の受注には許可がほぼ必須とされるため、Aさんも早い段階でこの申請を見据えて動き始めました。
依頼の経緯と行政書士の関わり
Aさんからご相談をいただいた当初、すでに「独立後に許可を取る」という方針は明確になっていました。
ただし、許可取得のための要件確認や、必要書類の収集・整理にあたり「何から手を付ければよいのか分からない」とお悩みの様子でした。
当事務所ではまず、Aさんのご経歴と勤務実績をもとに、技術者要件・財産的要件などの該当性を丁寧に確認し、不足している書類や準備すべき資料についてリストアップを行いました。
そのうえで、申請書類の作成、添付資料の精査、行政対応の代行まで一貫してサポートを実施いたしました。
結果とその後
結果として、Aさんは予定よりも1ヶ月ほど早く建設業許可を取得することができました。
その後、元勤務先と新たに元請け契約を締結し、自身が代表を務める事業者として初めての案件を受注。
「最初の一歩をしっかりと踏み出すことができた」と喜びの声をいただいております。
「自分で調べて申請しようとしたとき、正直、書類の山を前にして心が折れかけました。あのとき専門家にお願いして本当によかったと、今も思います」(Aさん・談)
第2章:遺言書作成支援で家族が救われたBさんのケース
Bさんは地方にお住まいの30代男性。
ご自身は都市部で勤務されていましたが、ご実家は地方にあり、両親の高齢化に伴い、そろそろ相続や介護についても視野に入れる必要が出てきたタイミングでした。
特に気がかりだったのは、お父様の所有する不動産や預貯金といった財産の分け方。
ご兄弟が複数いらっしゃることもあり、「何となくモヤモヤしたまま放置すれば、将来トラブルになるかもしれない」と感じておられたそうです。
依頼の経緯と行政書士の関わり
Bさんからのご相談は、「父に遺言書を作ってもらいたいが、どう話を切り出せばよいか分からない」というものでした。
家族間で相続の話をすることには、心理的なハードルがあるのが普通です。
当事務所では、まずBさんご本人と面談を行い、ご家族の構成やご実家の財産内容、お父様のご意向などを丁寧にヒアリングしました。
そのうえで、お父様への説明の仕方や、遺言作成の必要性・メリットについて一緒に整理し、実際にご家族との話し合いに臨まれる前に、文案のたたき台を複数ご提示しました。
最終的には、公正証書遺言として正式に作成され、証人の手配や公証人との調整も当事務所で行わせていただきました。
結果とその後
遺言作成後まもなくして、お父様はご病気のため他界されました。
突然のことではありましたが、すでに法的効力を持った遺言書が用意されていたことで、不動産の名義変更や預貯金の手続きも円滑に進み、相続人であるご兄弟間においても、特にトラブルは起こらなかったとのことです。
「正直、遺言書のことを“まだ早い”と感じていたのは、僕のほうでした。でも、亡くなってから家族で争うより、今、ちゃんと準備しておけて本当によかったと思います」(Bさん・談)
第3章:副業を始めたCさんの「契約書整備」支援
Cさんは40代の会社員。コロナ禍以降の働き方の変化を受け、将来的な独立も視野に入れた副業をスタートされました。
最初は知人の紹介で始めた小規模なコンサルティング業務でしたが、徐々に外部との関係性が複雑になり、契約内容の不明確さが不安材料となっていったそうです。
「今は信頼できる相手でも、将来トラブルになったら…」
そんな思いがきっかけとなり、当事務所にご相談をいただきました。
依頼の経緯と行政書士の関わり
Cさんからのご相談は、「契約書の雛形を用意したい」というものでしたが、詳しくお話を伺うと、単なるテンプレートではなく、実際の業務内容や今後の関係性の変化も見据えた形で整備する必要があると判断しました。
当事務所では、まず現状の取引形態や業務分担、報酬の支払い方法などを整理し、トラブルになりやすい論点を洗い出しました。
そのうえで、Cさん専用の契約書をゼロから設計し、内容の意味やリスクも逐一ご説明しながら、合意形成に向けた調整のサポートも行いました。
特に、解約条項や損害賠償に関する項目は、事後トラブルの抑止力として重要視しました。
結果とその後
契約書締結から半年後、Cさんと知人との事業は一旦終了することとなりました。
しかし、契約書に解消時の条件が明確に記載されていたことから、双方が納得したうえで、円満に関係を終了できたとのことです。
「あのとき契約書をきちんと整備していなければ、今ごろ“言った・言わない”で揉めていたかもしれません。お願いして本当によかったです」(Cさん・談)
おわりに
ここまで、行政書士に業務を依頼された3つのケースをご紹介してまいりました。
建設業許可、遺言書作成、契約書整備。
いずれも「人生の転機」や「新たな挑戦」に伴う局面において、行政書士がその背中をそっと押すような役割を担った事例です。
行政書士の業務は、単に「書類を作る」だけではありません。
手続きに必要な要件を整理し、リスクを見越して準備を整え、本人の想いや意図を汲み取りながら形にしていく。
その過程には、書類の向こうにある“人の事情”を理解する姿勢が欠かせません。
そしてこの記事を読んでくださっているあなたが、今後「依頼される側」になるとしたら。
どんな人の、どんな場面に寄り添い、どのような価値を届けられるのか。
ぜひ、実際の事例をヒントに、ご自身の未来像を思い描いていただければ幸いです。
実際の行政書士業務について、もっとリアルな現場を知りたい方は
🎥【再生リスト】仕事になる?行政書士のリアルな現場まとめ
👉 https://www.youtube.com/playlist?list=PLMxpu0YEc7tul-Sjcehd4LffsBrXtQv-P
にて、ケース別に解説した動画をご覧いただけます。
また、行政書士として「依頼される立場」になるためのSNS戦略や導線設計については、
✍️【noteマガジン】仕組みで回すSNS戦略マガジン|発信×導線×売上化
👉 https://note.com/bokiko_gyosho/m/m18ce8cdbede7
にて、実践的なノウハウを発信しています。