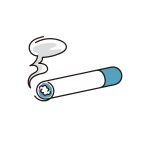当サイトの一部に広告を含みます。
育児休業給付金とは、会社員など雇用保険に加入している労働者が、育児休業中に受け取れる給付制度です。
給与が支払われない期間の生活を支える目的で設けられているものの、同じように働いている個人事業主やフリーランスは対象外となります。
なぜ、このような差が生まれるのでしょうか。
本記事では、育児休業給付金の仕組みと支給要件を整理しつつ、個人事業主が制度の外に置かれる理由、そしてその場合に取るべき選択肢について解説します。
Contents
関連投稿
第1章 育児休業給付金の仕組みと支給対象
育児休業給付金とは、雇用保険の被保険者(加入者)を対象とした制度です。
育児休業中、会社から給与が支払われない場合に、生活を支える目的で国(雇用保険)から支給されます。
支給対象となるには、主に次の条件を満たす必要があります。
- 育児休業前の2年間、雇用保険に加入し、11日以上働いた月が1年以上あること
- 育児休業開始時点において、育児休業終了後に離職予定がないこと
また、育児休業中に一部就業する場合でも、以下の要件を満たせば支給対象となります。
- 育児休業中の賃金が、休業開始時賃金月額の80%未満であること
- 育児休業中の就業日数が月に10日(80時間)以下であること
支給金額は、休業開始から180日までは「休業開始前賃金の67%」、それ以降は「50%」が基本となります。
ただし、上限・下限額があり、収入が多い場合は一部減額、反対に、賃金が少ない場合には最低保障額が適用されます。
このように、育児休業給付金は「雇用関係がある人」だけを支える制度であり、雇用保険に加入していない人は対象外です。
次章では、なぜ個人事業主やフリーランスがこの制度の枠外に置かれているのかを解説します。
第2章 個人事業主・フリーランスが対象外となる理由
育児休業給付金は、雇用保険を財源とする制度です。
そのため、支給を受けるには「雇用されている立場」であることが前提になります。
雇用主と労働者の間に労働契約が存在し、雇用保険料を支払っていることが必要条件です。
一方、個人事業主やフリーランスは、自身が事業の主体であり、雇用契約の相手が存在しません。
自分で自分を雇うことはできないため、制度上、雇用保険には加入できません。
この構造的な違いこそが、育児休業給付金の対象から外れる最大の理由です。
また、会社員が加入する健康保険では「出産手当金」などの所得補償が受けられますが、国民健康保険・国民年金に加入する個人事業主には、同等の給付制度がありません。
つまり、出産や育児により一時的に仕事を休む場合、個人事業主(あるいはフリーランス)は完全無収入となる可能性があるということです。
この現実を前提に、育児期間中の収入減少にどう備えるかを考える必要があります。
次章では、制度の外にいる人が取り得る3つの具体的な選択肢を紹介します。
第3章 制度の外にいる人が取れる3つの選択肢
育児休業給付金を受けられない個人事業主やフリーランスの場合でも、まったく支援策がないわけではありません。
国・自治体・民間それぞれの仕組みをうまく組み合わせることで、育児期間の生活と事業を両立することが可能です。
① 健康保険から受け取れる「出産手当金」
法人成りして社会保険に加入している場合、出産前後の一定期間、出産手当金(標準報酬日額の約2/3)を受け取ることができる可能性があります。
ただし、任意適用事業所に該当しない個人事業主は対象外です。
国民健康保険では出産育児一時金のみとなり、休業中の所得補償はありません。
② 自治体による独自支援・助成制度の活用
近年、自治体レベルで育児と仕事の両立を支援する制度が増えています。
具体的には以下のような補助があります。
- 子育て世帯向けの一時金支給
- ベビーシッター・家事代行の利用助成
- 自営業者を含む親の短時間保育利用支援
こうした制度は自治体により内容が大きく異なるため、居住地+「育児 助成金」「自営業」等のキーワード検索で確認しておくと良いでしょう。
③ 民間制度・自助によるリスク分散
制度外の働き方を選ぶ以上、「収入の止まるリスク」に備える必要があります。
主な対策としては、以下が考えられます。
- 就労不能保険や所得補償保険への加入
- 積立型の事業預金を設ける
- 複数の収益源(広告・コンテンツ販売等)を持つ
つまり、制度に頼るのではなく、あなた自身で設計することが最適解です。
次章では、これらの基礎を踏まえ、育児と収入を両立するための具体的な資金設計と可処分時間の確保について触れます。
詳細なシミュレーションやテンプレートは、別途有料noteにて解説します。
まとめ 制度に守られる働き方と、制度を設計する働き方
育児休業給付金は、会社員や契約社員など「雇用関係にある人」を支える制度です。
対象範囲が明確である一方で、個人事業主やフリーランスはその枠外に置かれています。
つまり、同じように働いていても、「雇われているかどうか」で支援の有無が分かれる仕組みです。
この差は一見 不公平に見えるかも知れませんが、裏を返すと、個人事業主(フリーランス)には制度を自分の手で設計できる自由があるとも言えます。
育児期間中の収入を確保する方法も、外部制度に頼るだけではなく、自分のビジネス構造や可処分時間の設計次第で変えることができます。
育児休業給付金を「受け取れるかどうか」で終わらせるのではなく、「どのように備えるか」「どんな働き方を選ぶか」を考えることが、長期的な安定につながります。
有料noteでは、「育児休業給付金がない人のための、自力で作る休業補填計画」として、可処分所得・可処分時間を守るためのシミュレーション、収支モデル、テンプレートを公開しています。