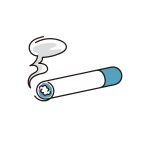当サイトの一部に広告を含みます。
通帳が見つからない──相続の現場では、意外とよくあるご相談です。
「通帳がないと手続ができないのでは」
「そもそも口座の存在を確認する方法がわからない」
と、不安を抱えるご家族も少なくありません。
結論からいうと、通帳がなくても相続手続は可能です。ただし、紙の通帳が前提だった時代と違い、手続の進め方や確認のポイントには少し注意が必要です。
近年は、通帳を発行しない「通帳レス口座」や、オンラインで完結するネット銀行も増えています。
本記事では、こうした“通帳のない時代”における相続手続の進め方を、実務の流れに沿って解説します。
Contents
関連投稿
第1章 通帳レス化が進むいま、相続手続はどう変わる?
かつては「通帳さえ見つかれば、口座も資産もすぐに把握できる」という時代でした。
しかし近年では、通帳を発行しない金融機関が増え、紙の通帳そのものが“オプション”扱いとなりつつあります。
三菱UFJ銀行やみずほ銀行をはじめ、大手各行が紙の通帳を廃止または有料化し、代わりにスマートフォンやインターネットで残高・入出金を確認する仕組みが主流になっています。
こうした流れを受けて、「通帳を探しても見つからない」「そもそも発行していなかった」というケースが、相続手続の現場でも確実に増えています。
紙の通帳がなくなること自体は問題ではありません。
問題になるのは、「どの金融機関に口座があるのか」を家族が把握していないことです。
通帳があれば一目でわかる情報も、デジタル管理になると、本人以外は確認が難しくなります。
たとえば──
- 給与や年金の振込先
- 公共料金や携帯電話の引き落とし口座
- ネット銀行や証券会社など、紙の郵便物が届かない取引先
こうした情報が一切共有されていないと、残された家族は「そもそも口座が存在するか」から調べなければならず、時間も手間もかかります。
通帳レス化によって、相続の第一歩が「書類を探す」から「情報を探す」に変わったともいえます。
この変化を踏まえて、次章では、通帳がない場合の具体的な確認・照会方法を解説します。
第2章 通帳がない場合の相続手続の流れ
通帳がない場合の相続手続は、
①取引先の金融機関がわかる場合
②取引先がわからない場合
の二つに分けて考えると整理しやすいです。
① 取引先の金融機関がわかる場合
被相続人が取引していた金融機関の名称がわかっているなら、まずはその金融機関に直接問い合わせましょう。
支店まで特定できていなくても問題ありません。金融機関側で検索してもらえる場合がほとんどです。
問い合わせ後の一般的な流れは次のとおりです。
- 金融機関へ連絡し、口座の有無や相続手続の案内を受ける
- 指定書類を作成・取得する(戸籍謄本、印鑑登録証明書など)
- 「残高証明書」や「取引履歴証明書」を申請する
- 証明書を受け取り、遺産分割や相続税申告の資料に使う
残高証明書の発行にあたっては、被相続人と相続人の戸籍書類、申請者本人の身分証明書や印鑑証明書などが必要になります。
金融機関によっては、相続関係説明図の提出を求められる場合もあります。
② 取引先の金融機関がわからない場合
取引先がわからない場合は、情報を一からたどる必要があります。
具体的には、次のような手がかりを探します。
- 遺品に含まれる通帳・キャッシュカード・ATMの利用明細
- 勤務先・年金受給口座・公共料金の引き落とし口座
- 故人が生活していた地域の金融機関
- 過去の郵便物やメール通知
これらから金融機関を特定したうえで、「口座の有無確認」または「残高証明書の発行」を申請します。
金融機関は、依頼があれば、被相続人名義の口座が存在するかどうかを調査してくれます。
この手続にはやや時間がかかりますが、通帳がなくても預貯金の有無を確認すること自体は可能です。
第3章 通帳を紛失した場合の注意点
通帳を紛失しても手続自体は可能ですが、いくつかの点で注意が必要です。
特に「費用」と「口座の扱い」に関しては、事前に把握しておくと後の負担を減らせます。
① 手数料などの費用が上乗せされる
金融機関が発行する通帳は、もともと口座名義人本人が管理することを前提としています。
そのため、相続人が通帳を紛失した状態で照会や証明書の発行を依頼する場合、通常の手続にはない費用が発生するケースがあります。
たとえば、
- 取引明細書を過去10年分取り寄せる手数料
- 通帳の再発行にかかる実費
- 追加の本人確認書類の提出
といった対応が必要になることがあります。
また、相続税の申告・納税を行うには、故人の預貯金の動きを確認する目的で、生前から最大10年分の口座取引情報を提出することが求められる場合があります。
通帳があればすぐに確認できますが、紛失していると、金融機関に明細書を発行してもらう必要があり、その分だけ費用も時間もかかります。
② 休眠口座の扱いに注意
一定期間以上取引のない口座は、金融機関で「休眠口座」として管理されます。
この状態でも、相続人が申告すれば手続によって払い戻しを受けることができますが、確認の手間は増します。
誰も気づかぬまま放置すると、最終的には預金保険機構を経由し、国庫に納付される仕組みとなっています。つまり、通帳がないまま休眠状態に入り、存在自体に気づかれなければ、相続財産として受け取れない可能性もあるということです。
③ 通帳をなくしたままにしない工夫
被相続人の通帳を探すことはもちろんですが、自身の将来に備え、
- 取引先 金融機関の一覧を家族に共有しておく
- 通帳レス口座のID・パスワードの保管方法を検討する
- 不要な口座を整理する
といった“デジタル時代の相続準備”を日頃から整えておくことが大切です。
次章では、こうした「通帳レス時代」における相続のあり方と、これからの世代が意識すべき対策をまとめます。
第4章 通帳レス時代の相続に備えるために
通帳がなくても相続手続は進められます。
ただ、通帳レス化やオンライン取引の普及によって、「手続できるか」よりも「どう探すか」「どう残すか」が、これからの相続の焦点になりつつあります。
紙の通帳は姿を消しても、お金の記録そのものが消えるわけではありません。
給与の振込、公共料金の引き落とし、電子マネーの残高、証券口座の履歴──これらはすべて、データとしてどこかに残っています。
問題は、その“入口”を家族が知らないこと。
相続を円滑に進めるためには、以下を日頃から整理し、信頼できる家族に伝えておくと安心です。
- 取引のある金融機関
- 口座のうち、生活費・貯蓄・投資用の区別
- どの情報を、どこに保管しているか
通帳レス化は、利便性を高める一方で、相続を「情報の手続」に変えました。
だからこそ、生前の整理が“最初の相続対策”になります。
関連記事・資料のご案内
関連投稿
さらに詳しい実務対応や、デジタル資産を含めた整理法については、こちらの記事で解説しています。
🔗 有料note:通帳レス時代の相続対策マニュアル
- 故人の口座を見つけるためのチェックリスト
- ネット銀行・証券口座の調査テンプレート
- 家族で共有できる「金融資産メモ」フォーマット付き