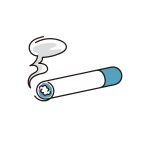当サイトの一部に広告を含みます。
Contents
関連投稿
離婚して家を出たんですが、いちばん辛かったのは”あの子”の寝顔でした。
名前を呼べば、真っ先に駆けてくる。
休日は一緒に散歩し、帰宅すると玄関まで迎えに来てくれた。
そんな我が子のような愛犬も、離婚届を提出した瞬間から「およその子」。会うことすら儘ならない現実があります。
日本の法律では、ペットは家族ではなく「物」として扱われます。
けれど、そのうえでなお、愛犬を取り戻せた方もいらっしゃいます。
本記事では、実際の裁判例や取り戻すために必要な証拠、どうしても取り返せない場合に撮り得る手段に至るまで、あなたが家族を取り戻せるようお伝えしていきます。
🐾第1章:犬は“物”?民法におけるペットの位置づけ
ペットは家族。
それは、感情としては正しくも、法的には通用しないのが日本の現状です。
民法上、ペットは動産=物として扱われる財産です。←冷蔵庫やテレビと同じカテゴリ。
離婚に伴う財産分与の際も、”どちらの所有物か”という観点で扱われます。
たとえば、民法第206条では
(所有権の内容)
第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。出典:e-Gov法令検索
この所有物にペットが含まれます。
つまり、誰のものか=誰が所有しているかが全てで、「情」に関わらず「証拠」で判断されます。
懐いているのは誰かは問題ではない
- 自分になついていた
- 名前を呼べば自分のところに来る
- 相手は世話していなかった
こうした感情ベースの主張では、残念ながら証拠にならないケースがほとんどです。
ただし、モノ扱いであっても実際の飼育実績が重視されるケースもあります。
🐾第2章:“本当に飼っていた”を証明するための証拠とは
犬の登録名義は相手ですが、実際にお世話をしていたのは私なんです。
このような主張が通るかどうかは、証拠の有無にかかっています。
所有権を立証するのに有効な証拠の具体例
1.登録名義・マイクロチップ情報
- 市区町村の畜犬登録の名義
- 狂犬病予防接種の済票
- マイクロチップの登録情報
一見すると、これらの名義人が有利なように思えますが、絶対か?と言われるとそうではありません。
後に名義変更されているケースもあるため、総合判断の一要素にとどまるのが現実です。
2.動物病院・トリミング等の支払記録
- 診察券に記載された飼い主名義
- 治療費や薬代などの支払履歴(領収書・カード明細)
- トリミングやしつけ教室等の予約名義や支払情報
実質的な飼育実態を示す強力な証拠として、誰が責任を持ち、管理・支払いをしていたかが重要視されます。
3.日常的な飼育記録
- 散歩中の写真や動画
- ごはん・おやつをあげている様子
- ペット用SNSアカウントや日記の投稿履歴
- ドッグカメラの録画データ など
細かな記録の積み重ねが、実質的な飼い主を裏付けることとなります。
4.購入契約書・引取り時の証明
- ペットショップやブリーダーとの契約書
- 保護団体との譲渡契約書
- 迎え入れたときの写真・動画・支払記録
最初に迎え入れたのは誰かも、所有権判断の出発点となり得ます。
🐾第3章:実際に争われた“犬の返還請求”裁判例
犬がモノとして扱われる事実は変わりませんが、実際の飼育状況を重視した判決も増えています。
ここでは、実際に裁判所で争われた犬の返還請求の裁判例をご紹介します。
📚実例①:登録名義は妻、でも返還命令が出たケース
あるご夫婦の離婚後、犬は妻のもとに残りました。しかし、夫は「自分が主に世話をしていた」と主張し、返還を求めて訴訟を提起。
主張と証拠
/
| 登録名義 | 妻 |
| 購入費用 | 夫 |
| 医療費支払 | すべて夫のクレジットカード |
| その他 | 散歩、食事の様子を記録した写真・動画を提出 |
判決
裁判所は、「登録名義は形式にすぎない」と判断し、実質的に飼育していたのは夫であると認定。
動産返還請求が認められ、妻に返還を命じる判決が下されました。
📚実例②:名義・飼育ともに妻、返還は認められなかった
こちらも離婚後、元夫が「犬を取り戻したい」と訴えたケースです。
主張と証拠
| 登録名義 | 妻 |
| 購入費用 | 夫 |
| 費用負担 | 医療・トリミング・ご飯代などすべて妻が負担 |
| その他 | 妻名義のSNSアカウントに日々の飼育の様子が投稿されていた |
判決
「購入時点での費用負担だけでは、現在の所有権を否定できない」とし、実質的な管理者は妻と判断された結果、元夫の請求は棄却されました。
このように、裁判所は形式だけでなく、事実関係も重視します。
ポイントは、お金の流れと記録の有無、一貫性です。
🐾第4章:返してくれないとき、取りうる法的手段とは
証拠をそろえたものの、相手が聞く耳を持たず。返してほしいと伝えても無視されている。
このような場合、次に検討すべきは法的手段です。
実際に、ペットの返還を求め、裁判を起こす方もいらっしゃいます。
⚖️ 所有権に基づく「動産返還請求訴訟」
ペットがモノである以上、民事訴訟において、他人に持ち去られた動産を返してもらうのと同じ手段で争うことになります。
必要なもの
- 自分い所有権があることを証明する資料
- 相手が占有(保有)している事実
- 返還を求めたが、応じてくれない証拠(LINEやメール等)
この訴訟では、所有権の立証が最大の争点となります。
🛡️ 緊急性が高い場合:「仮処分」の活用
仮に、相手が犬を第三者に譲渡・売却しようとしているような場合には、回復不能な損害を防ぐために「仮処分の申立て」を行うことも可能です。
たとえば、
- 犬の譲渡先に対し、仮に引き渡しを禁止する命令
- 動物病院での引取りや、保護団体への移転阻止など
ただし、仮処分にはスピード感が求められます。
状況によっては即日、法的措置を検討する必要があります。
🗣️ 話し合いが難しい場合:代理人による交渉
当事者同士では感情的になりやすく、話が進まないケースも多いです。
そうようなときには、弁護士等の第三者を通じた冷静な交渉が望ましいです。
文書により「返還請求書」を送付することで、相手に心理的プレッシャーを与えることもできます。
🐾第5章:取り戻す前に、心に問うべきこと
返してもらえたらそれで終わる。
そう思っていても、いざ争いが始まると心は擦り減ります。
法的に勝てる可能性があるとしても、犬にとって幸せなことなのでしょうか。
そして、あなた自身にとってもそれは、「望んだ結末」と言えますか。
🐶犬にとっても、居場所の変化は大きなストレス
- 環境が変わることで体調不良を引き起こす可能性も
- 高齢犬や病気を抱える子の場合、取り戻すことが負担になることも
- 飼い主の感情と犬の安全、安定した生活、どちらを優先するかの視点を
💔「取り戻す」が目的化していないか?
- 離婚による喪失感や、親権を得られなかった無力感が原動力ではありませんか?
- 単に、相手に「勝ちたい」だけではありませんか?
1歩引いてみると、自分でも気づかなかった感情の暴走に気づくことができるかもしれません。
💬だからこそ、「行動」と「覚悟」はセットで
法的手段をとることで、相手との関係が完全に断たれる可能性があります。
勝っても負けてもあなたのもとに戻るのは、「かつての生活」ではなく、新たな責任と関係性であることを覚えておいてください。
あなたの決断が愛犬にとっても、あなたにとっても、「悔いのない選択」であることを心から願っています。
まとめ
この記事は、YouTubeで公開中の動画「離婚後に犬を取り戻せるか?」をもとに、法的・実務的な観点から掘り下げてお届けしました。
▼動画はこちらからご覧いただけます
🎥【離婚後の愛犬はどっちのもの?犬の所有権を取り戻す法的手段とは】
https://youtu.be/●●●●(仮リンク)
個人的なお知らせを少しだけ
私は今、「愛玩動物看護師学科」への進学を目指しています(今日、AO面談に無事通過しました🌸)
けれど、これがゴールではありません。
これから、入学金・学費を工面しなければならない現実があります。
今までは、亡くなった愛鳥の治療費をメンバーシップで支援していただいていました。
そして次は、「誰かの大切な子」を守れるようになるための学びに進みます。
この活動を「見守るよ」「応援してるよ」と思っていただけたら、ぜひ、YouTubeのメンバーシップにご参加いただけませんか?
特典はありません。
でも、登録してくださったそのひとりひとりの存在が、私の原動力になります。
▼メンバーシップはこちらから
https://www.youtube.com/channel/UCRex_B9uPGOMsofqrxh7ScQ/join