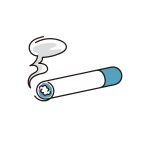当サイトの一部に広告を含みます。
Contents
関連投稿
行政書士の試験勉強をがんばっているあなたへ。
その知識、本当に”現場”で使えますか?
「憲法と行政法は得意です」
「民法も解けます」
これらはあくまで行政書士試験が前提でのお話です。
名前、ロゴ、動画、SNS投稿、ブログ等々、開業した後に問われるのは、“法律の知識”ではなく”使い方”です。
そして、その最初の落とし穴となりうるのが、著作権と商標権です。
第1章|“試験には出ないけれど、必ず聞かれる”知財の実務
行政書士試験では、著作権も商標も、ほとんど出題されません。
そのため、「今は優先度が低い」と判断する受験生も多いでしょう。
ですが、もしあなたが「合格後に実務で食べていく」つもりであれば、この分野を避けて通ることはできません。
なぜなら、開業直後から最も多く寄せられる相談は、「ロゴ」「名前」「デザイン」「発信内容」など、いずれも“表現物”に関するものだからです。
💬たとえば、こんな質問を想定してください
- 「この屋号で開業したいんですが、大丈夫ですか?」
- 「LPにこの写真を使いたいのですが(拾い画を見せながら)」
- 「YouTubeで収益化したいんですけど、この曲使えますよね?」
これらの問いに対して、行政書士として関与する以上、「グレーですね」と濁すだけでは済まされません。
“ちゃんと知っている人”だけが、信用を獲得できるのです。
実務と“試験の論点”は別物
試験勉強で得た知識は、基礎として非常に重要です。
しかし、実務ではそれに加えて「リスクを予測し、回避する知識」や、「法的に問題のある使用かどうかを判断する力」が求められます。
そしてそれは、「勉強しようと思えば、いつでもできる」では通用しない世界です。
“差がつく行政書士”が持っているのは、「知財の勘所」
この分野に詳しい行政書士は、まだ少数派です。
だからこそ、ここを押さえておくことで、他の実務家と大きな差がつきます。
- クライアントの発信内容に関する法的リスクの強度は?
- ロゴや屋号等に関し、商標法上のリスクはないか?
- 外注された制作物の著作権の帰属先は?
これらを見抜けるだけで、「あ、この人は頼りになる」と感じてもらえるのです。
第2章|“知らなかった”では済まされない、知財のトラップ
行政書士が取り扱う法分野には、「知らないと違法になる」ものが数多くあります。
その中でも、著作権と商標は“主観に関わらずアウト”になる点で、特に注意が必要です。
厄介なことに、これらは合格直後の初手で問われる可能性が高いものでもあります。
著作権は「載せただけ」でアウト
画像、BGM、文章、ロゴ、イラスト等、ネット上にあるからといって、自由に使えるわけではありません。
例えば、チラシにフリー素材を使用した場合。
「フリー素材」だからといって、用途に関係なく使えるわけではありません。
商用利用不可のものですと、弁護士から警告書が届き、印刷物をすべて回収しなければならないケースもあります。
商標は「登録すればOK」ではない
たとえ、あなたが商標登録していたとしても、区分の選定ミスや、先行する類似商法次第で無効となるケースがあります。
屋号や商品・サービス名等、ビジネス上、名づけの機会は数多く訪れますが、きちんと調査せずに使用しますと、名刺、ホームページ、SNS等を整備した頃に「その名称は当社の登録商標です」と連絡が届くこともあります。
こうなると、名刺や出版物はすべて廃棄となりますし、ドメインの変更、使用ロゴも差止変更が必要です。また、顧客からの信用は失墜し、追加費用もかかります。
つまり、名前1つでビジネスの根幹が揺らぐ恐れがあるのです。
「たぶん大丈夫」は最大の地雷
最も危険なのは、知識が浅いまま「たぶん大丈夫です」と言ってしまうこと。
あなたの言葉に安心し、クライアントが実際に使用した結果、訴訟リスクが発生した場合。
それは「助言したあなたの責任」となります。
とんでもなく恐ろしいことですが、知識が浅い人ほど自信満々に答えがちな現状があります。
知らないことを、知らないと言えるように、最低限の“勘所”を知っておく必要があるのです。
現場に出題範囲はない
行政書士試験とは異なり、現場には「この論点が出ます」のヒントはありません。
突然飛んでくる“ガチ質問”を受け、こちらで論点を特定し、適切な回答をするしかないのですが、それができずに詰まった瞬間、信用はゼロになるかもしれません。
こうなると、あなたが合格証書を持っていようと、クライアントにとっては「頼れない人」でしかないのです。
第3章|“やらかした行政書士”たちの記録
知財に関するトラブルの多くは、容赦なく襲ってきます。特に、開業初期や副業段階にありがち。
ですので、本章では、実際に行政書士やその周辺で発生した事例をご紹介します。
ケース①|屋号が“類似商標”だった → 全面リブランディング
背景
40代男性/元営業職。副業で行政書士として開業。
「親しみやすさ」と「信頼性」を込めた屋号とロゴを用意し、ドメイン・LINE・名刺・HPまで完璧に整えたはずだった。
落とし穴
- 類似商標(名称)が既に登録されていた
- 数か月後、内容証明が届く
- 屋号の使用差止め、全媒体の刷新、ドメイン変更、封筒・名刺等すべて廃棄
結果
半年かけて築いたブランドが“紙くず”になり、信用失墜。
「調べておけば、1日で防げたことだった」と本人談。
🧠 商標は、思いついた名前をそのまま使うと危険な分野。 使用前に調査しない=地雷原全力疾走。
ケース②|フリーBGMのつもりが… → YouTube収益ゼロ
背景
開業直後にYouTubeで情報発信を開始。
BGMは無料素材サイトからダウンロード。
再生数も伸び始め、広告収益が見え始めたが…
落とし穴
- 使用していたBGMのライセンスが途中改定
- 著作権フラグが立ち、広告制限
- チャンネル全体の評価が落ちる
- 再編集&再アップにコスト発生
結果
収益どころか、信頼・再生数・制作コスト、すべてがマイナスに転化。
「フリー素材だから大丈夫」の認識が裏目に出たケース。
🧠 著作権は“生き物”。今日OKでも、明日NGになる可能性を常に想定すべき。
ケース③|外注ロゴ → 実は“著作権は他人のもの”
背景
開業時、クラウドソーシングでロゴを外注。
デザインにも納得し、納品されたデータをさっそく使用。
名刺、HP、商標出願まで進めた──が。
落とし穴
- 数か月後「他の案件で同じロゴが使用されている」と通報
- 契約時、「著作権譲渡」に関する取り決めをしなかった
- 制作側が著作権を持っていることで使用不可となった
- 出願商標は差し戻し、ウェブページ等はパクリ扱いされて炎上寸前
結果
「お金を払ったから自分のもの」という思い込み、権利関係を確認しなかった。
ブランド価値にキズがつき、信用回復に1年かかった。
🧠 契約書にたった1行「著作権を譲渡する」とあるかないかで、あなたの財産が“自分のもの”になるか、“他人のもの”になるかが決まる。
総括:これは「レアケース」ではない
上記はいずれも、特別な話ではありません。
行政書士が独立開業するなかで、ごく普通に起こり得る話です。
しかしながら、試験勉強では誰も教えてくれません。
では、どうすればこれらのトラブルを回避できるのでしょうか?
第4章|“使える行政書士”になるための、最低限の知財スキル
試験問題なら、「わからなければ飛ばす」で済みます。
けれど、実務においては、「わからなければ信用を失う」可能性があります。
更に、実務には“出題範囲”という概念がありません。
だからこそ、「これは触れてはいけない」と察知する“勘所”と、「調べ方」や「守るための型」を持っておく必要があります。
📘著作権|「フリー素材」と「フリーライド」は別物
基本の押さえ
- 著作権とは、創作的に表現されたもの
(画像/文章/音楽/動画 etc.) - フリー素材でも、商用利用不可、改変NG、クレジット必須等の条件がある
- 引用には5つの条件クリアが必須
実務でのチェック例
- 使用元URL、ライセンス表記の確認
- 商用利用、改変に関する可否を確認
- 画像・文章の掲載に先立ち、クレジット表記の要否を記録
🧠 「この画像、著作物?」と判断できるセンスが実務力。
AI画像、SNSスクショ、テンプレ文章──グレーを避ける力が問われます。
🏷商標|「名前をつける=地雷原に足を踏み入れる」
リスクの所在
- 屋号、サービス名、商品名、ロゴ等のほとんどが商標権の対象
- 類似商標がある場合、差止めや損害賠償リスクも視野に
最低限やるべきこと
- J-PlatPatで「ひらがな/カタカナ/英字」すべて検索
- 同業・類似業種に使用例がないか確認
- 使用媒体(HP/SNS/印刷物等)との一致確認
🧠 商標は「被ってるか」だけじゃなく「どう使うか」でアウトになる可能性があります。
「登録してあるから安心」ではなく、“先に使っていた人”が勝つ世界でもあります。
📄契約|“誰のものか”を明確にするひと言が命綱
発信の外注や協業が増える中で、「書いたもの・作ったものは誰のものか」が曖昧な契約は極めて危険です。
契約時に必ず確認すべき事項
- 成果物の著作権は譲渡されるか(著作権法第27条/第28条含むか)
- 商標登録の予定がある場合、二次利用・販売制限はあるか
- 納品後の習性対応、使用媒体、著作者表示について明記されているか
雛形抜粋(実務使用例)
第◯条(著作権の譲渡)
本業務により納品された成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)は、甲が乙に対して成果物の納品と同時に譲渡するものとする。
🧠 契約は、トラブルになってから読むものではなく、「作る時点」で仕込むものです。
🧰実務で使える“引き出し”
以下は、実際の行政書士業務の中で使用しているチェックリストや雛形コメントの一部です。
✔ 開業前の商標チェック用テンプレ
- J-PlatPat検索画面をスクショ保存
- 区分ごとに注意すべき類似業者を一覧化
- 仕様予定媒体(名刺/LP/YouTube等)との整合性をスプレッドで確認
✔ 著作物の確認フロー
- 使用元URL記録表の作成
- クライアント向け「引用条件チェックリスト」の提供
- AI生成物に対する補足条項文例(※ChatGPT等)
✔ 契約書への盛り込み例
- 著作権譲渡 or 利用許諾の文言比較
- 商標登録に先立つ覚書のひな形
「知らなかった」では、守れない世界で
行政書士試験に合格することは、確かに大きな一歩です。
ですが、そのあとには、“信用で食っていく”世界が待っています。
そして、信用とは、「正しく答えられる人」ではなく、「危ないと気づける人」が得るものです。
質問されたとき、答えに詰まったことはありますか?
「このロゴ、使っても大丈夫ですよね?」
「この屋号、被ってないですか?」
「YouTubeにこのBGM使っていいですか?」
この問いに対し沈黙した瞬間、あなたの名刺の価値は0円になります。
あとで勉強すればいい、は通用しない
試験の勉強とは違い、実務は「今どう答えるか」がすべてです。
「時間ができたら勉強しよう」「落ち着いたら学ぼう」では、間に合わないのが現場のスピード感。
だからこそ、試験勉強の合間、“わずかなすきま時間”で構いません。
一つでも多く、知財の“地雷ポイント”を知っておくことが、あなた自身を守ります。
🎥 関連動画|著作権違反のリアルな事例を知りたい方へ
著作権については文章だけで理解するのが難しい部分もあります。
実際にYouTubeなどで起こりやすい著作権違反を、BGM・画像・台本の3点に絞って解説した動画を公開しています。👉 YouTubeで絶対やっちゃダメな著作権違反3選|BGM・画像・台本、全部アウト
YouTubeメンバーシップはこちら
🔗https://www.youtube.com/channel/UCRex_B9uPGOMsofqrxh7ScQ/join関連投稿