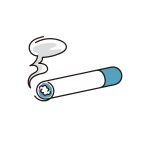当サイトの一部に広告を含みます。
長尺の配信から“おいしい瞬間”だけを抜き出して広める切り抜き動画は、クリエイターにも視聴者にもメリットがあります。
一方で、無断切り抜き=著作権侵害になりやすいのも事実。
プラットフォームの規約、肖像権・商標、収益化の可否まで、見るべきポイントは多岐にわたります。
この記事では、日本法(著作権法の「引用」概念が前提。米国の“フェアユース”とは別物)をベースに、合法的に切り抜くための実務手順をまとめます。
あなたがこの記事を読み終えるころには、「これなら出せる/これは危険」の判断が自分でできるようになります。
Contents
関連投稿
まず押さえていただきたい結論(超要約)
- 他人の動画は原則、無断編集NG。
切り抜き=編集=二次的著作物の利用であり、権利者の許諾が必要です。 - 日本法の「引用」は、編集や意味改変を伴う切り抜きには基本的に使えません。
- 収益化するのなら、事前に書面(または同等の記録)で条件を明確化。
プラットフォーム規約も二重で確認しましょう。 - グレーなのは肖像権/パブリシティ権/商標。
ロゴ・ポスター・人物の写り込みにも注意。 - トラブル時は非公開→記録保存→連絡。
カウンタ通知は慎重に(誤るとリスク拡大)。
第1章 結論と前提:切り抜き動画は「許諾ありき」です
他人が作成した動画を切り抜く行為は、たとえ数秒であっても「編集」を伴うため、法律上は二次的著作物の利用にあたります。
つまり、権利者の許可を得ずに行えば著作権侵害となるおそれがあるというのが前提です。
「少しだけなら大丈夫」「引用だからOK」という声もよく聞かれますが、実際にはそう単純ではありません。
日本の著作権法における「引用」は、改変しないこと・主従関係が明確であること・出典を明示することなど、厳格な条件をすべて満たした場合にのみ認められます。
言い換えると、元動画を編集・トリミング・字幕付けなどの加工を行った時点で「引用」の範囲を超えることになり、原則として許諾が必要になります。
また、YouTubeやTwitchなどの配信プラットフォームは、それぞれ独自の利用規約を設けています。
プラットフォーム上で「埋め込み機能」を利用して紹介することと、「再編集して再投稿すること」はまったくの別扱いです。
特に収益化を伴う場合には、利用規約+著作権法の双方に違反するリスクがあるため注意が必要です。
要するに、合法的に切り抜きを行うための第一歩は「誰が権利を持っているのか」を確認し、許可を取ることを前提に考えることです。
権利者が不明な場合や連絡が取れない場合は、残念ながら利用を見送るのが安全です。
「グレーゾーン」ではなく「明確なホワイトゾーン」で活動する意識が、結果的に自分のチャンネルやブランドを守ることにつながります。
次章では、実際に合法的な切り抜きを行うための手順を、具体的な5ステップに分けて解説します。
第2章 合法切り抜きの5ステップ
ここからは、実際に切り抜き動画を「合法的に」作成するための流れを、5つのステップに分けて解説します。
一つひとつの手順を踏むだけで、後々のトラブルを防ぎながら、安心して公開できるはずです。
ステップ1:権利者を特定する
まず確認すべきは、その動画の著作権を誰が持っているのかという点です。
個人配信者のケースもあれば、事務所や企業が権利を管理している場合もあります。
音楽や映像素材を他社が提供している場合、その部分だけ別途許可が必要になることもあります。
ゲーム実況やVTuber配信などでは、「所属事務所」「ゲーム会社」「配信プラットフォーム」それぞれのルールが重なっていることも珍しくありません。
どこに許可を取るべきかが分からない場合は、動画の概要欄や公式サイトの利用ガイドラインを確認しましょう。
そこに明記されていることが多いです。
ステップ2:利用内容を具体化する
許可を求める際は、単に「動画を使わせてください」ではなく、どの部分を・どのように使うのかを明確に伝えることが重要です。
たとえば、次のような点を整理しておくとスムーズです。
- 使用箇所:何分何秒~何分何秒まで
- 使用目的:切り抜き/紹介/解説など
- 公開先:YouTube・X・Instagram等
- 編集内容:トリミング・字幕追加・ナレーション挿入など
- 収益化の有無:広告収入の発生予定があるか
- 公開期間:恒久公開 or 期間限定
こうしておくことで、相手も内容を把握しやすく、許可の判断がしやすくなります。
ステップ3:許諾を取得し、証拠を残す
次に、実際の許諾取得です。
最もシンプルなのは、相手に直接メッセージやメールで問い合わせる方法です。
SNSのDMや公式サイトのお問い合わせフォームなど、連絡手段はさまざまあります。
このとき大切なのは、やり取りを必ず記録に残すことです。
「いつ・誰から・どの範囲で許可を得たのか」が後から確認できるよう、スクリーンショットやメールの保存を徹底しましょう。
収益化を伴う場合は、簡単な書面を交わすのが理想です。
メール本文に同意内容を明記し、相手の返信をもって契約成立とする形でも構いません。
ステップ4:クレジット・リンク・NG条件を守る
許諾を得たら、出典の明記と約束事項の遵守を忘れないようにしましょう。
概要欄や動画の最後に、以下のような表記を添えると丁寧です。
- 出典:〇〇チャンネル(https://~)
- 使用許諾:〇年○月〇〇日付で取得済み
- ※内容の一部をトリミング・字幕加工しています
また、相手から「誤解を招く編集は禁止」「政治・宗教に絡めないでほしい」といった条件が提示されることもあります。
そうした条件も、“利用の一部”として守る義務があります。
違反した場合、許諾が取り消されることもあるため注意が必要です。
ステップ5:公開後の管理と対応
動画を公開した後も、安心して放置できるとは限りません。
プラットフォームの自動検出システム(YouTubeのContent IDなど)が著作権保護コンテンツと判定することもあります。
この場合は慌てず、一時的に非公開にして確認を取るのが安全です。
また、権利者や第三者から申し立てが来た場合には、即時対応する姿勢が大切です。
放置するとアカウント停止や法的措置につながるおそれもあります。
万一削除要請があっても、まずは冷静にやり取りの履歴を示し、誠実に説明すれば解決するケースがほとんどです。
以上の5ステップを守るだけでも、著作権トラブルの多くは回避できます。
「自分の作品ではないものを扱う」という意識を持ち、常に“相手への敬意”を前提にした切り抜きを心がけることが大切です。
次章では、具体的に「どんなケースがOKで、どんなケースがNGになるのか」をわかりやすく整理していきます。
第3章 OK/NG早見表|合法と違法の境界線
切り抜き動画は、使い方次第で合法にも違法にもなります。ここでは代表的なケースを整理しながら、「ここまではOK」「これは危険」という判断軸を紹介します。
OKになり得るケース
1. 権利者が再利用を明示的に許可している場合
YouTubeで「クリエイティブ・コモンズ」ライセンスが設定されている動画や、公式に「切り抜きOK」と公表しているチャンネルが該当します。
ただし、利用条件(クレジット表記・営利利用不可など)は必ず守る必要があります。
2. 自分が制作・配信した動画を切り抜く場合
自作動画の切り抜きは自由に行えます。収益化も問題ありません。
ただし、配信内で他者の音楽や映像素材を使用している場合は、その部分に別の権利が発生していないか確認しましょう。
3. 純粋な「引用」として成立している場合
ニュース解説や評論の一部で、最小限の範囲を引用し、主従関係が明確で改変がない場合は適法となります。
ただし、切り抜き動画のように編集・加工を加えたものは、基本的にこの「引用」には当たりません。
4. ゲーム会社や配信者が明確なガイドラインを設けている場合
ゲーム実況動画や配信コンテンツについて、二次利用を認めるルールが公式サイトに掲載されているケースがあります。その範囲内での切り抜きは合法です。
NGになりやすいケース
1. 無断で他人の動画を編集・再投稿する場合
元動画の一部を切り抜き、自分のチャンネルに再投稿する行為は、著作権侵害に該当する可能性が高いです。
「たった数秒」でも、編集を伴えば二次的著作物の利用にあたります。
2. 映画・ドラマ・ミュージックビデオなどの抜粋
これらの映像は著作権保護が非常に厳格です。切り抜いてSNSでシェアすることは、たとえ非営利であっても原則NGです。
3. 配信中の人物の映像や声を無断で使用する場合
TwitchやYouTube Liveなどの配信を切り抜き、本人の許可なく投稿すると、著作権侵害に加えて肖像権侵害にもあたるおそれがあります。
4. 他人のロゴ・商標・企業広告を切り抜く場合
企業が制作したプロモーション動画やロゴ入り映像を無断で使用することは、著作権・商標権の両方で問題となり得ます。
5. 誤解を招く編集をした場合
元の発言を切り取って意図をねじ曲げたり、誤解を与える見せ方をした場合、名誉毀損や信用毀損に発展することもあります。
よくある誤解
「数秒なら大丈夫」→誤りです。
秒数ではなく、著作物の“質的な重要性”が問題になります。数秒でも、その作品の核心部分であれば侵害とされます。
「出典を明記すればOK」→不十分です。
出典表示はマナーとして重要ですが、法的には「許可」とは別問題です。
「海外ではフェアユースがある」→日本では通用しません。
日本法にフェアユースは存在しません。日本では「引用」としての適法利用が唯一の例外です。
このように、切り抜き動画は「何をどう使うか」で立場が大きく変わります。
次章では、日本法上の「引用」と「切り抜き」の違いをより明確に整理し、どこから違法ラインに踏み込むのかを見ていきます。
第4章 「引用」と「切り抜き」の違いを正しく理解する
「引用だから大丈夫」と思って無断で動画を切り抜くケースは少なくありません。
しかし、実際には引用と切り抜きはまったく別の行為です。
ここを混同すると、悪気がなくても著作権侵害にあたることがあります。
引用が認められるための5条件
日本の著作権法では、他人の著作物を「引用」として利用できるのは、次の5条件を満たす場合に限られます。
- 主従関係が明確であること
引用部分があくまで“補足的”であり、メインは自分の意見や解説であること。 - 引用の必要性があること
他の表現では目的を果たせず、その著作物を引用することに合理的な理由があること。 - 引用部分が明確に区別されていること
どこからどこまでが引用なのか、視覚的・構造的に明示されていること。 - 出典を明記していること
引用元の作品名・著作者名・URLなどを明確に記載すること。 - 内容を改変していないこと
引用部分の編集・加工・要約など、意味を変える行為をしていないこと。
この5つを満たしていれば、著作権者の許可を得なくても利用が認められるケースがあります。
ただし、どれか1つでも欠けると引用の成立は難しいと考えた方が安全です。
切り抜きは「改変」を伴う
切り抜き動画は、元の動画の一部を抜き出して再構成する点に特徴があります。
字幕を付けたり、テンポを調整したり、BGMを入れたりすることも多いでしょう。
これらの行為はすべて、著作権法上の「改変」に該当します。
つまり、引用の条件⑤(改変しない)を満たせないため、引用とは認められません。
さらに、切り抜き動画では引用部分が中心となり、自分の主張が添えられていないことが多いため、主従関係(条件①)も成立しない場合がほとんどです。
よくある誤解と落とし穴
- 「短い部分なら引用にできる」→誤りです。
短くても、編集・トリミングを行えば引用ではなくなります。 - 「感想を入れたから自分の意見が主」→不十分です。
たとえコメントを加えていても、動画全体の主軸が引用部分にある場合は引用にはなりません。 - 「海外ではフェアユースでOK」→日本では適用外です。
フェアユースはアメリカの制度で、日本では認められていません。
日本で許されるのは、あくまで著作権法32条の「引用」だけです。
まとめ:引用は「分析」、切り抜きは「編集」
引用は、他人の著作物を材料に自分の考えを展開する行為です。
一方、切り抜きは、他人の著作物そのものを再構成し、別の作品として発信する行為です。
つまり、切り抜きは「新しい著作物を作る」=二次的著作物の利用にあたり、法的には引用ではなく、権利者の許可が必要な範囲になります。
次章では、実際に権利者に許可を取る際の文面テンプレートや、クレジット表記の書き方を紹介します。
正しい依頼の仕方を知っておくと、相手にも誠実な印象を与えられます。
第5章 許諾依頼テンプレートとクレジットの書き方
切り抜き動画を合法的に公開するには、権利者から明確な「許諾」を得る必要があります。
ここでは、相手に連絡する際の文面例と、動画に添えるクレジット表記のポイントを紹介します。
1. 許諾をお願いする際の基本ルール
許諾を求めるメッセージは、礼儀正しく・簡潔に・具体的にが原則です。
長文や説明過多は避け、相手が判断しやすい情報だけをまとめましょう。
- どの部分を使いたいのか(時間・内容)
- どのように使うのか(編集内容・公開媒体)
- 収益化の有無
- 出典を明示すること
- 削除要請があれば速やかに対応すること
これらを明示すると、誠実で信頼できる依頼と受け止めてもらえます。
2. DM・SNS用の短文テンプレ
〇〇様
こんにちは。△△と申します。
貴チャンネルの動画「〇〇〇〇」(URL)のうち、〇分〇秒〜〇分〇秒の部分を切り抜き、私のYouTubeショート(またはX)で紹介したいと考えています。
出典・リンクを明記し、収益化は行いません。
ご許可をいただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
営利利用を予定している場合には「収益化あり」と明示し、別途条件を確認しましょう。
3. メールで依頼する場合の文例
件名:動画の切り抜き利用についてのご相談
件名:動画の切り抜き利用についてのご相談
〇〇様
初めまして、△△と申します。
貴チャンネル「〇〇〇〇」に掲載されている動画「△△△△」(URL)を拝見し、大変興味を持ちました。
その中の〇分〇秒〜〇分〇秒のシーンを切り抜き、私のYouTubeチャンネルにて紹介させていただきたく、ご連絡いたしました。
動画内および概要欄に出典を明記し、貴チャンネルへのリンクを掲載いたします。
収益化の有無:あり(またはなし)
公開予定:〇年〇月〇日~
もし条件等がございましたらお知らせください。
ご検討のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
敬具
△△(氏名または屋号)
連絡先メールアドレス:〇〇〇〇
チャンネルURL:〇〇〇〇
この形であれば、ビジネスライクな印象を与えつつ、相手が判断に迷わない情報量になります。
4. クレジット表記の例
動画の概要欄やエンドロールには、必ず出典と許諾情報を明示しましょう。
例としては以下のような形式が一般的です。
- 出典:〇〇チャンネル(https://~)
- 使用許諾:〇年〇月〇日付で取得済み
- 本動画の一部をトリミング・字幕加工して掲載しています。
- 無断転載・二次配布を禁止します。
クレジットを明記することで、視聴者にも「正しく許可を取っている動画」であることが伝わり、チャンネル全体の信頼度も上がります。
5. 許可をもらったら「証拠」を必ず残す
相手からの返信や同意メッセージは、必ず保存しておきましょう。
削除要請やトラブルが発生した際に、「どの範囲で許可を得ていたか」を説明するための重要な証拠になります。
スクリーンショット・メール保存・日付入りメモなど、形式は問いませんが、残す習慣を持つことが大切です。
6. 許諾が得られなかった場合
相手が拒否した、あるいは返信がなかった場合は、利用を見送るのが安全です。
「連絡が取れなかったからOK」と判断して公開するのは、最もリスクの高い対応です。
他の素材を使うか、オリジナルで作り直す方が、長期的には確実に自分の信用を守ります。
次章では、YouTube・Twitch・ゲーム会社など、プラットフォームごとの規約と落とし穴を見ていきます。
せっかく許諾を得ても、利用規約違反で削除されるケースがあるため、ここも要チェックです。
第6章 プラットフォーム規約でつまずくポイント
切り抜き動画は、著作権法のルールだけ守っていれば安全――というわけではありません。
YouTubeやTwitchなど、各プラットフォームが独自の利用規約を設けており、その規約に違反すると、法的に問題がなくても動画削除やアカウント停止の対象になることがあります。
ここでは、主要なプラットフォームごとの注意点を整理します。
1. YouTubeの注意点
(1)埋め込みと再アップの違い
YouTubeでは、他者の動画を「埋め込み機能」で自分のサイトに表示することは認められています。
しかし、動画をダウンロードして編集・再アップロードすることは規約違反です。
あくまで、埋め込み=YouTube上の再生リンクを借りる行為、再アップ=別の動画として配信する行為、という扱いになります。
(2)クリエイティブ・コモンズ(CC)ライセンスの誤解
「CCライセンスだから自由に使える」と誤解されがちですが、再利用できるのは“ライセンス条件を守る範囲内”のみです。
たとえば「商用利用不可」「改変禁止」などの条件が付いている場合、それを破ると規約違反になります。
(3)Content IDによる自動検出
YouTubeには、著作権保護された音声や映像を自動検出する「Content ID」システムがあります。
合法的に許可を得ていても、自動判定で警告や収益化制限を受けることがあります。
その際は慌てず、非公開→異議申立て→証拠提示の流れで冷静に対応しましょう。
2. Twitchの注意点
Twitchでは、配信者自身が「クリップ機能」で切り抜きを作成できる仕組みがあります。
ただし、この機能はTwitch内での視聴を前提としており、他のプラットフォームへの転載は原則として禁止です。
また、配信内でBGMを流している場合、その音楽が著作権で保護されていると配信者本人でさえアーカイブ削除やBAN対象になることがあります。
他人の配信を切り抜く場合はもちろん、BGMが含まれている部分を避けるか無音に差し替えるようにしましょう。
3. ゲーム会社のガイドライン
ゲーム実況・切り抜き動画で最も多いトラブルがここです。
各ゲーム会社は「動画投稿ガイドライン」や「配信ポリシー」を公開しており、その内容に従う必要があります。
代表的な注意点は以下のとおりです。
- 商用利用の可否:収益化を禁止しているタイトル多し
- ネタバレ範囲の指定:エンディング・ボス戦などは配信禁止になる場合あり
- 二次利用の制限:他人の配信映像を再利用する行為を禁じているケースが多い
- クレジット表記の義務:ゲームタイトル・会社名・©表記を求められることがある
任天堂・スクウェア・エニックス・カプコンなど、主要メーカーはガイドラインを明示しているので、必ず公式サイトで確認してから投稿しましょう。
4. VTuber・事務所系チャンネルのルール
VTuberや芸能事務所所属の配信者の動画は、個人ではなく運営会社が著作権を管理しているケースが大半です。
公式に「切り抜きガイドライン」が公開されている場合は、その内容に沿えば利用可能ですが、以下の点には注意が必要です。
- ガイドラインの改訂が突然行われることがある
- クレジット表記の形式が指定されている(例:「切り抜きチャンネル名」「元配信URL」)
- 誹謗中傷・過度な編集・サムネ煽りは禁止
- 収益化を行う場合は事前申請が必要な場合もある
特にホロライブ、にじさんじなど大手事務所は、切り抜きOKだが条件が細かいので、リンク元の規約を逐一確認しておくのが安全です。
5. SNS(X、Instagram、TikTokなど)の共通注意点
短尺動画を再投稿する際、プラットフォーム側が音源や動画素材のライセンスを一時的に提供していることがあります。
ただし、その権利はそのプラットフォーム内限定。
YouTubeで使えたBGMが、TikTokではNGになる、というのはよくあるパターンです。
また、企業アカウントの投稿を転載する場合は、企業側の広報ポリシーにも注意が必要です。
6. まとめ:法より前に“規約”を読む習慣を
著作権法は全国共通ですが、プラットフォーム規約はサービスごとに異なります。
たとえ法的に問題がなくても、「規約違反」で削除されることは珍しくありません。
特に収益化を狙う場合、アカウント停止は致命的です。
動画を投稿する前に、必ず「自分が利用しているプラットフォームの最新ガイドライン」を確認する習慣をつけましょう。
これだけでリスクの大半は防げます。
次章では、動画に登場する人物・ロゴ・店舗などの権利(肖像権・商標・施設規約)について解説します。
ここを見落とすと、著作権以外のトラブルを招くこともあります。
第7章 肖像権・パブリシティ・商標・施設規約にも注意
著作権をクリアしていても、切り抜き動画には別の法律リスクが潜んでいます。
特に問題になりやすいのが、肖像権・パブリシティ権・商標権・施設の利用規約の4つです。
これらは「著作権と無関係に成立する権利」なので、個別に配慮が必要です。
1. 肖像権(人物の顔や姿)
他人の顔や姿が特定できる形で映り込んでいる場合、本人の同意なく公開すると肖像権の侵害になる可能性があります。
たとえ一瞬でも、本人が特定できる映像を無断で公開することは避けましょう。
- 一般人の場合:必ず同意を得るか、モザイク・ぼかしで対応
- 芸能人や配信者の場合:事務所を通じた許諾が原則
- SNS上の顔出し投稿でも、再利用には別途許可が必要
特にライブ配信の切り抜きなどでは、視聴者のコメント欄や映り込みにも注意が必要です。
2. パブリシティ権(有名人の名前・姿・声)
芸能人やVTuberなど、知名度の高い人物の「名前・声・容姿・キャラクター」には、商業的な価値があります。
これを本人や所属事務所の許可なく広告や動画に利用すると、パブリシティ権の侵害になるおそれがあります。
例)
- 人気配信者の発言シーンを切り抜き、別タイトルで再構成して収益化する
- 有名人の写真や音声を無断で使い、自分の動画の宣伝に利用する
どちらも、権利者から見れば「無断で利益を得ている」行為に該当します。
使用を検討する際は、必ず事前確認を行いましょう。
3. 商標権(ロゴ・商品・企業名)
企業ロゴやブランド名を映す場合にも注意が必要です。
特に商品パッケージ、ポスター、店舗の看板などは、商標として保護されていることがあります。
- 企業ロゴを意図的に強調して編集する
- 広告のような見せ方で掲載する
- 批判的・誤解を招く使い方をする
これらは、商標権侵害や不正競争防止法違反に発展する可能性があります。
正しい商品紹介やレビュー目的であれば許容されることもありますが、誇張や誤用を避けることが前提です。
4. 施設規約(店舗・イベント会場など)
撮影場所の利用規約にも注意が必要です。
ショッピングモールやイベント会場などでは、「撮影禁止」「二次利用禁止」と明記されていることがあります。
たとえ現場で撮影を許されていても、その映像をYouTubeなどで公開するのは規約違反となることがあります。
また、他人の敷地内での撮影や配信を行う場合は、管理者の許可が必要です。
商業利用を目的とする場合は、追加で「使用料」が発生することもあります。
5. VTuber・AIキャラクターなどの特殊ケース
近年は、VTuberやAIキャラクターのように「見た目」「声」「人格」が一体となったコンテンツも増えています。
これらは著作権だけでなく、キャラクター権・人格権・商標など複数の権利が複雑に絡みます。
特に「切り抜きガイドライン」が用意されていない個人VTuberの場合は、本人に直接確認を取るのが原則です。
まとめ:著作権以外の“もうひとつの地雷”を忘れない
切り抜き動画で最も多いトラブルは、実は著作権よりも肖像や商標の扱いです。
誰かの顔・声・ロゴ・空間を使う以上、その裏には必ず何らかの権利があると考えましょう。
動画を編集するときは、「この映像に、他人の権利が紛れ込んでいないか?」を最後にもう一度チェックしてから投稿するのが安全です。
次章では、収益化を目指す人が特に注意すべき「契約」と「書面の取り交わし」について解説します。
ここを疎かにすると、後から「許諾した・していない」で揉める原因になります。
第8章 収益化をするなら「書面」で残す
切り抜き動画を趣味の範囲で楽しむなら口約束でも済むことがありますが、収益化を行うなら書面で残すことが必須です。
動画広告やメンバーシップ、投げ銭など、金銭が発生した瞬間に「契約関係」として扱われるからです。
1. 口頭やDMでの許可は“最低限”
SNSのDMやメールで「OKですよ」と返信をもらうだけでも法的な効力はあります。
ただし、その内容があいまいだと後で「そんな条件で許可した覚えはない」とトラブルになることがあります。
そこで、やり取りの中に次の4点を必ず含めておきましょう。
- どの動画(URL)をどの範囲で使用するか
- 収益化の有無
- クレジット表記と公開方法
- 削除や変更の要請があった場合の対応
この4つが明確に確認できるスクリーンショットやメールを保存しておけば、トラブル時の防御力は格段に上がります。
2. 書面で残すなら、1枚で十分
本格的な契約書を作る必要はありません。
WordやPDFでA4一枚にまとめ、双方の署名かメール送信で同意すればそれで成立します。
形式よりも、「誰が・何を・どこまで許したか」が読み取れる内容であることが重要です。
記載すべき基本項目(収益化を前提とする場合)
- 利用目的(切り抜き動画の制作・配信)
- 対象動画(タイトル・URL・該当部分)
- 編集内容の範囲(字幕・トリミング・音声編集など)
- 公開媒体(YouTube・TikTokなど)
- 収益化の方法(広告収入・スーパーチャット等)
- 収益の分配がある場合はその割合
- クレジット表記の方法
- 再利用・第三者への再許諾の可否
- 取り消しや削除要請時の対応
- 準拠法と管轄(日本法・○○簡易裁判所など)
この10項目を押さえておけば、後から揉める余地はほとんどなくなります。
3. 同意書の文例(簡易版)
私(以下「甲」という。)と、○○○(以下「乙」という。)は、甲が制作した動画コンテンツ「(動画タイトル・URL)」の一部(〇分〇秒〜〇分〇秒)を、乙が編集・再構成のうえ自身のチャンネル(URL)で公開することに合意した。
乙は、動画の概要欄に出典・リンクを明示し、甲から削除の要請があった場合は速やかに削除するものとする。
収益化を行う場合の利益分配、公開期間、その他条件については、別途協議のうえ決定する。
本同意書はメールまたは電子署名により有効とする。
〇年〇月〇日
甲(氏名・チャンネル名)__________
乙(氏名・チャンネル名)__________
1枚で完結する実務的な内容です。PDF化して保存しておけば十分です。
4. メールベースで残す場合のポイント
契約書を交わさない場合でも、メール本文に明確な合意文を残しておくとよいでしょう。
本メールをもって、貴動画の該当部分を切り抜き動画として使用することについて合意しました。
内容・範囲・期間・収益化条件等は、前回のやり取りどおりといたします。
このように明示しておけば、後日法的な証拠としても機能します。
5. 書面化のメリット
- 収益分配の条件を明確にできる
- 権利関係を整理して第三者からの申し立てを防げる
- 削除・変更依頼の対応をスムーズにできる
- プラットフォーム側への異議申し立て時に“証拠”として提出できる
「書面を作る=信頼されていない」ではなく、「お互いを守るための予防策」と考えるのが正解です。
次章では、万が一トラブルや著作権申立てがあったときの初動対応マニュアルを紹介します。
適切に動けば、炎上やアカウント停止を防ぐことができます。
第9章 トラブル・申立て時の初動マニュアル
切り抜き動画を公開していると、権利者やプラットフォームから「著作権侵害の申し立て」や「削除要請」が届くことがあります。
そのときに慌てて対応を誤ると、動画の削除だけでなくアカウント停止、場合によっては法的責任に発展することもあります。
ここでは、トラブルが起きたときの初動対応を順を追って解説します。
1. まず非公開にする
申し立てや警告を受けたら、まずは動画を非公開または限定公開に変更しましょう。
公開を続けたまま対応すると、被害拡大や悪質と見なされるおそれがあります。
削除前に、動画のURL・概要欄・公開日時をスクリーンショットで保存しておくと後で経緯を説明しやすくなります。
2. 事実関係を整理する
次に、以下の点を確認します。
- 該当動画のどの部分が問題とされているか
- 相手が権利者本人または代理人か
- 自分が許諾を得ていた場合、その証拠(メッセージ・メール・契約書)
特に、申し立てが「本人のものかどうか」は重要です。
中には、本人を装ったなりすましや、自動検出の誤判定もあります。
感情的に反論せず、相手の正当性をまず確認しましょう。
3. 証拠を提示できるよう準備する
許可を得ていた場合は、そのやり取りを整理しておきます。
メール本文・スクリーンショット・同意書など、第三者が見ても一目で分かる形式で保存しておくことが大切です。
YouTubeの異議申し立てを行う場合にも、これらの資料が提出できると判断が早くなります。
4. 相手への連絡は丁寧かつ短く
直接コンタクトを取る場合は、冷静で簡潔なメッセージを心がけましょう。
ご連絡ありがとうございます。
ご指摘いただいた箇所を確認し、現在非公開のうえ内容を精査しております。
許諾範囲や表記に不備があった場合は、速やかに修正または削除対応いたします。
この程度で十分です。長文や弁解めいた説明は不要です。
5. 異議申立てを行う場合の注意点
自分に正当な権利があり、誤って申し立てを受けた場合は「異議申立て」が可能です。
ただし、虚偽の申立ては逆に自分が処罰対象になるため、証拠をそろえたうえで慎重に行いましょう。
- 許諾を得ている場合:その証拠を添付
- CCライセンスや公式ガイドラインに基づく場合:該当ページのURLを記載
- フェアユース(海外向け)を根拠とする場合:日本では通用しない点に注意
手続きに不安がある場合は、無理に反論せず、専門家に相談する方が安全です。
6. 炎上を防ぐための基本姿勢
- SNSで弁解や反論を投稿しない
- コメント欄で視聴者と口論しない
- 削除対応後は静かに経緯を整える
- 再投稿する場合は、必ず修正版として明記する
問題が解決するまで公開を急がないこと。
「誠実な対応をしている」と見えるだけで印象は大きく変わります。
7. 再発防止のチェックリスト
- 許諾の範囲を再確認した
- 使用素材の出典・権利者を整理した
- ガイドラインや利用規約を最新化した
- クレジット表記を統一した
- 許可証・メールをフォルダ管理した
このチェックを習慣化するだけで、トラブル発生率は大幅に下がります。
トラブル対応の基本は「迅速・記録・冷静」です。
感情的な反応よりも、記録と誠実さで信頼を取り戻すことが、長く活動を続けるための最善策です。
次章では、これまでの内容をまとめつつ、投稿前に確認できる最終チェックリストを紹介します。
ここまで来れば、もう切り抜き動画で迷うことはないはずです。
第10章 公開前の最終チェックリスト
ここまで解説してきた内容を踏まえ、切り抜き動画を公開する前に確認しておきたいポイントを一覧にしました。
このチェックを一通り済ませてから投稿すれば、リスクの大半は回避できます。
権利関係
- 元動画の権利者を特定した
- 著作権だけでなく、肖像権・商標・施設利用規約も確認した
- ゲームや音楽などの素材はガイドラインの範囲内で使用している
許諾と証拠
- 権利者から明確な許可を得ている
- 許諾範囲(部分・期間・収益化の有無)が書面またはメッセージで残っている
- 許可内容をメール・PDF・スクリーンショットで保存している
編集と表記
- 元動画の意図を歪める編集をしていない
- クレジットや出典を明記している
- 政治・宗教・誹謗中傷に関わる内容を避けている
- 規約に沿ったサムネイル・タイトルを設定している
プラットフォームの規約
- YouTube・Twitch・各SNSの利用規約を確認した
- 商用利用や二次利用が禁止されていない
- BGM・効果音がプラットフォーム内でライセンス許諾されている
トラブル対応体制
- 削除要請が来た場合の対応方針を決めている
- 許諾記録や契約書の保管場所を決めている
- 申し立て対応の連絡文テンプレを用意している
公開後の運用
- コメント欄での誹謗・過度な編集指摘への対応を決めている
- 許諾を得た相手に公開報告を送っている
- 内容更新や削除の要請があれば速やかに応じる準備がある
このチェックを毎回繰り返すことで、「安全に切り抜く」感覚が自然と身につきます。
動画投稿の世界では、スピードよりも信頼の積み重ねが最も大きな武器になります。
誠実な運用を続けていれば、周囲のクリエイターや視聴者からの信頼も確実に厚くなっていくはずです。
第11章 まとめ|「許諾・表示・規約順守」がすべての基本
切り抜き動画は、元のコンテンツに新しい価値を加え、視聴者により身近な形で楽しんでもらえる優れた手法です。
しかし、その裏には多くの権利とルールが存在し、それを理解せずに行うと一瞬で信頼を失います。
本記事の内容を要約すると、守るべき原則はたった3つです。
- 許諾を得ること
どんなに短いシーンでも、他人の著作物を扱うなら必ず権利者の許可を取る。 - 出典・クレジットを明示すること
誰の作品で、どこから引用したのかを明確に示す。 - プラットフォームの規約を順守すること
法律よりも先に、利用しているサイトのルールを確認する。
この3つを徹底するだけで、トラブルの多くは防げます。
切り抜き動画を作る行為は、単なる転載ではなく新しい創作の一形態です。
だからこそ、「敬意」と「透明性」が求められます。
正しい手順を踏めば、切り抜きはオリジナル制作者にとってもプラスになり、双方が利益を得られる関係を築けます。
もし、どうしても判断に迷うときは、「これは相手の立場で見たらどう映るだろう?」と一度立ち止まって考えてみてください。
その一瞬の慎重さが、あなた自身のチャンネルを長く守ることにつながります。
次のステップ
この記事で紹介した手順を踏まえ、実際に許諾文やクレジット例を使ってみてください。
さらに実務的なテンプレート(同意書・メール文面・異議申立て対応文など)を知りたい方は、下記の有料noteで詳しく解説しています。
▶ 有料版:切り抜き動画の実務完全マニュアル(許諾交渉ログ・雛形セット付き)
ここまで読んでくださった方は、すでに「切り抜き動画を安全に扱うための基礎」を完全に理解しています。
これからは、正しい知識を持つクリエイターとして、安心して発信を続けてください。