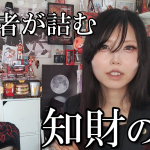当ページでは、皆様からよく寄せられる質問と回答をご紹介します。
ご不明な点やさらに詳しい情報、個別相談が必要な場合には、お気軽にお問い合わせください。
1.サービス内容に関するご質問
Q. 相談・依頼方法を教えてください。
A. 当事務所へのご相談について、「お問い合わせ」ページ>お問い合わせフォームからお願いします。
お問い合わせフォームにはいくつか記入欄を設けているため、お手数ですが、必要事項を明記のうえ送信をお願いします。
Q. 無料相談は行っていますか。
A. 当事務所では、無料相談を行っておりません。
原則、1時間あたり5,000円(税別)を目安に、「対面」「ビデオ通話」のいずれかの方法にて承っています。
Q. 相談時に必要なものはありますか。
A. 事案や内容によりますが、下記のものをご用意ください。
- 身分証明書
- ご相談内容に沿った書類等
料金は1時間あたり5,000円(税別)ですが、遠方の場合、交通費や日当のお支払をお願いする場合がございます。
「相談内容に沿った書類等」とは、当事者の戸籍書類や、不動産の情報が確認できる登記簿謄本等をいいます。
必ず用意していただかなければならないわけではなく、当該書類があることで、より有意義な内容にできるものなので、お問い合わせの際に詳細はお尋ねください。
Q. 問い合わせ後、どれくらいで返信がもらえますか。
通常であれば、5営業日以内に返信いたします。
混雑状況によりお時間をいただく場合もございますので、ご了承ください。
2.支払に関するご質問
Q. 支払方法の選択肢を教えてください。
A. 現金、銀行振込に対応しています。
Q. 領収書はどのように受け取れますか。
A. 原則、お支払完了後、PDF等のデジタル形式に加え、紙媒体での発行も可能です。
また、必要に応じて郵送対応も行いますので、お気軽にお申し付けください。
3.各コンテンツに関するご質問
Q. ブログに掲載されている写真を使用したいのですが、どうすればいいですか。
A. 当事務所で使用している写真等は、一部を除き、下記のサイト様が提供するフリー素材です。
このため、当事務所から直接誤使用になるのではなく、各サイト様にてアカウント登録等を経て、適切にご使用いただくよう、よろしくお願いします。
| サイト名 | ホームページアドレス |
|---|---|
| かわいいフリー素材集 いらすとや | かわいいフリー素材集 いらすとや (irasutoya.com) |
| フリーのイラスト素材集 ちょうどいいイラスト | 商用可・フリーイラスト素材集|ちょうどいいイラスト (tyoudoii-illust.com) |
| Loose Drawing | 無料で商用可のフリーイラスト素材|Loose Drawing |
| photoAC | 写真素材なら「写真AC」無料(フリー)ダウンロードOK (photo-ac.com) |
上記以外の写真について、榊原が撮影したものは「PIXTA」にて販売していますので、ご活用ください。
Q. ブログの記事や動画を拡散したいんですが、どうすればいいですか。
A. 当事務所のブログ、動画ともにリンクフリーです。
ただし、下記にご注意ください。
- リンク先は、当事務所の公式サイトや動画が掲載されている公式チャンネルなど、正規のリンク先に設定してください。
- 直接のファイルリンク、第三者による再アップロードリンクはご遠慮ください。
- 動画を埋め込む場合、当事務所の公式プレイヤー(YouTube等の埋め込みコード)をご使用ください。
- 当事務所のWebサイトが他のWebサイトの一部として表示されないよう、ご配慮ください。
- 当事務所が誤解を招く形や、不適切なコンテンツにリンクすることはご遠慮ください。
- 動画の一部を使用する場合やサムネイルとして画像を利用する場合、事前に当事務所の許可を得てください。無断での改変・商用利用は固くお断りします。
- 榊原の商標である「ヲタク行政書士®」を使用する際は、事前の許可を得てください。
当事務所が発信する情報が広く正確に伝わるよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
Q. 写真を待ち受け画面にしてもいいですか。
A. 当職が撮影した写真を待ち受け画面としてご使用いただけること、大変光栄に思いますが、下記の点にご留意ください。
- 写真を利用する場合、個人の待ち受け画面等、非商用・私的利用の範囲内にてお願いします。
- 写真を無断で改変することはご遠慮ください。
- 写真を他者と共有することは、原則、禁じます。
応援していただけることについて、心より感謝しております。
今後ともよろしくお願いいたします。

| 受付・ご対応時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 - 17:00 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ― | ― |
- ※ ▲ AMのみ
- ※ ネット問い合わせは、随時受付中
- ※ 打合せ・現地訪問については上記時間外でもご対応が可能です
 よくある質問
よくある質問