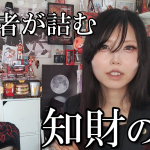当サイトの一部に広告を含みます。

当ページでは、特別寄与料を請求できる人(事例)と方法、注意点を解説します。
Contents
特別寄与料とは
特別寄与料とは、相続人以外の親族が被相続人の財産に関し、維持・増加に貢献する行為を行った場合、貢献者から相続人に対し、請求できる金銭を指します(民法第1050条)
(1)特別寄与料を請求できる人
特別寄与料を請求できるのは、被相続人の財産の維持または増加について、特別の貢献をした配偶者、6親等内血族、3親等内姻族です(民法第725条)
しかし、親族のうち、下記に該当する人は対象外となります(民法第1050条第1項)
- 相続人
- 相続放棄をした元相続人
- 相続欠格または廃除により相続権を失った人
- 離婚した元配偶者
- 内縁の夫または妻
- 血族または姻族ではない人
(2)特別寄与料と寄与分の違い
寄与分とは、被相続人の財産について、維持または増加に特別の貢献をした相続人がいる場合、貢献度に応じ、通常の相続分に加える形で受け取る遺産を指します(民法第904条の2)
特別寄与料と寄与分には、下記の通り、いくつか異なる点があります。
| 寄与分 | 特別寄与料 | |
|---|---|---|
| 請求できる人 | 配偶者 子または孫 父母または祖父母 兄弟姉妹 | 配偶者 6親等内血族 3親等内姻族 |
| 要件 | 1.通常期待される程度を超える特別の貢献があったこと 2.被相続人の財産の維持または増加と因果関係があること 3.相続人の一定の行為により、被相続人の財産の維持または増加があること | 1.被相続人に対し、療養看護その他の労務を無償で提供したこと 2.無償の療養看護や労務の提供により被相続人の財産が維持または増加したこと |
| 請求方法 | 1.遺産分割協議 2.調停・審判 | 1.特別寄与者から相続人に対し、請求 2.当事者同士で協議 3.調停・審判 |
| 請求期限 | なし | 下記のいずれか早い期間の経過により、家庭裁判所に対し、協議に代わる処分を請求できなくなる 1.相続開始および相続人を知った日から6か月を経過したとき 2.相続開始のときから1年を経過したとき |
| 根拠条文 | 民法第904条の2 | 民法第1050条 |
特別寄与料の請求時に満たすべき要件
特別寄与料を請求するには、下記の要件を満たす必要があります(民法第1050条第1項)
- 被相続人の親族であること
- 被相続人に対し、療養看護その他の労務を無償で提供したこと
- 相続財産の維持または増加に因果関係があること
1.被相続人の親族であること
被相続人の親族とは、配偶者、6親等内血族、3親等内姻族を指します(民法第725条)
親族であっても、相続人に該当する人、相続放棄をした元相続人、相続欠格または相続廃除により相続権を失った人は含まれません。
また、親族に含まれない第三者も対象外となるだけでなく、内縁の夫または妻も含まれない点に注意しましょう。
2.被相続人に対し、療養看護その他の労務を無償で提供したこと
特別寄与料の請求対象となるのは、被相続人に対する療養看護またはその他の労務を無償で提供した場合に限られます。
例えば、被相続人が寝たきりであり、自宅で長期間介護を行ったケースや、生活に困窮している際に金銭的な支援に加え、その関連業務を行ったようなケースが考えられます。
3.相続財産の維持または増加に因果関係があること
特別寄与料を請求するには、特別寄与者が行った療養看護その他の労務により、被相続人の財産が減少するのを防いだ(維持)または増加した事実が求められます。
例えば、被相続人が不動産を所有していた場合、特別寄与者が無償で賃貸管理や手続業務を支援した結果、収益が確保され、被相続人の財産が増加したようなケースが考えられます。
被相続人の療養看護をサポートした対価として金銭を受け取っていた場合や、単に療養看護を行った事実だけでは当該要件を満たすと認められない点に注意しましょう。
特別寄与料の請求方法
特別寄与料を請求するには、下記の手続を検討します。
- 当事者間での話し合い
- 家庭裁判所に申立て
1.当事者間での話し合い
特別寄与料は、特別寄与者から相続人との話し合いにより決定することになります。
寄与分の場合、寄与者も相続人の1人なので遺産分割協議の場で決定することになりますが、特別寄与者は相続人ではないため、必ずしも遺産分割協議に参加できるとは限りません。
しかし、特別寄与料が支払われることになった場合、相続分に影響を及ぼすことになるため、遺産分割協議が行われる前に請求することをオススメします。
2.家庭裁判所に申立て
特別寄与者と相続人の間で特別寄与料を決定するのが困難な場合、家庭裁判所に対し、特別の寄与に関する処分の調停・審判を申立てることができます。
調停の申立先は、請求相手となる相続人の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者の合意により定める家庭裁判所が管轄です。
相続人が複数いる場合、特別寄与料の請求は、相続人全員または一部を選択して行うことができます。
調停がまとまらない場合、家庭裁判所は審判により特別寄与料を決定し、相続人に支払を命じることができます。
請求相手に相続人の一部のみを選択した場合でも、特別寄与料は各相続人の法定相続分または遺言による指定相続分に応じた額となります(民法第1050条第5項)
特別寄与料の計算方法
特別寄与料の金額や計算方法について、法律に規定はありません。
そのため、原則的には当事者同士の話し合いにより決定することになります。
ただし、特別寄与料の請求対象が「療養看護またはその他の労務の提供」であることから、監護・介護や事業に従事した場合の計算方法を目安として算定することができます。
(1)被相続人の療養看護を行っていた場合
特別寄与者が被相続人の療養看護を行っていた場合、下記の計算式を用いることができます。
特別寄与料=療養看護の日数×プロに頼んだ場合の報酬相当額×裁量割合
療養看護の日数について、入院及びプロによる療養看護サービスを受けた期間は含みません。
プロに頼んだ場合の報酬相当額とは、介護報酬基準等をもとに1日あたりの報酬額を用います。
裁量割合とは、裁判所が個々の事情を勘案して判断するもので、概ね0.5~0.8倍を目安に設定されます。
具体的には、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他の事情を考慮し、裁量的割合にて調整されることになります。
(2)被相続人の事業に労務を提供していた場合
特別寄与者が被相続人の事業に労務を提供していた場合、下記の計算式により求めることができます。
特別寄与料=本来であれば得られた年収×(1-生活費控除割合)×寄与年数
本来であれば得られた年収とは、被相続人の事業と同種・同規模・同年齢の年間給与額を参考に算出します。
生活費控除割合は、生活費の負担分を控除した額を指します。
特別寄与料を認めてもらうには、被相続人の療養看護に貢献したこと、又は労務を提供していたことを示す下記のような証拠が必要です。
・介護または従事したことを示す記録
・レシート、領収書など
・メール、メッセージアプリ等の記録など
特別寄与料と相続税
特別寄与料の額が決定した場合、被相続人からの遺贈とみなし、相続税の課税対象となるだけでなく、2割加算の対象となる点に注意しましょう。
いっぽう、特別寄与料を支払った相続人側は、相続分から特別寄与料を控除した額を課税額として相続税を算出することができます。
相続税の申告・納税期限までに特別寄与料が確定しない場合、更正の請求を行うことで還付を受けることが可能です。
特別寄与料の請求方法、注意点まとめ
当ページでは、特別寄与料を請求できる人、請求方法と注意点を解説しました。