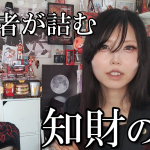当サイトの一部に広告を含みます。
当ページでは、飼主が先に死亡した場合に備え、ペットに財産を残す方法、注意点を解説します。
Contents
関連投稿
引き取り手のいないペットの行く末
飼主の死亡後、ペットの引き取り手がいない場合、原則、保健所に保護されます。
保健所に収容された動物は、保護期限満了後、殺処分となります。
期間満了前の場合でも、譲渡適性がないと判断された場合、病気、けが等の理由で亡くなる動物もいます。
ペットに相続権はない
日本国内において、人以外の生き物が財産を譲受けることはできません。
このため、ペットに財産を残すには、ペットの面倒を見てくれる人 または 法人等の団体に託す方法が考えられます。
ペットに財産を残す方法
ペットに財産を残す方法には、次の選択肢があります。
- 遺言書による遺贈
- 贈与契約
- 家族信託
1.遺言書による遺贈
遺言作成者である飼主が、遺言の中に「ペットを飼育することを条件に、飼育に必要な財産を譲る」と記載しましょう。
一定の条件をつけて遺贈することを、負担付遺贈といいます。
具体的には、次の内容を記載します。
- 遺贈相手の氏名、住所、連絡先
- ペットの飼育方法等
- 遺贈する財産の金額、保管場所
1-1.負担付遺贈の注意点
負担付遺贈は、遺言作成者が一方的に指定できることから、受遺者(指定された人)には遺贈を拒否する権利があります。
受遺者は、自分が受遺者であることを知った日から、原則、3か月以内に遺贈の放棄 または 承認手続を行う必要があります。
(1)遺言により、遺言執行者を指定する
(2)生前、受遺者に話をしておく
等の対策をしておくと安心ですね。
2.贈与契約
ペットに財産を残すためには、下記の贈与契約が考えられます。
- 負担付死因贈与契約
- 負担付生前贈与契約
2-1.負担付死因贈与契約
負担付死因贈与契約とは、贈与者(飼主)と受贈者(受け取る側)で、生前に契約を交わすものです。
負担付遺贈の場合、遺言作成者が一方的に指定しますが、この場合、双方の同意がなければ成立しないうえに、契約後は特別な事情がない限り、両者撤回することができません。
2-2.負担付生前贈与契約
負担付生前贈与契約とは、飼主が生きている間にペットを任せる契約を結ぶものです。
ペットが人見知りする場合や飼主が世話をできない状況にある場合には、負担付生前贈与契約を検討しましょう。
3.家族信託
家族信託の場合、飼主とペットの世話を託される側とで信託契約を締結します。
契約という点では、負担付死因贈与契約、負担付生前贈与契約と同様ですが、飼育に係る費用を「信託財産」として、あらかじめ飼主の財産から切り離す必要があります。
信託契約では、信託の開始条件、飼育内容の希望、ペットの葬儀に関する希望のほか、任される人(受託者)に何かあったときについても定めることができます。
信託契約で定めた内容について、受託者がきちんと履行してくれるか不安な場合、裁判所に「信託監督人」の選任を申立てることも可能です。
信託監督人は、信託契約の目的、内容が適切に履行されているかを監督する役目を担います。
受託者に何かあったときについて、何の取り決めもされていない場合、元の飼主の相続人がお世話を引き継ぐことになります。
相続税がかかる場合に注意
死亡人からペットの飼育に必要な財産を受け取った場合、相続税がかかります。
負担付死因贈与契約の場合、贈与税ではなく、相続税の対象となります。
ただし、相続税には基礎控除額が設けられており(3,000万円+600万円×法定相続人の数)、相続人は当該控除の適用を受けることができます。
ペットに財産を残す方法と注意点まとめ
当ページでは、ペットに財産を残す方法と注意点を解説しました。