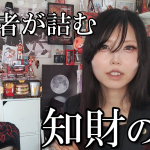当サイトの一部に広告を含みます。

Contents
筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′) / 榊原行政書士事務所 代表行政書士 / 3級FP技能士 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること
発信者情報開示命令とは
SNS等のインターネット上の投稿により、自分の権利を侵害された人は、一定要件を満たすことで下記の相手に対し、発信者情報開示命令の申立を行うことができます。
- SNS等を運営するコンテンツプロバイダ(CP)
- SNS等に侵害情報を記録するアクセスプロバイダ(AP)など
発信者情報開示命令の申立手続
発信者情報開示命令の手続は、下記の流れで行います。
- CPが持つ発信者情報の開示・提供命令の申立
- 申立書の写しがCPに送付される
- 裁判所の決定により、下記の命令が下される
a.申立人に対し、IPアドレス等の情報から特定されるAP情報を提供すること
b.申立人から通知があった場合、保有する発信者情報をAPに提供すること - 上記a.を基に、APに発信者情報の開示命令、消去禁止命令の申立を行い、CPに通知
- 申立書の写しがAPに送付される
- 3-b.を基に、CPからAPに発信者情報を提供
- 裁判所の決定により、審理に必要な期間中の発信者情報の消去禁止命令が下される
- 裁判所が当事者の意見を聴取し、開示命令に関する審理開始
- 裁判所により発信者情報開示命令が出ると、申立人に発信者情報が開示される
発信者情報開示命令の申立て先
発信者情報開示命令の申立て先は、下記の通りです。
| a.原則的な管轄 | 1.相手方の主たる事務所 または 営業所の所在地を管轄する地方裁判所 2.申立が相手方の事務所 または 営業所における業務に関する場合、当該事務所 または 営業所の所在地を管轄する地方裁判所 3.1および2の事務所が海外の場合、代表者その他主たる業務担当者の住所地を管轄する地方裁判所 4.上記1から4により管轄裁判所が定まらない場合、東京地方裁判所 |
| b.競合管轄 | 東日本の地方裁判所がa.の原則的な管轄権をもつ場合、当事者の選択により、その地方裁判所のほか、東京地方裁判所にも申立て可 |
| c.合意管轄 | 上記の規定に関わらず、当事者が合意により定める地方裁判所への申立て可 |
申立に必要な書類
発信者情報開示命令の申立には、下記の書類が必要です。
- 申立書
- 申立書の写し
- 申立を理由づける具体的な事実ごとの証拠
- 当該申立に係る会社の登記事項証明書
- 手続代理人の委任状(代理人に委任する場合)
- 管轄上申書(外国法人について、管轄を認める場合)
申立手数料
発信者情報開示命令の申立手数料は、1個の申立ごとに1,000円の収入印紙が必要です。
発信者情報提供命令、消去停止命令の申立
発信者情報提供命令、消去停止命令の申立については下記の通りです。
申立て先
発信者情報開示命令事件が係属する裁判所に申立てを行います。
申立書の添付書類
提供命令、消去禁止命令の申立は、発信者情報開示命令の申立と同じ書面で行って構いません。
ただし、開示命令申立書と別の書面で申立を行う場合、相手方への送付用として、提供命令 または 消去禁止命令の申立書の写しも提出する必要があります。
相手方となるAP、CPへの送付用ですね。
申立手数料
提供命令、消去禁止命令の申立費用は、1個の申立ごとに1,000円です。
発信者情報開示命令のメリット
発信者情報開示命令を利用するメリットは、従来の制度に比べ、費用、期間共に縮小されたことで、申立人の負担が軽減された点です。
従来の手続では、IPアドレス開示の仮処分手続に2,000円、発信者の住所氏名開示訴訟に13,000円が必要でしたが、発信者情報開示命令制度の場合、いずれの費用も1,000円です。
開示命令2回、提供命令、消去禁止命令の申立で合計4,000円なので、3分の1ですね。
発信者情報開示命令の申立てを行う際の注意点
発信者情報開示命令の申立てを検討する場合、下記に注意しましょう。
1.削除、損害賠償請求はできない
発信者情報開示命令の申立て手続は、あくまでも「開示請求」に過ぎません。
このため、問題となる投稿の削除、損害賠償請求を行うことはできない点に注意しましょう。
削除請求や損害賠償請求が目的の場合、別で訴訟を起こす必要があります。
2.従来の制度と同様の要件が求められる
発信者情報開示命令の申立てにおいても、原則、下記の要件を満たす必要があります。
- 特定電気通信による情報の流通であること
- 請求者が自己の権利を侵害された本人であること
- 権利を侵害されたことが明らかなこと
- 情報開示を求める正当な理由があること
- 相手方が発信者情報をもっていること
- 開示を求める内容が発信者情報であること
上記1.の要件は、「不特定の者により受信されることを目的とした電気通信の送信」と定義づけられ、インターネット上のSNS、ブログ、動画共有サイトのコメント欄等が該当します。
このため、DM、メッセンジャー等による「特定の個人に向けた送信」は対象外となり、発信者情報開示命令の対象外となる点に注意しましょう。
このほか、3や4についても具体的に証明する必要があるため、悩んだ時は弁護士までご相談下さい。
3.発信者の特定可能なところまで開示されない
発信者の氏名、住所を特定するには、発信者情報開示命令で開示されるのは、問題となる投稿を送信した回線の契約者情報に過ぎません。
投稿者自身が契約する回線から当該投稿を行っていればいいのですが、公衆Wi-Fi等の不特定多数が利用可能な回線を利用した場合、回線の契約者情報だけでは足りません。
投稿がネットカフェ、ホテル等の回線から行われた場合、開示情報を足がかりにこれらの施設に協力を依頼し、犯人を特定できる可能性はありますが、発信者情報開示命令だけでは不可能です。
とはいえ、手続が迅速化されたことにより、投稿者の特定可能性は高くなったことには違いありませんので、本気で相手を特定したい場合には、早めに弁護士に相談されることをオススメします。
発信者情報開示命令の申立手続、注意点まとめ
当ページでは、発信者情報開示命令の申立手続、注意点を解説しました。